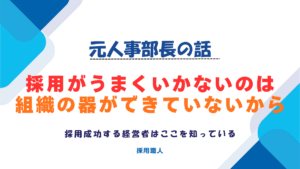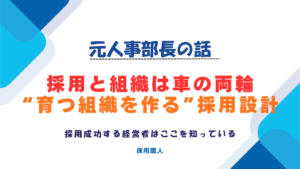組織が成長しないのは採用戦略がとまっているからだ
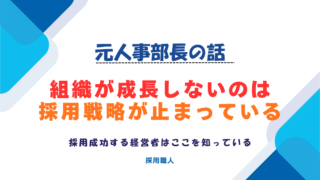
「人を採ったのに、なぜ会社が変わらないのか?」
「求人を強化したのに、現場は変わらない」
「人が入っても、定着せず、組織が回らない」
──そんな声を、建設業の経営者から毎月のように聞きます。
でも、それは“人が悪い”わけでも“若者の質が落ちた”わけでもありません。
原因は、採用戦略が止まっているから。
採用とは、単なる「人集め」ではなく、
会社を前に進めるための経営装置です。
採用が止まれば、会社の成長も止まる。
組織は、“採用戦略の質”で決まるのです。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
データが示す「採用戦略と組織成長の関係」
リクルートワークス研究所の調査によれば、
中小企業のうち「採用を経営戦略と連動させている企業」は全体のわずか32%。
しかし、その企業群では──
- 離職率:▲28%
- 売上成長率:+46%
- 従業員満足度:+52%
という結果が出ています。
つまり、採用戦略を“経営戦略の中で回している会社”ほど、
組織が安定し、成長しているということ。
参考:リクルートワークス研究所「中小企業の採用構造変化レポート2024」
https://www.works-i.com/research/
採用が止まる会社に共通する「構造の欠落」
採用がうまくいかない会社には、共通する構造的な欠陥があります。
それは「採用→育成→定着→成果」の流れが、バラバラなこと。
典型的なケース:
- 採用は人事や広告会社に任せる
- 教育は現場に丸投げ
- 定着は“本人次第”
- 評価は曖昧
結果、誰も「組織を育てる構造」を見ていない。
経営者は“今の売上”を見て、
現場は“今日の人手”を見て、
人事は“応募の数”を見ている。
バラバラの視点では、組織は成長しません。
採用戦略が止まると、組織の血流が止まる。
採用は“組織の循環を生むポンプ”なんです。
「採用しても、回らない会社」
以前、私が支援した地方の中堅建設会社(社員25名)は、
年間200万円の広告費を使っても応募が10件未満。
社長は言いました。
「とにかく人を採りたい。広告会社に全部任せている」
しかし入社した若手は3ヶ月で辞め、
現場リーダーは疲弊、教育も手探り。
その後、社長にこう提案しました。
「採用を経営戦略の中に戻しましょう」
実施したこと
- 経営計画に“人材戦略ページ”を追加
→「今年、どんな人を採り、どう育てるか」を明文化 - 採用KPIを設定(応募・面接・定着を月次管理)
- 教育担当を固定し、育成マニュアルを整備
半年で応募200名、採用20名。
離職率10%以下。施工量は2倍。
「採用が回る=組織が育つ」ことを経営者自身が実感した瞬間でした。
「採用を“活動”でなく“構造”として設計せよ」
ほとんどの会社が、採用を「イベント」として扱っています。
- 忙しくなったら採用
- 辞めたら募集
- 広告会社に頼む
これでは、採用が“毎回リセット”される。
経験もデータも蓄積せず、改善が起こらない。
一方、“構造としての採用”を持つ会社は違います。
採用を、
① 経営の意思決定
② 数字によるPDCA
③ 教育・評価への循環
この3つで回している。
採用を仕組み化した会社ほど、採用費は減り、組織は強くなる。
改善策①:採用を「経営計画」に埋め込む
採用は、“経営会議の議題”に戻すところから始まります。
たとえば、経営計画書の中に「人材戦略ページ」を設ける。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 採用目的 | 3年後に班数を2→4班に拡大 |
| 採用人数 | 職長候補2名、若手3名 |
| 教育体制 | 現場長+OJTリーダー固定 |
| 採用KPI | 応募30名/採用5名/定着率80%以上 |
このように、採用を経営数字と連動させる。
採用KPIを追うことで、
「採用が経営を動かしている」ことが可視化されます。
改善策②:「採用設計図」を作る
建設業には図面があるように、採用にも“設計図”が必要です。
設計図の要素は4つ。
- 目的設計:なぜ採るのか
- 人物設計:どんな人を採るのか
- 導線設計:どのルートで出会うか
- 評価設計:どう判断するか
これを明文化して初めて、採用は“再現性”を持つ。
採用設計がない会社は、毎回ゼロから建て直す家と同じです。
計画がある会社は、同じ型で確実に成果を積み上げられる。
👉 詳しくは:
「技術者が集まる会社」は求人原稿がうまいのではなく“仕組み”が違う
改善策③:採用と育成をつなぐ“評価構造”を整える
採用した人を育てるのは、教育だけではありません。
評価の仕組みが重要です。
「頑張りが見える会社」には人が定着する。
「評価が曖昧な会社」には人が育たない。
たとえば──
- 新人(1年目):出勤・安全・報連相で評価
- 中堅(2〜3年目):段取り・責任感・技術力
- 職長(3年目以降):育成力・チーム管理
こうした評価基準を明確にすることで、
「自分はどこに向かっているのか」が社員に伝わる。
これが“育つ組織”の必須条件です。
改善策④:採用を“チーム戦略”に変える
採用は、経営者一人の仕事でも、人事の仕事でもない。
組織全体の戦略に変える必要があります。
採用をチームで回している会社は、成長が早い。
| 役割 | 主な責任 |
|---|---|
| 経営者 | 採用方針・最終判断 |
| 人事 | データ管理・施策実行 |
| 現場長 | 教育・面接同席 |
| 社員 | リファラル(紹介)・定着支援 |
この構造を作るだけで、採用の精度は格段に上がります。
採用は“現場で完結しない”構造こそが鍵です。
採用戦略が動き出すと、組織が動き出す
採用を経営の中に戻すと、会社全体の“流れ”が変わります。
- 採用KPIが経営KPIに連動する
- 教育・定着がデータで可視化される
- 経営判断が「人の構造」を前提に変わる
そして、社員の意識も変わる。
「採用って社長だけの仕事じゃない」
「会社を育てる仕組みなんだ」
こうした“全員経営の採用”が実現した会社ほど、
定着率が上がり、チームが活き始める。
採用戦略が動く=組織が成長する、
それは建設業でも例外ではありません。
実例:採用戦略が動いた瞬間、会社が変わった
支援したA社(社員18名)は、以前こう言っていました。
「毎年採っても、現場に残るのは1人か2人。」
採用を経営会議で扱うようにした半年後──
- 応募:月5件 → 月30件
- 採用単価:90万円 → 38万円
- 定着率:40% → 87%
- 売上:前年比170%
社長の言葉が印象的でした。
「採用戦略を止めていたのは、自分だった。
採用が動くと、会社が動く。人が動く。数字も動く。」
採用戦略を再起動させる5つの質問
あなたの会社の採用戦略は、今どこで止まっているでしょうか?
以下の質問に“はい”と答えられなければ、戦略は止まっています。
- 採用目的を経営計画に明文化しているか?
- 採用KPIを毎月チェックしているか?
- 育成フローを可視化しているか?
- 評価基準を全社員で共有しているか?
- 採用改善を会議で議題化しているか?
1つでも「いいえ」があれば、
採用戦略のどこかで“循環”が止まっています。
まとめ:採用を動かせば、組織は勝手に育つ
- 採用が止まれば、組織の成長も止まる
- 採用戦略は「人を集める活動」ではなく「組織を育てる装置」
- 経営に採用を戻すことで、会社全体の循環が生まれる
採用は、気合でも予算でもなく、構造設計で決まる。
その構造づくりを体系化したのが、
採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から採用導線、教育・定着までを一気通貫で支援。
“採って終わり”から“育って回る組織”へ。
御社の採用を「成長戦略」に変えるお手伝いをしています。
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用は、会社の未来を動かす“エンジン”です。
そのエンジンを止めたままでは、
どんなに現場が頑張っても、会社は前に進めません。
採用戦略を再起動させましょう。
それが、組織成長の第一歩です。