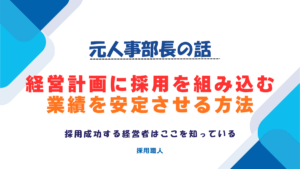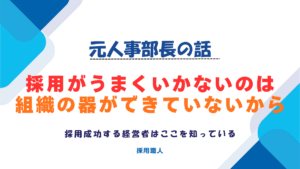採用を“現場任せ”から“経営戦略”に変える3つの思考転換
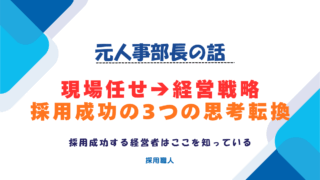
経営者に問いたい──「採用」は本当に“現場の仕事”ですか?
「うちは採用は現場の判断でやってるよ」
建設業の社長から、そんな言葉をよく聞きます。
でも、よく考えてみてください。
採用とは、「未来の売上をつくる投資」です。
ならば、それを経営判断から切り離すこと自体がおかしいと思いませんか?
私は元建設会社の人事部長として、
年間200万円の広告費をかけても応募が10人以下、採用ゼロ──そんな状態から、
応募200人・採用20人を達成した経験があります。
変わったのは、“やり方”ではなく“考え方”でした。
経営者が「採用を戦略の中心に戻す」と決めた瞬間、全てが動き出したんです。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
きっかけは「社長が採用に興味がない」から始まった
数年前、ある地方の建設会社を支援したときの話です。
社長は40代半ば。社員20人ほどの中堅会社でした。
当初の相談内容はこうでした。
「人が全然来ない。広告会社に頼んでも反応ゼロ。
もう採用は運任せですよ。」
話を聞くと、求人内容も面接も全部“現場任せ”。
採用方針を聞いても、「まあ、真面目で続けてくれれば誰でも」と言う。
──これでは採れるはずがありません。
採用は「誰でもいい」ではなく、
“誰を採るかを決める経営の意思”が必要なんです。
データが示す「経営が採用を握る会社ほど採れている」
リクルートワークス研究所の2024年調査によれば、
中小企業で経営者が採用戦略に関与している割合は34%。
しかし、採用成功企業では72%の経営者が直接関与しています。
つまり、「採れる会社」は、経営者が採用を事業戦略の延長線として扱っている。
参考:リクルートワークス研究所『中小企業の採用構造変化レポート2024』
https://www.works-i.com/research/
現場任せの採用が生む3つの“ズレ”
では、なぜ「現場任せ採用」では上手くいかないのか?
理由はシンプルで、経営・人事・現場の意識がズレるからです。
1. 求める人物像のズレ
経営者は「会社の未来を担う人」を採りたい。
でも現場は「今、手が足りない人」を求める。
→ 結果、目先の人手補充ばかりが続き、長期戦略が崩れる。
2. 採用目的のズレ
経営者は「事業拡大のための採用」を考えている。
現場は「楽になるための人員補充」を望む。
→ 採っても成果が出ず、すぐ辞める。
3. 評価基準のズレ
現場は“技術力”を重視、経営は“人間性”を重視。
どちらが正しいかではなく、軸が揃っていないのが問題。
この3つのズレが積み重なると、採用は永遠に迷走します。
採用を“経営戦略”に変える3つの思考転換
ではどうすれば、採用を「現場任せ」から「経営主導」に変えられるのか?
ここからが本題です。
思考転換①:「採用=経営資源の再配分」として考える
多くの経営者は「人がいない」と言いますが、
実際には“どんな人を、どの役割に、どう配置するか”が決まっていない。
採用を「労働力確保」ではなく、
**“経営資源の再配分”**として考えることが第一歩です。
たとえば、
「1人の即戦力を探すより、3人の育成枠を設ける」
この判断だけで、採用の打ち手はまったく変わります。
思考転換②:「採用=営業活動」として設計する
採用は「人を選ぶ活動」ではなく、「人に選ばれる活動」です。
つまり、営業と同じ。
求人原稿は“会社の営業資料”であり、
面接は“商談”であり、
内定通知は“契約提案”です。
この視点を持つだけで、採用の成果は変わります。
- 原稿が「募集文」から「価値提案」に変わる
- 面接が「確認」から「共感形成」に変わる
- 内定が「通知」から「約束」に変わる
実際、当社が支援した企業でも、
求人文の構成を「採用営業」に変えたところ、応募率が2.8倍に上がりました。
詳しくはこちらの記事も参考にしてください →
採用で“写真”が9割を決める──建設業で応募率を2.8倍にした「見せ方」の設計
思考転換③:「採用=理念の浸透活動」として位置づける
経営理念が浸透していない会社ほど、採用が空回りします。
なぜなら、採用は“理念の入り口”だからです。
私が支援したある会社では、
求人原稿の冒頭に社長の言葉を入れました。
「うちの仕事は楽ではない。
けれど、“自分の手で形を残す”ことに誇りを持てる人に来てほしい。」
この一文だけで、応募者の質がガラッと変わりました。
理念を言語化できる会社ほど、人が集まる。
それは、経営が「何のために人を採るのか」を自覚しているからです。
実際に採用構造を変えた建設会社の話
ある中堅建設会社(社員25名)は、
毎年200万円以上の広告費を使っても、応募は5〜6人。採用ゼロ。
そこで経営者と一緒に、採用の構造を根本から見直しました。
- 経営計画と採用計画を連動
→「3年で施工チームを2班→4班に拡大」と明確に設定。 - 採用会議を毎月開催
→広告会社ではなく、社長+人事+現場リーダーで議論。 - 理念ベースの原稿設計に変更
→「どんな想いで働く会社か」を全面に出す。
結果、半年で応募が200人に増加。
採用単価は約40万円、離職率は半年後に0%。
経営者が採用を“数字で管理”したことで、
採用は経営の成果指標の一つになりました。
経営者がすぐ実践できる「採用構造改革のステップ」
では、今日からできる実践法をお伝えします。
ステップ1:経営方針に採用を組み込む
経営計画書の中に「採用方針」という1ページを設ける。
「どんな人を、なぜ、どの期間で採るか」を明文化する。
ステップ2:採用KPIを設定する
応募数・面接率・定着率を「経営KPI」に加える。
採用は“数字で語る”ことで改善が進む。
ステップ3:現場との連携ルールを明文化
現場が“欲しい人”、経営が“必要な人”。
そのギャップを会議で埋める仕組みをつくる。
この3つをやるだけで、採用のブレは劇的に減ります。
関連して、実践の全ステップをまとめた記事はこちら →
建設業の採用はお任せください。母集団の形成に成功応募件数UP!
「採用は経営判断である」という覚悟が会社を変える
採用を変えるのに、派手な戦略も最新ツールも要りません。
必要なのは、経営者の“覚悟”です。
「人が足りない」ではなく、
「人をどう増やすかを自分が決める」と宣言すること。
経営者が採用に関わる会社は、理念が伝わる。
理念が伝わる会社には、人が集まる。
それが経営主導型採用の本質です。
採用は「経営の言葉」で語る時代へ
私は人事部長時代、こう感じていました。
「社長が採用を語る会社ほど、応募者が信頼してくれる」
逆に、社長が採用を“外注化”している会社は、
どれだけ広告費をかけても、信頼を得られません。
採用は、数字ではなく“理念”で人を動かす時代。
そして理念は、経営者しか語れません。
まとめ:採用を経営の延長線に戻そう
- 採用を「現場任せ」にすると、方針がバラバラになる
- 採用を「経営戦略」にすると、全ての判断軸が揃う
- 経営者が採用を語れる会社は、信頼され、選ばれる
採用は、気合でも予算でもなく、仕組みで決まります。
その“仕組み”をつくる支援をしているのが、
採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から応募導線の最適化までを一気通貫で支援し、
“経営主導の採用構造”を社内に根づかせます。
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用を“現場任せ”にしている会社は、人が集まらない。
逆に、経営者が採用を“語る会社”は、未来を創る人が集まる。
あなたの会社は、どちらの採用を選びますか?