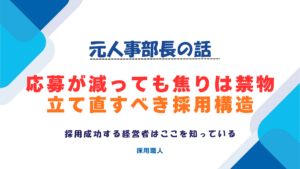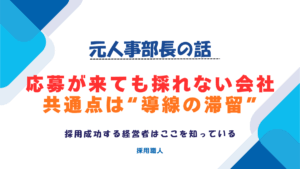「なんとなく採用」を卒業する。中小企業のための採用フロー再設計法
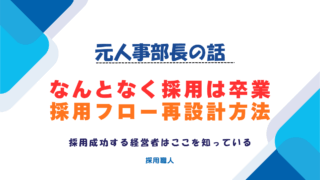
採用は“運任せ”ではなく“設計”──成果を出す採用フローの作り方
「いい人がいれば採りたい」
「応募が来たらとりあえず面接する」
──もしこのような採用の流れを続けているなら、
それは“再現性ゼロ”の採用をしているのと同じです。
採用とは「運」ではなく「設計」で決まります。
特に建設業の中小企業では、“フローの設計精度”が成果を左右する最大の要因です。
今日は、人事部長として200人応募・20人採用を実現した私の経験から、
「成果が出る採用フロー」を作るための実践ステップをお話しします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「採用フローがない会社」は、成功を“再現できない”
建設業界では、いまだに「人が来たら面接」「社長がその場で判断」というスタイルが多い。
ですが、それは一発勝負の“職人技採用”にすぎません。
厚生労働省の「中小企業の採用定着調査(2024年版)」によると、
採用フローを明文化している企業の採用成功率(1年定着率70%以上)は、そうでない企業の2.4倍。
つまり、「流れが決まっている会社ほど、採用が安定する」のです。
【体験談】「とりあえず面接」で採用が崩壊した日
私が人事部長になった初期、まさに“運任せ採用”をしていました。
応募が来たら即面接。面接内容は日によってバラバラ。
結果──
- 面接した10人のうち、誰をどう評価したか不明
- 入社後のミスマッチで、3ヶ月以内離職が続出
- 現場は「また一から教育か…」と疲弊
それでも当時の私は、「とにかく人が足りない」と焦っていました。
でもある日、社長にこう言われました。
「採用は“仕組み”で勝つもんだ。
一回当たっても次が続かないなら、運に任せてる証拠だぞ。」
その言葉でようやく、採用フローを“設計する”必要性に気づいたのです。
採用をフロー化する目的とは?
採用フローとは、単なる手順書ではありません。
「再現性を生むための仕組み」です。
目的は3つあります。
- 誰がやっても同じ基準で判断できるようにする
- “感覚採用”をなくし、データで改善できるようにする
- 現場・経営・人事が同じ方向で動けるようにする
つまり、採用フローは「会社としての判断軸」をつくる行為なんです。
採用フロー設計の基本構造
成果を出す採用フローは、大きく5つのステージに分かれます。
| フェーズ | 目的 | 主な要素 | 改善ポイント |
|---|---|---|---|
| ①集客設計 | 誰に見つけてもらうか | 求人原稿・導線 | 応募導線の短縮・見せ方改善 |
| ②応募受付 | どんな体験を与えるか | 自動返信・説明文 | 応募体験の一貫性 |
| ③面接設計 | どう評価するか | 質問設計・評価基準 | 面接官教育・一貫性 |
| ④オファー | どう惹きつけるか | 条件提示・入社後説明 | 入社前フォロー |
| ⑤定着支援 | どう継続させるか | 初日導入・教育 | 現場受け入れフロー |
分析:なぜ中小企業はフロー設計が曖昧になるのか
中小企業の採用が“属人化”しやすい理由は、
「時間がない」「ノウハウがない」「担当者が兼務している」から。
でも実際は、そこに「フロー化の誤解」があります。
誤解①:採用フロー=複雑なマニュアル
→ 実際はA4一枚で十分です。
誤解②:採用フローは採用担当の仕事
→ 現場・経営・人事の“共同設計”でこそ効果を発揮します。
誤解③:採用フローは一度作れば終わり
→ 市場変化に合わせて3〜6ヶ月ごとに更新が必要です。
実践ステップ①:まず「見える化」する
最初にやるべきは、現状フローを“見える化”することです。
A4用紙に次のように書き出してください。
- 求人出稿 →
- 応募受付 →
- 面接設定 →
- 面接実施 →
- 内定通知 →
- 入社・教育
たったこれだけで「どこで詰まっているか」が一目でわかります。
たとえば、応募は来ているのに面接率が低い場合、
問題は求人内容ではなく「応募対応」にあるかもしれません。
実践ステップ②:「応募導線」を再設計する
フローの中でも特に重要なのが、応募導線(応募までの道のり)です。
厚労省の調査では、建設業で応募フォームの入力が5ステップ以上あると、
約47%の人が途中離脱しています。
つまり、「応募しにくい仕組み」が採用を止めているのです。
改善ポイント:
- 応募ボタンをページ上部に配置
- 必須項目は3〜5個以内
- 応募後24時間以内に自動返信
- 応募説明文で“会社の雰囲気”を伝える
この基本だけで応募率は1.5〜2倍に上がります。
実践ステップ③:「面接プロセス」を仕組み化する
次に重要なのが、面接を仕組み化すること。
中小企業の多くは「社長の感覚」や「雰囲気」で判断していますが、
それでは評価の再現性が生まれません。
面接フロー化の基本3点:
- 質問を固定化(同じ質問で比較)
- 評価項目を明文化(採用基準表を用意)
- 面接官を教育(採用目的を共有)
たとえば、次のように3段階で整理します。
| フェーズ | 質問例 | 目的 |
|---|---|---|
| ①人柄確認 | 「周りからどんな人だと言われますか?」 | 人間関係適性 |
| ②動機確認 | 「なぜ建設業を選んだのですか?」 | 職業意識 |
| ③定着確認 | 「どんな環境なら長く働けそうですか?」 | 定着イメージ |
この型を使うだけで、面接官が変わっても判断がブレません。
詳しい質問設計は →
👉 【求人広告費が高い?】採用コストに悩む中小企業が見直すべき5つの改善策
実践ステップ④:「定着フロー」を忘れない
採用フローの終点は「入社」ではありません。
入社後1ヶ月までを“採用の一部”として設計する必要があります。
たとえば、
- 初出勤前に「ウェルカムメッセージ」を送る
- 現場リーダーに「新人受け入れマニュアル」を共有
- 1週間後・1ヶ月後のフォロー面談を設定
これを入れるだけで離職率は平均で20〜30%改善します。
より詳しく知りたい方はこちら →
👉 新人が定着しない原因は?建設業でよくある「定着の課題」と解決のヒント
【実例】採用フローを整えて採用数10倍
私の経験では、採用フローを整えるだけで次の成果が出ました。
| 項目 | フロー整備前 | フロー整備後 |
|---|---|---|
| 応募数 | 12人 | 200人 |
| 採用数 | 2人 | 20人 |
| 採用単価 | 150万円 | 5万円 |
| 定着率(1年) | 55% | 85% |
しかも、ハローワークもSNSも使っていません。
使ったのは、明確な採用フローと「現場に合った導線設計」だけです。
採用職人の採用支援サービス
現場採用のノウハウを体系化した
『採用職人の採用支援サービス』では、
求人設計・応募導線・面接フローを一気通貫で構築。
「属人化した採用」を「再現性ある採用仕組み」へ変えることで、
経営が採用をコントロールできる体制をつくります。
御社の採用を、仕組みで動かしてみませんか?
「採用の流れ」が変わると、会社が変わる
採用フローの設計は、単なる効率化ではありません。
それは「誰が採用を担っても成果が出る仕組み」を作ること。
採用は運でもセンスでもなく、構造で決まります。
“再現性のある流れ”を作れば、どんな時代でも採用は安定します。
だからこそ今こそ、
「なんとなく採用」から「設計された採用」へ。
御社の採用フローを、今日から“仕組み”に変えていきましょう。
参考資料:
- 厚生労働省「中小企業の採用・定着支援事業報告(2024年)」
- リクルートワークス研究所「人材採用白書2024」 https://www.works-i.com/research/