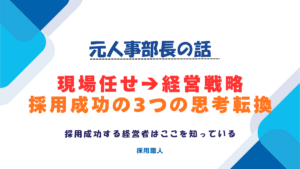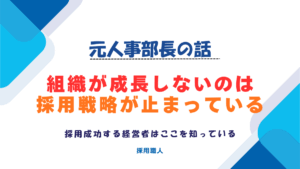「採用がうまくいかない」のは“組織の器”ができていないから
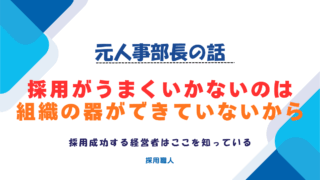
「人が育たない」ではなく「育つ器がない」
「せっかく採用しても、すぐ辞めてしまう」
「若手が育たない。中堅が疲弊している」
──そんな悩みを抱える建設会社の社長は多い。
でも、その原因は“人材の質”ではなく、
会社側の“器(構造)”ができていないことにある。
採用活動は“人を集める作業”ではなく、
“組織の器を整える作業”なのだ。
私は元建設会社の人事部長として、
年間200万円の広告費で応募10人以下、採用ゼロの状態から、
応募200人・採用20人・定着率90%を達成した。
成功の鍵は「採用を組織構造の中に戻したこと」だった。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
採用が失敗する会社の共通点──“構造の空洞化”
どれだけ熱意があっても、
「組織の構造」が整っていなければ、人は根づかない。
私がこれまで支援してきた中小建設会社を見て、
採用がうまくいかない会社に共通する特徴は、驚くほど似ている。
- 採用活動が“その場しのぎ”
→ 来月の現場が足りないから、今すぐ人を探す。 - 育成の役割が曖昧
→ 誰が新人を育てるか、決まっていない。 - 評価・報酬の仕組みが後づけ
→ 入ってから「どう扱うか」を考える。 - 社長の頭の中にしか“理想の組織像”がない
→ 現場も人事も動けず、指示待ちになる。
要するに、「採用はするが、受け皿がない」状態。
例えるなら、
新しい水を注ぎ続けているのに、バケツの底に穴が空いているようなものだ。
採用を“人数確保”で終わらせた失敗事例
私が以前担当した会社の話。
年間3人の採用目標を立てていたが、
社長の方針で「今期は一気に10人採ろう」となった。
広告を強化し、応募も増え、見た目は“成功”に見えた。
だが、半年後には──
- 10人中7人が退職
- 現場リーダーが疲弊
- 教育コストだけが残る
「せっかく採ったのに…」という嘆きが残った。
原因を分析すると、たった一つ。
組織の“育つ構造”がなかった。
採用は「入口」ではなく、「循環」の一部。
採用だけ強化しても、組織の体温は上がらない。
「採用=経営装置」仕組み化が重要
この失敗を通じて気づいたのは、
採用とは単独の活動ではなく、経営の仕組みだということ。
採用 → 育成 → 定着 → 成果 → 再投資
この循環を設計して初めて、
「採用が回る組織」になる。
つまり、“採用設計=組織設計”である。
建設業で採用に成功している会社は、
例外なくこの“構造”を持っている。
採用と組織を連動させる3つの構造設計
では、採用と組織成長をどう結びつけるのか?
答えはシンプルです。
採用前に“組織の3構造”を設計すること。
① 成長構造:どこまで育てるかを決める
人を採る前に、「どんな姿に育てたいか」を決める。
建設業では特に、“現場で学ぶ文化”が根強い。
だが、教育の仕組みを作らずに「成長しない」と嘆いても意味がない。
育成には段階が必要だ。
- 1年目:基礎スキル+安全意識
- 2年目:作業の独立+報連相
- 3年目:後輩指導+小規模現場管理
このように「3年で何を身につけるか」を設計しておくことで、
採用した人が“どこへ向かうか”をイメージできる。
👉 関連して、こちらの記事もおすすめ:
建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
② 構造構成:役割を見える化する
採用後の“混乱”は、役割の不明確さから生まれる。
たとえば、
「誰が新人の教育を担当するのか」
「報連相の窓口はどこか」
「評価は誰が行うのか」
これを曖昧にしたまま人を入れると、必ず現場が混乱する。
ある会社では、役職・役割マップを作っただけで離職率が半減した。
| 役職 | 主な責任 | 関わる採用フェーズ |
|---|---|---|
| 社長 | 採用方針・理念定義 | 面接最終判断 |
| 現場長 | 育成・評価・教育進捗 | OJT設計 |
| 職長 | 新人の指導・フィードバック | 入社後1〜3ヶ月 |
| 人事 | 募集・面接・データ管理 | 応募・面接導線 |
この“見える化”が、組織の安定を生む。
③ 循環構造:採用の成果を次に活かす
多くの会社では「採用して終わり」。
しかし、成長する会社は必ずフィードバック構造を持っている。
- 面接で感じた課題を教育設計に反映
- 現場の育成データを次期採用に活かす
- 定着率を経営会議でモニタリング
これを回すだけで、採用は“蓄積型”に変わる。
採用を単発イベントから経営ループへ。
これが、持続的な組織成長の条件です。
実例:採用の「器」を整えて成長した会社
ある地方の建設会社(社員20名)。
「人が辞めるたびに採用、また辞める」の繰り返しだった。
私が関わったのは、まず“採用を止める”ことからだった。
半年間、新規募集をストップし、以下を整備した。
- 教育担当を明確化(現場長を固定)
- 面談テンプレートを導入
- 経営会議で定着率を毎月共有
すると、不思議なことが起きた。
人を採っていないのに、社内の雰囲気が良くなった。
「新人を迎える準備が整った」と現場が言い出したのだ。
その半年後、3人を採用。
1年後の離職率は0%、施工班を1.5倍に増員。
採用を止めて“器を整えた”だけで、会社が成長した。
詳しくはこちらの記事でも紹介しています:
「採用に困らない会社」の裏にある“構造の違い”とは?
採用を「構造」で見ると、経営が変わる
採用が“現場の仕事”から“経営テーマ”に変わると、
数字の流れが変わります。
- 採用KPIが経営KPIに連動
- 定着率が利益率に直結
- 教育コストが投資指標になる
つまり、採用を構造で見ると、
経営が“人”を通じて動くようになる。
これが、組織成長の本質です。
実行ステップ:採用と組織を連動させる具体策
では、今すぐ何から始めればいいか?
以下の3ステップでOKです。
ステップ①:採用前に“育成計画”を作る
「どんな人が来ても育てられる環境」を先につくる。
OJT担当・面談頻度・教育期間を明文化する。
ステップ②:採用KPIを経営会議で共有
応募数・採用率・定着率を毎月追う。
「人の数字」を「経営の数字」に変える。
ステップ③:採用の成功・失敗を共有
現場・経営・人事が一枚の表で学ぶ仕組みをつくる。
失敗を“次の成功条件”に変える。
組織の「器」を作るのは社長の仕事
どんなに人事が優秀でも、
どんなに求人が上手でも、
組織の“器”をつくるのは経営者しかいません。
採用戦略とは、経営方針の延長線。
人を採るのではなく、「会社を育てる」視点が必要だ。
建設業の採用は、スピードよりも構造の整合性で決まる。
採用を焦るより、育つ土台を整える方が、長期的には早い。
まとめ:「採用の力=組織の器の大きさ」
- 採用がうまくいかない原因は、採用手法ではなく“組織構造”にある
- 採用を“経営の一部”として再設計することで、人は育ち、会社が回る
- 組織の器を広げることが、採用成功の最短ルート
採用は、気合でも予算でもなく、構造と仕組みで決まります。
その構造づくりを体系化したのが、
採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から採用導線、教育・定着までを一貫支援し、
“採って終わり”から“育つ組織”へ。
御社の採用と成長をつなげる仕組みを、一緒に作りませんか?
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用は“人を増やすこと”ではなく、
“器を整えること”から始まります。
器の大きさ以上に、人は育たない。
でも器を広げれば、驚くほど人は育つ。
それが、建設業の採用成功の本質です。