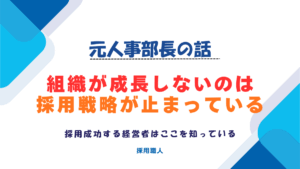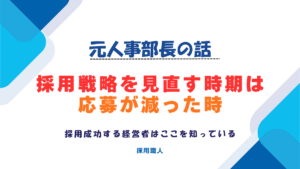採用と組織は車の両輪。“育つ組織”を作る採用設計
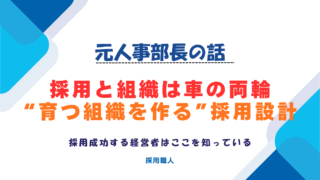
「採用したのに辞める」──その繰り返しに終止符を打てるか
「せっかく採ったのに、すぐ辞める」
「採用はできても、育たない」
そんな声を、毎月のように建設業の社長から聞きます。
でも実は──
採用がうまくいかないのではなく、組織が育つ構造ができていないだけなんです。
採用と組織は、車の両輪。
どちらか片方だけを回しても、前には進みません。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
現場で見た「人が定着しない会社」の共通点
私は元・建設会社の人事部長として、
200社以上の採用支援に関わってきました。
驚くことに、“人が辞める会社”には共通点があります。
- 採用は頑張っているが、育成の仕組みが存在しない
- 現場が「教える側」になっておらず、放任か過干渉
- 採用の目的が“人手補充”で止まっている
つまり、採用は「入口の設計」だけで終わり、
その先の“育つ構造”が存在しない。
例えるなら、立派な玄関を作っても、
中の部屋が未完成の家に人を招いているようなものです。
採用は成功したのに「誰も残らなかった」
ある地方の建設会社。社員数は25名、平均年齢45歳。
社長は「若手を採りたい」と毎年100万円以上の求人広告を出していました。
1年目、応募は増え、5人採用。
「ようやく若返りができた」と喜んでいたのも束の間──
1年後、残ったのはわずか1人。
理由を聞くと、こんな答えが返ってきました。
「誰に聞いていいかわからなかった」
「仕事を覚える前に怒られて終わった」
「会社の方針が見えなかった」
彼らは“合わなかった”のではない。
受け皿(組織構造)が存在しなかったのです。
採用と組織が分離している会社は「逆回転」する
多くの中小企業では、
採用と組織づくりが別々の部門で進んでいます。
- 採用:人事または広告会社
- 育成:現場のリーダー任せ
- 定着:誰も責任を持たない
この構図では、採用の努力が組織に伝わらない。
経営者は「採用が課題だ」と思い込むが、
本当は“採用と組織の接続点”が抜け落ちているだけ。
採用を変える前に、まず組織の循環を整えることが必要なのです。
採用と組織をつなぐ3つの接続ポイント
組織が育つ会社は、採用と組織の「接続設計」ができています。
ポイントはたった3つ。
① 方針の接続──経営戦略と採用戦略を一本化する
多くの会社では、「経営方針」と「採用方針」が別々に存在します。
しかし、経営方針が「施工班を増やす」であれば、
採用方針も「班を率いる人材を採る」に連動しなければ意味がない。
採用とは経営計画の一部。
経営が人を動かし、人が経営を支える構造を作る。
② 構造の接続──“育つ仕組み”を先に整える
採用を始める前に、「育成構造」を先に設計する。
- 誰が新人を教えるか
- どの期間で何を身につけるか
- どのタイミングで評価するか
これらを明確にした会社は、入社後の離職率が圧倒的に低い。
ある会社では「1年目は“基礎・報連相・安全”に絞る」と明文化しただけで、
半年の離職率が70%→10%に改善した。
採用は、“教育シナリオ”がないと回らない。
③ 評価の接続──採用成果を数字で見る
採用の最終成果は「人が育つこと」。
そのためには、採用をKPIで管理する必要がある。
| KPI | 目的 | 経営への効果 |
|---|---|---|
| 応募数 | 求人反応の把握 | 母集団形成の改善 |
| 面接率 | 応募対応スピードの確認 | 機会損失の防止 |
| 定着率 | マッチング・教育効果の測定 | 離職コストの削減 |
採用KPIは、“経営の健康診断”と同じ。
数字で見るからこそ、改善が進む。
なぜ「育たない組織」になってしまうのか
採用と組織が分離した会社には、3つの“歪み”が起きています。
- 採用スピード>教育スピード
→ 採っても育てられない。結果、現場が疲弊。 - 採用目的>育成目的
→ 「人を入れる」こと自体がゴールになっている。 - 採用担当>組織責任者
→ 採用は人事任せ、育成は現場任せ。誰も全体を見ていない。
採用を成功させるには、
この3つを“経営が一本化すること”が不可欠です。
実例:採用と組織を同時に整えて成功した会社
私が支援したある中小建設会社(社員22名)は、
当初、離職率が40%、採用単価が100万円を超えていました。
社長は「求人が悪い」と言っていましたが、
実際は“組織構造のズレ”が原因でした。
そこで取り組んだのは、採用を止めて組織を整えること。
実施内容
- 教育担当者を3名選定し、評価基準を共有
- 月1回の面談制度を導入
- 採用と育成を経営会議で一体管理
半年後の成果はこうです。
- 応募:10件 → 45件
- 採用単価:98万円 → 38万円
- 定着率:60% → 92%
- 売上:前年比150%
採用を「経営装置」として扱った瞬間、
会社全体のリズムが変わったのです。
“育つ組織”を作る採用設計法
ここからは、実際に経営者が取り組める実践ステップを紹介します。
ステップ①:「理想の組織像」を描く
まず、“採りたい人”よりも“育てたい組織”を考える。
5年後のチーム構成・リーダー層・役割バランスを可視化する。
例:
- 現場班を3班 → 5班に拡大
- 若手職長を3名育成
- 2年で中堅層の離職率を10%以下へ
このように、組織の未来図を前提に採用を設計する。
ステップ②:「採用×育成×評価」を一本化する
採用担当・教育担当・評価者を分けず、
1本のチームで運用する。
毎月の経営会議で「採用数・教育進捗・定着率」を並べて確認する。
数字を並べることで、組織が“採用の流れ”を理解できるようになる。
ステップ③:「採用データ」を経営数字に転換する
応募数や離職率などのデータを、経営KPIとして管理。
採用KPIは営業・原価管理と同じレベルの経営数字です。
- 採用単価を下げる=利益率の改善
- 定着率を上げる=生産性の安定
- 教育期間を短縮=稼働スピードの向上
採用を数字で語れるようになると、
会社全体が「人を経営する」感覚に変わります。
組織の“器”を整えると、採用は自然にうまくいく
人が育つ会社は、採用が上手だからではありません。
育てる構造があるから、採用もうまくいくのです。
採用を広告で増やすのではなく、
組織の構造で増やす。
- 役割を明確に
- 教育を仕組みに
- 評価を経営に
この3つを整えれば、応募数も定着率も必ず上がる。
「採用=組織の鏡」組織の成熟度をあげよう
採用活動を見れば、その会社の“組織の成熟度”が分かります。
- 採用が感覚的 → 組織も属人的
- 採用が数字で管理 → 組織も仕組みで動く
- 採用が理念と連動 → 組織も育つ文化になる
採用は経営の縮図です。
人が集まらないのではなく、構造が人を受け止められていないだけ。
まとめ:採用と組織は一体で設計するもの
- 採用と組織を分けて考えると、どちらもうまくいかない
- 採用は“入口”、組織は“土台”──両輪で動かすことで初めて前進する
- 組織の器を整えれば、採用は自然と回り出す
採用は、気合でも予算でもなく、構造設計で決まる。
その構造を体系化したのが、
採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から採用導線、教育・定着の仕組みまでを一気通貫で支援し、
“採る”から“育つ”へ。
御社の組織を、確実に成長させる実務設計を提供しています。
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用と組織は、決して別物ではありません。
「人を採る」ことは、「会社を育てる」こと。
両輪が噛み合ったとき、
初めて会社はまっすぐ前に進みます。