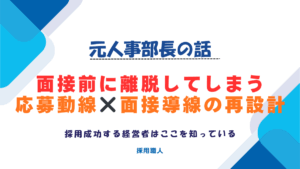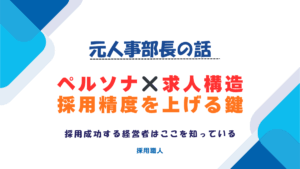採用の精度を決めるのは“求人の設計図”ペルソナと構造分析の重要性
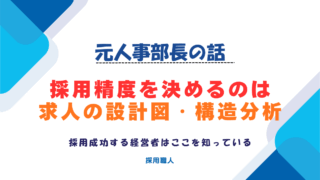
採用の「最初のボタン」を間違えると、何をしてもズレ続ける
「うちは“まじめで長く働ける人”がほしい」──。
面接でそう話す社長は多いのですが、実際に求人を見てみると、“誰に向けて書かれたのか”がわからない原稿ばかりです。
採用の成否を分けるのは、最初の「ペルソナ設計」。
どんな人を採りたいのか、何を求め、どんな生活をしているのかまで描けていない会社ほど、求人広告に頼るしかなくなるのです。
この記事では、
- なぜペルソナ設計がズレるのか
- 求人構造をどう分析すれば採用精度が上がるのか
- 実際に成功した建設会社の分析方法
を、元建設会社人事部長の立場から解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
求人広告の「数字」は嘘をつかない
全国の中小建設会社で、1求人あたりの応募数は平均3.2件/月(厚労省「一般職業紹介状況」2024年7月時点より)。
にもかかわらず、採用できる会社とそうでない会社の差は、求人内容の中身で生まれています。
採用できている会社ほど、求人原稿を「誰向けに設計しているか」が明確です。
逆に採れない会社ほど、「とりあえず出してみた」「前回の原稿を再利用」という状態。
言い換えれば、
求人構造=採用成果の設計図。
ペルソナが定まらないまま求人を出すのは、図面なしで家を建てるようなものです。
データが示す「ペルソナ不在の弊害」
ある調査(リクルートワークス研究所・2023)によると、
「採用活動で最も困難なことは?」という質問に対し、
中小企業の経営者の68%が「求める人物像の具体化」と回答しています。
ペルソナが定まっていないと、次のような悪循環に陥ります:
- 求人内容が曖昧 → 応募者層がバラつく
- 面接基準がズレる → “いい人”を逃す
- 現場配属後にミスマッチ → 離職率が上がる
人事部長時代、実際に離職率42%→18%まで改善した際も、最初に着手したのは「ペルソナの再設計」でした。
「採用ターゲット」を誤解していないか
多くの社長が「若手がほしい」と言います。
しかし、私が現場ヒアリングをすると、本音はこうです。
「できれば即戦力で、資格もあって、でもあんまり偉そうじゃない人がいい」
──これ、誰ですか?
結局、“理想の人物像”が幻想の合成写真になっている会社が多いのです。
ペルソナ設計とは、単なる理想像ではなく、
「今の組織に合う人物像」をデータで導き出す作業。
たとえば、
- 定着者の平均年齢
- 入社理由の傾向
- 離職者の共通点
- 現場リーダーの性格タイプ
これらを分析すれば、「次に採るべき人の特徴」が見えてきます。
改善策①:定着者データから“採るべき人”を見極める
まずやるべきは、「辞めなかった人」を徹底分析することです。
▼分析の視点
| 分析項目 | 内容例 |
|---|---|
| 入社経路 | どの媒体・紹介から来たか |
| 年齢層 | 20代前半〜30代など |
| 居住エリア | 通勤距離・通勤手段 |
| 性格傾向 | 慎重/外向的/協調型など |
| 定着理由 | 給与・人間関係・現場の雰囲気など |
こうして「定着者の共通点」を出すと、驚くほどシンプルな傾向が見えてきます。
たとえば、通勤時間30分以内・未経験・チーム型志向が定着率80%というケース。
これをもとに、求人文のターゲットを“その人に響く言葉”で設計するのです。
改善策②:求人構造を「3層」で分解する
ペルソナを決めたら、次は求人構造の整理です。
求人原稿は、以下の3層構造でできています:
- 表層(見出し・キャッチコピー):興味を引く入口
- 中層(仕事内容・待遇):応募判断の材料
- 深層(価値・文化):共感・定着につながる要素
このうち“深層”が弱い会社ほど、応募数はあるのに採用につながりません。
なぜなら、応募者は「働く理由」を探しているからです。
改善策③:ペルソナを社内で「共有・更新」する
ペルソナ設計は、一度作って終わりではありません。
採用を成功させている会社は、半年ごとに見直しをしています。
たとえば、現場リーダーと一緒に「最近の新人でうまくいった人・合わなかった人」を分析し、
そこからペルソナを更新。
こうすることで、求人が“現場にフィットする言葉”に変わっていきます。
実際、ある建設会社ではこの仕組みを導入してから、採用後3ヶ月以内離職ゼロを達成しました。
関連テーマはこちら →
“採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
ペルソナ設計が「採用の軸」をつくる
ペルソナが明確になると、採用活動全体が一本の線でつながります。
- 求人内容が具体的になる
- 面接で聞くべき質問が定まる
- 教育・評価の方針が一致する
つまり、「採用の軸」ができるのです。
結果、応募単価は下がり、採用単価も40万円以下に安定。
「採用職人の採用支援サービス」(https://recruit-worker.com/)では、
この“ペルソナ設計〜導線構築”をワンセットで支援しています。
現場が動きやすく、経営が迷わない採用の仕組みを一緒に整えていきましょう。
実績と信頼:数字で見る再現性
私の前職では、年間200万円の広告費で応募10人以下・採用0〜3人の状態から、
ペルソナ設計と求人構造の再構築によって、
応募200人/採用20人/応募単価3万円以下を実現。
しかも、
SNSなし・ハローワークなし。
「求人広告会社任せにしない仕組み」で成果を出しました。
note紹介:ペルソナ設計を“仕組み化”するために
ペルソナを明確にするには、言語化のテンプレートと分析フレームが欠かせません。
それらを体系化したnoteはこちらです:
価格は¥4,980〜¥20,000。
1回の採用単価(平均150万円)のわずか数%の投資で、再現性ある採用設計を手にできます。
まとめ:「誰を採りたいか」が、すべての起点
採用で成果を出す会社は、「何人採るか」よりも「誰を採るか」にこだわります。
そしてその答えは、求人構造の中に隠れています。
ペルソナ設計は、採用の“感覚”を“再現可能な仕組み”に変えるための第一歩。
採用の成否は、最初の1枚の求人で決まります。