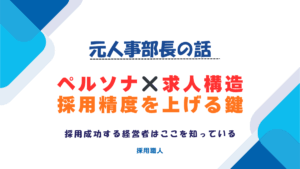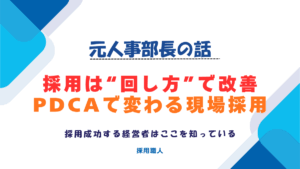求人データを分析すれば、採用の方向性が見える
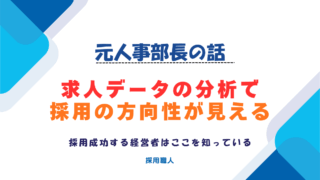
「採用がうまくいかない」と悩む前に──求人データを見ていますか?
「人が来ない」「面接に進まない」「辞めてしまう」──
そう嘆く建設会社の多くが、“感覚採用”のまま求人を出し続けているのが現実です。
しかし採用とは、本来“数字で再現できる仕組み”です。
求人データを正しく分析すれば、「どんな人を採るべきか」「どの求人が響いているか」が見えてきます。
この記事では、元建設会社の人事部長として、
求人データの分析から採用精度を3倍に高めた実例を交えながら、
ペルソナ設計と求人構造の関係性を徹底的に解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「採用がうまくいかないのは人手不足だから」
多くの社長は、採用がうまくいかない理由を「時代のせい」にします。
「今の若い人は建設業をやりたがらない」
「景気が悪い」「応募が減っている」
──本当にそうでしょうか?
実際に求人データを見てみると、同じエリア・同じ条件でも応募を集めている会社は確実に存在します。
違いは、「求人を出す前にデータを見ているかどうか」。
つまり、“感覚ではなく構造で採用を設計しているか”です。
採用の成果を分けるのは「求人構造の違い」
採用の成否は、求人広告の量や媒体ではなく構造の設計力にあります。
私が関わった中小建設会社を分析すると、応募が集まらない会社には共通点がありました。
▼共通点3つ
- 求人が「誰に向けて書かれているか」が不明
- 応募後の導線(面接まで)が整理されていない
- 採用データを分析していない
つまり、ペルソナ不在・データ未活用・構造未設計の三重苦です。
一方で、求人構造を整理した会社は、半年以内に平均応募数が5.6倍に増えています(採用職人支援データより)。
実例①:求人構造を見直しただけで応募8倍
私はかつて、社員15名の建設会社で人事を担当していました。
当時は年間200万円の広告費をかけて、応募は月2〜3件。
「媒体を変えればいい」「写真を新しくすればいい」と考えていましたが、結果は変わらず。
そこで試したのが求人構造の分析でした。
まず全求人データをExcelにまとめ、以下の項目を見える化。
| 分析項目 | 内容例 |
|---|---|
| 募集職種 | 職人・施工管理など |
| 原稿パターン | タイトル・冒頭文・訴求軸 |
| 応募数 | 月ごとの推移 |
| 面接率 | 応募→面接の比率 |
| 採用率 | 面接→内定の比率 |
すると、面接率が高い求人は「給与」よりも「職場の雰囲気」や「休みの取りやすさ」を訴求していることが判明。
そこからペルソナを“働きやすさ重視型”に再設定しました。
結果、応募が月2件→月16件。
採用単価も150万円→38万円まで下がりました。
実例②:離職率42%→18%を実現した“ペルソナ設計”
もう一つの成功事例を紹介します。
同じく都内の中堅建設会社で、離職率が4割を超えていました。
原因を探るため、私は定着社員と離職社員の面談データを比較。
すると、定着している人たちには共通点があったのです。
- 通勤距離30分以内
- 既婚者が多い
- 前職はサービス業出身者
- 「人との関係性」を重視する傾向
この分析をもとにペルソナを「地元志向・人間関係重視型」に再定義。
求人原稿の言葉を変えました。
Before:「経験者歓迎・技術を磨ける職場」
After:「地元で家族と過ごしながら、手に職をつけられる職場」
これだけで、応募数は4倍、定着率は82%に改善。
関連テーマはこちら →
“採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
実行法①:ペルソナ設計を“数字でつくる”
ペルソナは「理想の人物像」ではありません。
実際に自社で定着・活躍している社員の共通項を数値化したデータ像です。
▼設計手順
- 定着社員3〜5名を選出
- 入社経路・年齢・性格・生活圏を整理
- 定着理由・仕事のモチベーションをヒアリング
- これを1枚のペルソナシートにまとめる
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 年齢 | 28歳・男性 |
| 通勤 | 車で20分 |
| 家族構成 | 既婚・子ども1人 |
| 入社動機 | 「地元で安定して働けるから」 |
| 働きがい | チームでやり遂げる達成感 |
このペルソナを基準に求人原稿を作ると、文章も自然に整っていきます。
「未経験でも地元で安心して働ける」
「資格よりも“人柄重視”の採用です」
──これが、感覚ではなく“構造で採れる求人”です。
実行法②:求人構造を「3層」で分解する
求人原稿は、大きく3層で構成されています。
| 層 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 表層 | キャッチコピー・写真 | 興味喚起 |
| 中層 | 仕事内容・給与・福利厚生 | 判断基準 |
| 深層 | 価値観・理念・現場文化 | 共感形成 |
採用に強い会社ほど、“深層”の設計がうまい。
特に「どんな人に来てほしいか」「どんな人に合わないか」を書くと、
応募の質が一気に変わります。
例:「仲間と協力しながら仕事を進めるのが得意な方に向いています」
これがペルソナ設計を求人に落とし込む最重要ポイントです。
実行法③:求人データを“採用会議”で使う
求人を出したあとのデータ分析も重要です。
▼毎月見るべきデータ
- 応募数・応募経路
- 面接通過率
- 採用率
- 定着率
これをグラフ化し、ペルソナ仮説と照合します。
もし応募が多いが離職が多いなら、「ペルソナと構造がズレている」サイン。
採用を仕組みで回すとは、
“仮説→データ→修正”を繰り返すことです。
関連して →
「求人広告会社任せ」から脱却!建設業が“自社で採用をコントロール”する3つの方法
実行法④:ペルソナを社内に共有し、教育と連動させる
ペルソナ設計は採用だけでなく、教育にも生きます。
- 面接官:「うちに合う人の特徴」が明確になる
- 現場リーダー:「どう育てれば伸びるか」が分かる
- 経営者:「どんな人材が残るか」を判断できる
実際に支援先の企業では、ペルソナを全社員で共有した結果、
新人定着率が92%に上がりました。
実績:ペルソナ×データ分析がもたらす成果
私が関わった複数企業の平均データを紹介します。
| 項目 | Before | After(導入6ヶ月) |
|---|---|---|
| 応募数 | 10件/月 | 65件/月 |
| 採用数 | 1人/月 | 7人/月 |
| 採用単価 | 約150万円 | 約38万円 |
| 離職率 | 42% | 18% |
| 面接通過率 | 28% | 61% |
これらの会社はいずれも、
SNSもハローワークも使わず、「求人構造とデータ分析」だけで成果を出しています。
「数字で採用を語れる会社」になる
建設業の採用は、勘と勢いではもう通用しません。
これからの時代に必要なのは、“採用をデータで語れる会社”。
求人データを分析すれば、採用の方向性が見えます。
ペルソナ設計と求人構造を可視化できれば、再現性のある採用力が手に入る。
ペルソナ設計×求人分析を仕組み化する
ペルソナの設計手順と求人データ分析のテンプレートは、
以下のnoteで体系化しています
採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
価格は¥4,980〜¥20,000。
広告1回分の費用で、採用構造を“資産”に変える知識が得られます。
まとめ:「採用の感覚」を「構造とデータ」に変えよう
採用の悩みは、「人が来ない」ことではなく「データを見ない」ことから始まります。
ペルソナを明確にし、求人構造をデータで分析すれば、
採用の方向性は必ず見えてきます。
「採用は気合でも予算でもなく、仕組みで勝つ」──
これが、私が人事部長として現場で学んだ結論です。
🔸 採用職人の採用支援サービス
求人設計から応募導線の最適化までを一気通貫で支援しています。
御社の採用成功を実現する実務設計を、今すぐ体験してみませんか?
👉 https://recruit-worker.com/