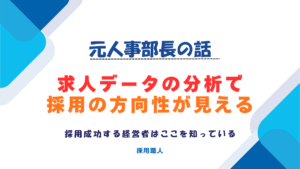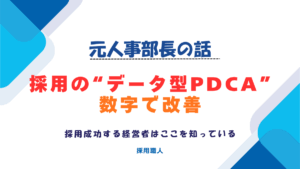採用は「やること」ではなく「回すこと」PDCAで変わる現場採用
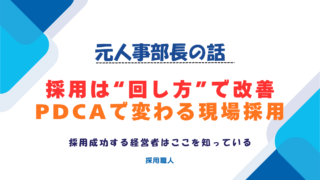
採用活動を“やりっぱなし”にしていませんか?
「採用は回してこそ成果が出る」。
これは、元人事部長として現場を何十社も見てきて確信したことです。
求人を出して、応募を待ち、面接して終わり──。
こうした“やりっぱなし採用”では、翌年も同じ課題を繰り返します。
たとえば、ある建設会社では年間200万円の広告費をかけても応募10人以下。
原因を分析してみると、「何がうまくいったのか」「どこが悪かったのか」を
一度も振り返っていなかったのです。
採用を“単発のイベント”から“仕組みとして回す”ためには、
PDCAサイクルの考え方が不可欠です。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
採用が「回らない」原因は“感覚運用”にある
多くの会社では「今年も同じように求人を出してみよう」と、前年の再掲を繰り返します。
これが“採用が回らない会社”の典型です。
なぜか?
それは「データを残していない」から。
たとえば、
- どの職種から応募が来たのか
- 面接通過率はどのくらいか
- 一人採用するのに何件応募が必要か
このような指標(KPI)を記録していないと、
改善の方向性が見えません。
総務省の労働力調査(※参考:https://www.stat.go.jp/data/roudou/)によると、
建設業の有効求人倍率は2.57倍(2024年平均)。
つまり、「採用が難しい時代」ではなく「比較される時代」です。
競合に勝つためには、データで採用を管理し、改善点を見抜く力が求められます。
【実例】「数字で回す」だけで応募が3倍になった話
私が人事部長として関わったある建設会社では、
最初の1年目は「応募が10件、採用ゼロ」という状態でした。
しかし、
“感覚”ではなく“データ”で採用を振り返る仕組みを導入。
毎月の指標をこう定義しました:
- 応募数(応募経路別)
- 書類通過率
- 面接通過率
- 内定承諾率
数字を出してみると、
驚くほどの「ボトルネック」が見えたのです。
たとえば面接通過率がわずか18%。
つまり、面接内容そのものが採用を止めていた。
そこで、質問項目を再設計し、面接官研修を実施。
翌月には通過率が40%に上昇し、応募数も約3倍になりました。
採用PDCAの基本4ステップ
① Plan(計画)──「採用の目的」を明確にする
まず決めるべきは、「誰を」「何のために」採るのか。
これが曖昧なままだと、どんなに原稿を改善してもズレ続けます。
【例】
「経験者を採りたい」ではなく、
「入社3ヶ月で現場を任せられる人材を採る」など、成果を具体化します。
② Do(実行)── 計画に基づき、施策を打つ
求人原稿・面接・導線などの施策を実行します。
ポイントは、「施策ごとに数字を紐づける」こと。
例:
- 原稿改善 → 応募率
- 面接改善 → 通過率
- フォロー改善 → 内定承諾率
これにより、「どの施策が効果を生んでいるか」を可視化できます。
③ Check(評価)── データで“仮説の正否”を検証する
ここでの注意点は、「感想」ではなく「数値」で見ること。
「今回うまくいった気がする」はNG。
「応募率+15%」「通過率−10%」など、明確な数値を基準にします。
毎月のKPIレポートを簡易的に作るだけでも、
採用精度は格段に上がります。
④ Act(改善)── 成果を仕組みに変える
最後にやるべきは「うまくいったことを再現する仕組み化」。
たとえば、面接官マニュアルや、求人原稿の成功パターンをテンプレート化する。
この“型化”が、次の採用を早く・安く・安定的に回すカギです。
データは「批判」ではなく「改善の材料」
多くの現場でPDCAが止まる理由は、
「数字を出すと責任追及になる」と誤解されているからです。
でも本来、数字は“人を責めるため”ではなく、
“現場を改善するため”のもの。
私の人事時代も、最初は職長から
「数字で管理されるのはイヤだ」と反発がありました。
けれど、数ヶ月後にはこう言ってくれたのです。
「数字で見えると、どこを頑張ればいいか分かるな」
数字は冷たいものではなく、現場を守る道具なんです。
採用PDCAを仕組み化するには
PDCAを継続的にまわすには、
「担当者のスキル」に頼らない仕組みづくりが必要です。
たとえば:
- 月次で採用指標を自動集計するExcelシート
- 原稿・面接・定着率を一元管理する管理表
- 改善会議を定期化する運用ルール
これらを整えることで、採用は“再現可能な経営機能”になります。
成果を出す会社の「採用レポート」には共通点がある
私が支援した企業では、
成果が出る会社ほど「採用レポート」を形式化しています。
レポート項目例:
- 月別応募数(経路別)
- 面接通過率・内定率
- 採用単価(応募数÷採用数)
- 退職率(3ヶ月・6ヶ月・1年)
これを毎月10分で確認するだけでも、
次の手が見えてきます。
関連:
“採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
採用を「仕組み」で回すために
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
求人設計から導線改善、PDCA設計までを一気通貫で支援しています。
単発の施策ではなく、“再現性のある採用”を作ることに特化しています。
御社の採用をデータで強くし、仕組みで回していく設計を体験してみませんか?
まとめ:採用は気合でも予算でもなく「仕組み」で回すもの
採用は“やること”ではなく、“回すこと”。
一度の成功より、「成功を再現する仕組み」が価値を持ちます。
PDCAをまわせば、採用は「運」ではなく「管理」になる。
そしてそれは、中小建設業こそが取り入れるべき武器です。
もし、どこから手をつければいいかわからないなら、
まずは自社の採用データを一度“見える化”してみてください。
そこからすべてが始まります。