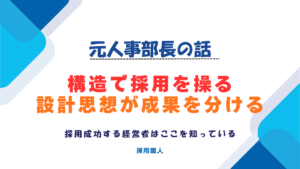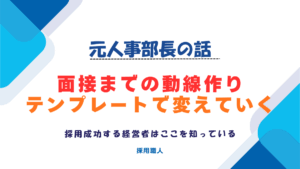同じテンプレートなのに結果が違う理由。“構造を理解した会社”が採用に強い
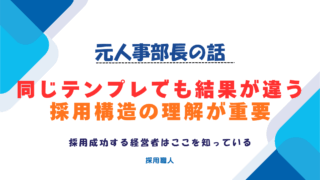
「テンプレートを使えば採用できる」その考え方が落とし穴です
最近、「求人テンプレートを使ったけど効果がなかった」という声をよく聞きます。
でも、実はテンプレート自体に欠陥はないんです。
問題は「どう使ったか」。
同じテンプレートを使っても、
A社は応募200人、B社は応募ゼロ。
この差を生むのは、“構造理解と現場目線”の有無です。
この記事では、建設業の現場で実際に採用が安定した会社の事例を交えながら、
「テンプレート任せでは採れない理由」と「成果につなげる使い方」をお伝えします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
【本文構成】
「テンプレートを入れれば採用できる」
「テンプレートさえあれば求人は書ける」。
この考えが一番危険です。
テンプレートは“道具”であって、“魔法”ではありません。
たとえば、同じ図面でも、職人が変われば仕上がりが全く違うように、
求人原稿も“使い手の理解度”で結果が大きく変わります。
多くの会社がやってしまうのは、テンプレートの枠だけを埋めて終わり。
中身が「会社の現場を反映していない」状態で出しても、求職者には伝わりません。
採用テンプレートの本質は「思考の順序」
テンプレートの本当の目的は、「書きやすくする」ではなく
“採用の考え方を整理すること”にあります。
順番に言えば──
- どんな人に来てほしいかを明確にする
- その人が気になる情報を順に並べる
- 会社の言葉で安心と信頼を伝える
これができて初めてテンプレートは機能します。
つまり、「型」ではなく「順序」が採用を変える。
求職者が求人を読むときの心理導線を理解していないと、
どんなテンプレートを使っても「他社と同じ文」にしか見えません。
同じテンプレートで結果が分かれた2社
事例①:A社「現場写真+会話文」で応募3倍
A社は型どおりのテンプレートに“現場写真”と“社員コメント”を追加。
「休憩中は職人同士で雑談して笑い声が絶えない」
この一文だけで応募率が3倍に。
理由は、求職者が「雰囲気がわかる」と感じたから。
A社は“テンプレートの空欄を埋める”のではなく、
会社の温度を注入したのです。
事例②:B社「条件」しか書かず応募ゼロ
同じテンプレートを使っても、B社は条件面ばかりを記載。
「給与30万円〜/社保完備/賞与あり」
どこにでもある文言で、結果は応募ゼロ。
「テンプレートを使ったのに反応がない」と嘆く前に、
現場を見せる努力をしていたか?が分岐点です。
関連して → 採用で“写真”が9割を決める──応募率を2.8倍にした見せ方
実行法:テンプレートを“活かす”ための3ステップ
テンプレートを成果に変えるには、次の3ステップが必要です。
Step1:現場取材で「1日の流れ」を聞く
人事が現場に足を運び、
「どんな人が教える?」「どんな時間が楽しい?」を聞く。
これが文章の“熱”を生みます。
Step2:求職者目線で「最初の3行」を設計
テンプレート導入文は“3秒で共感”が命。
「未経験でも続けられる環境を探している方へ」
のように、ターゲットの悩みを代弁する。
Step3:面接前提の「応募導線」を設計
応募したくなるだけでなく、面接まで来る流れを設計。
応募フォームやレスポンス速度もテンプレートの一部です。
まとめ:テンプレートを“使う会社”が採用を制す
テンプレートは便利ですが、使い方を誤ると「量産型の求人」になる。
反対に、構造を理解して使えば、採用の設計図になります。
採用が強い会社ほど、
「テンプレートを使う前に、何を伝えるか」を決めています。
採用を変えるのは“ツール”ではなく“使い手の理解”。
テンプレートは、その理解を形にするための道具です。
建設業の採用は、気合でもセンスでもなく、構造で決まる。
採用職人の採用支援サービス紹介
現場採用のノウハウを体系化した
『採用職人の採用支援サービス』では、
求人テンプレート導入から応募導線・面接設計までを一貫して支援しています。
御社の採用を“属人戦”から“仕組み戦”に変える実務設計を体験してください。
内部リンク挿入