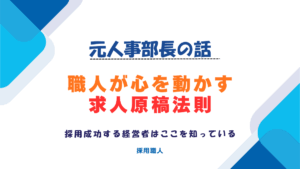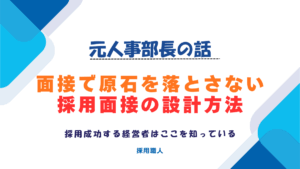面接が得意でなくても大丈夫。職長が“いい人材”を見抜ける3つの質問
面接が苦手な職人でも“いい人材”を見抜ける方法
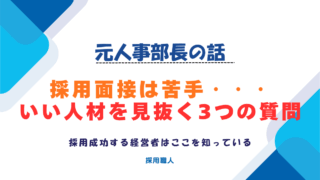
「感じがいい」ではなく「現場で生きる人」を見抜く面接術
「面接で話してみたら良さそうだったのに、入ってみたら全然違った…」
建設業の現場で、こんな経験をしたことはありませんか?
僕自身、人事部長として現場と一緒に面接を重ねる中で痛感しました。
——“面接は人を見る場ではなく、現場を写す場”だと。
この記事では、面接が苦手な職人や職長でも「本当に現場で活躍できる人材」を見抜けるようになる方法を、実例とステップで解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「人を見る力」は“質問力”でつくられる
面接が苦手な職人の多くは、「何を聞けばいいか分からない」と口を揃えます。
でも実は、“質問が下手”なのではなく、“聞く目的”が曖昧なんです。
たとえば、こんな会話が現場面接でよくあります。
「今までどんな仕事してた?」
「解体とか配管とか、ちょっとだけ」
「そうなんだ。体力には自信ある?」
「まぁ、そこそこです」
——ここで終わってしまう。
でも本当に知りたいのは、「どんな環境で、どんな人たちと、どう働いてきたか」です。
質問を変えるだけで、見える情報がまったく違います。
「配管やってたとき、どんなチームでした?一緒に動いてたのは何人くらい?」
「リーダーと3人で回してました」
「その中で、自分はどんな役割でした?」
「図面見て、材料運んで、段取り少しやってました」
——この答えで、“実務の理解度”と“責任感”のレベルが一気に見えてきます。
つまり、いい面接は「聞く内容」ではなく「掘り下げ方」で決まるんです。
面接で見るべきは「スキル」より「現場の適合性」
建設業では「経験者だから安心」「資格があるから即戦力」という判断がまだ多い。
でも、採用の現場で本当に見るべきは“人の使い方の癖”です。
私が過去に担当した会社で、こんな事例がありました。
ある会社では、経験10年以上の職人を採用しました。
履歴書も完璧。面接でも受け答えがしっかりしていて、「これは当たりだ」と思ったんです。
ところが入社後、半年で退職。
理由は「うちのやり方に合わなかった」。
逆に、未経験で入った20代の若手は、今では班長としてチームを引っ張っています。
違いは“仕事の考え方”。
スキルではなく、「現場の価値観に合うかどうか」で決まるんです。
面接で見るべきは、経験ではなく「相性」。
その見極めを支えるのが、質問設計と評価軸です。
現場面接で使える“3つの質問テンプレート”
面接が苦手な職人でも、次の3つの質問を押さえれば十分です。
①「どんな現場が一番印象に残ってますか?」
→ 人の“働き方の価値観”が出ます。
たとえば「大きい現場より少人数の方が好き」と答える人は、チーム型の現場に向いています。
②「これまでの職場で、うまくいった時・うまくいかなかった時は?」
→ 成功・失敗の話から、“責任感”と“人間関係のクセ”が見えます。
他人のせいにする人は危険。
逆に「自分の段取りが悪くて…」と話す人は成長タイプです。
③「どんな時に“この仕事やっててよかった”と思いました?」
→ “仕事観”と“やりがいのポイント”を知る質問。
モチベーションの源泉が分かると、入社後の定着率にもつながります。
こうした質問を使うことで、現場職長でも自然に「人となり」を引き出せます。
(関連して詳しく解説しています → 面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計)
職長が評価すべき“4つの視点”
面接後の評価は、「なんとなく良かった」「印象がいい」ではなく、以下の4項目で整理します。
| 評価項目 | 見るポイント | 例 |
|---|---|---|
| ①責任感 | 指示待ちでなく、自分で考えようとするか | 失敗談に“自分の改善”を話す人 |
| ②協調性 | 現場でのチーム適応力 | 「前職の人間関係」を冷静に話す人 |
| ③成長意欲 | 技術を覚えたい姿勢があるか | 「資格より現場で覚えたい」などの発言 |
| ④価値観の一致 | 会社の働き方に共感できるか | 面接で「長く働けそう」と言うかどうか |
これを職長と共有し、「5段階評価」でつけるだけでも採用精度が上がります。
面接の仕組みを変えただけで“離職率が下がる”
ある土木会社では、職長面接を導入する際に僕が関わりました。
最初は「そんなの無理だ」「聞くことない」と言っていた職長たちも、質問表を使ううちに変わりました。
3ヶ月後には、
「あの人、最初は地味だったけど、今めっちゃ伸びてる」
「話してた通り、まじめで責任感あるよな」
と、自分たちで採用した人を“育てる意識”が芽生えたんです。
結果、1年間で離職率が大幅に下がりました。応募は増えていないのに、“辞めない現場”ができました。
採用は「見る力」と「選んだ後の関わり方」がセットです。
(このテーマをさらに掘り下げた記事はこちら → 新人が定着しない原因は?建設業でよくある「定着の課題」と解決のヒント)
面接が「選ぶ場」から「関係をつくる場」へ
面接は“見抜く”だけの場ではありません。
同時に「会社を見せる場」でもある。
だからこそ、職長や現場が関わる面接は強いんです。
求職者は、話した職長の姿を見て「この人たちと働きたい」と決めます。
建設業の採用で大事なのは、“スキルより空気感”。
現場の温度が伝わる面接こそが、会社の魅力をつくります。
現場が採用に関わる会社ほど、人は定着する。
面接は、その第一歩なんです。
仕組みで支える「職長面接の標準化」
ここまで読んで「うちでもやりたいけど難しそう」と感じた方へ。
職長面接の導入は、実は仕組み化すれば簡単です。
必要なのは3つのツールだけ。
1️⃣ 面接質問リスト
2️⃣ 評価シート(4項目×5段階)
3️⃣ 面接後のフィードバックミーティング
これをテンプレート化しておくだけで、現場の誰でも同じ基準で判断できます。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、この仕組みを1社1社に合わせて構築しています。
採用は“気合”ではなく“仕組み”で決まる
「人を見る目がない」と嘆く前に、「見る仕組み」をつくる。
それが、建設業における採用の本質です。
面接のやり方を変えるだけで、離職率は下がり、採用の質は安定します。
そして何より、「自分たちで人を選べる会社」になる。
もし、現場が主体の採用体制をつくりたいなら、
こちらのnoteで詳しく解説しています。
👉 面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
👉 “採用の失敗”を減らすためのチェックリスト
採用職人の採用支援サービスでは、求人設計から面接設計までを一貫して支援しています。
御社の採用が“現場主導で回る仕組み”に変わる、その第一歩を一緒に設計しましょう。