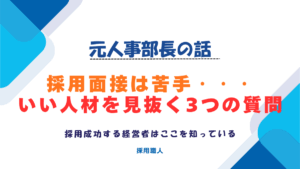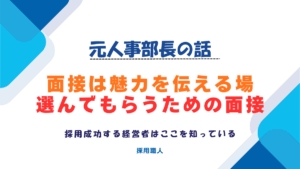面接で“伸びる人”を見抜けていますか?建設業が見落とす「原石人材」の特徴
面接で落としてはいけない“原石人材”の見抜き方
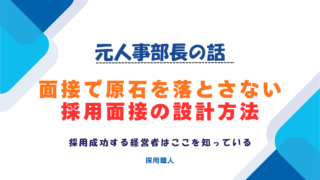
「経験がないから不安」──その判断が、未来の主力を逃しているかもしれない
「未経験だからやめておこうか」
「現場経験が浅いから厳しいかもな」
面接の現場で、そうつぶやく職長や社長を何度も見てきました。
でも、その“判断”が、未来の主力を逃していることに気づいている会社は少ない。
建設業の採用現場には、“原石人材”が埋もれています。
彼らはまだ磨かれていないだけ。
ただし、見抜ける会社と見抜けない会社の差は“質問設計”と“評価軸”にあります。
今日は、人事部長として200人以上の面接に同席してきた僕が、
「この人、最初は不安だったけど、今はエースになってる」という事例をもとに、
“原石人材”を見抜くための面接技術をお伝えします。
“経験”よりも“吸収力”を見よ
現場で伸びる人の共通点は「柔軟さ」にある
ある建設会社で、20代未経験の青年を採用したときのこと。
履歴書には「飲食・工場・短期バイト」と職歴がバラバラ。
普通なら“続かないタイプ”と判断して不採用にしていたでしょう。
でも、面接で話してみると、彼の口から出た言葉に違和感があった。
「前の職場では、先輩がやりやすいように掃除の順番変えたら、喜ばれたんです」
たった一言でしたが、そこに“気づき力”と“改善意識”が見えた。
この会社ではその後、彼が2年で班長に。
学歴も経験も関係なかった。
人が伸びるかどうかは、“変化を受け止める柔軟さ”で決まる。
面接で「伸びしろ」を判断する3つのポイント
原石人材を見抜くために、職長や面接担当が見るべきは次の3点です。
① 反応のスピード
質問した瞬間に、表情や反応が返ってくる人は“吸収型”。
「考えながら話す」タイプよりも、「まず聞いて動く」タイプが現場では伸びやすい。
② 例え話ができるか
自分の体験を“他の事例”に置き換えて話せる人は、思考の柔軟性が高い。
「前職ではこうでしたが、こっちはこうなんですね」と言える人は応用力がある証拠。
③ 素直さと自己客観性
「前の職場では怒られることも多くて」と言える人は、自己分析ができている。
反省できる人は伸びる。言い訳をする人は変わらない。
この3つを見極めるだけで、“経験ゼロ”でも伸びる人材を逃さなくなります。
原石人材は“質問の角度”で浮かび上がる
「何を聞くか」ではなく「どう掘るか」
原石人材は、面接の定型質問では見えません。
たとえば、こう聞いても何も分からない。
「前職ではどんな仕事してました?」
「倉庫で仕分けしてました」
ここで終わると、ただの“職歴確認”です。
でも、こう聞き直してみましょう。
「仕分けの時、どうやって早く終わらせてた?」
「最初は遅かったけど、台車の並べ方変えたら早くなりました」
——この瞬間、「この人、工夫できるな」と分かる。
面接とは、“事実の確認”ではなく、“思考の発掘”です。
【参考記事】面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計
落としかけた“原石”がエースに育った話
ある中堅建設会社での話です。
当時、面接に来たのは30代前半の男性。
前職はコンビニ勤務、資格なし。
社長は「うーん、厳しいかな」と渋い顔。
でも現場の職長が一言。
「この人、話してて“人の立場で考える”って感覚があるよ」
その直感を信じて採用。結果、2年で主任職に。
いまでは後輩育成まで任される存在です。
人は“スキル”ではなく“意識”で化ける。
面接でそれを見抜ける会社は、採用後の定着率も高い。
(関連: 「若者がすぐ辞める」のではなく「辞めやすくしている」のは会社側だ)
原石人材を見抜く“逆質問”テクニック
採用担当や職長側からだけでなく、応募者の“質問力”にも注目しましょう。
「何か質問ありますか?」のときに、こう返す人は要チェックです。
「入社後はどんなことから教えてもらえますか?」
「チームで動くとき、どんな雰囲気ですか?」
——この2つは、“学びへの意欲”と“組織適応力”のサイン。
逆に、「休みは?」「残業は?」だけの質問が続く場合、価値観が合わない可能性があります。
質問内容には、思考の成熟度が出ます。
面接は“会話のキャッチボール”であり、質問が深い人ほど伸びる人材です。
面接評価を“スキル表”から“成長予測表”へ
建設業の多くは、面接評価を「資格・経験・年数」で判断しがち。
でも、原石人材を採る会社は“未来の伸びしろ”で見ています。
おすすめは、次の4項目を5段階で評価する方法です。
| 評価項目 | 内容 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 吸収力 | 新しいことへの順応性 | 話の理解スピード、反応 |
| 素直さ | 指摘を受け入れる姿勢 | 自己分析・反省の有無 |
| 改善意識 | 現状を変えようとする思考 | 失敗談の中の“工夫” |
| 対人適応 | チームワークの柔軟性 | 他人の立場に立てる発言 |
評価シートにこれを加えるだけで、判断がブレなくなります。
そして「未経験だけど、伸びる」と確信できる採用が増える。
採用で最も重要なのは「見る力」ではなく「見ようとする姿勢」
面接で“いい人”を逃す会社の共通点は、「見ようとしていない」ことです。
履歴書で落とす、資格で切る、第一印象で決める。
でも、人の本質はその裏に隠れています。
私が見てきた成功企業は、どこもこう言います。
「最初は何もできなかったけど、今は頼もしいよ」
それは偶然ではなく、“伸びる人を見る目”を磨いた結果です。
“現場が採用に関わる”と原石を逃さなくなる
職長や現場リーダーが面接に同席すると、見え方が変わります。
人事や経営者が見落とす「現場適応の感覚」を見抜けるからです。
たとえば、ある電気工事会社では、現場のリーダーが最終面接を担当。
導入半年で、採用後の離職が3分の1に。
現場採用の本質は、「一緒に働く人が選ぶ」こと。
これができる会社は、採用のブレがなくなり、職場の雰囲気も安定します。
この仕組みづくりの具体法は、こちらの記事で詳しく解説しています →
現場が採用に関わる会社ほど“人が集まる”
採用職人の支援サービスで“見抜く力”を仕組みに変える
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
「原石人材を見抜く面接設計」を導入する企業を増やしています。
質問設計・評価基準・職長面接のテンプレートまで、
実際の現場で使える形に落とし込むのが特徴です。
現場で「面接って苦手なんだよな」と感じる人でも、
スクリプトを使えば自然に“人を見る質問”ができます。
まとめ:人を見る力は、経験ではなく仕組みで育つ
“原石人材”を採れる会社は、見る目がある会社ではありません。
「見ようとする構造」を持っている会社です。
面接は才能ではなく技術。
質問を磨き、評価を整えれば、誰でも“伸びる人”を見抜けるようになる。
そして、その小さな改善が、会社の未来を左右します。
採用は、経験を買うものではなく、可能性に投資する行為だ。
未来のエースを逃さない面接設計を、今日から始めてみませんか?