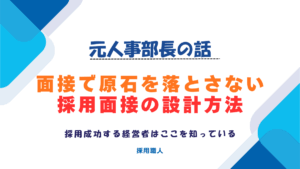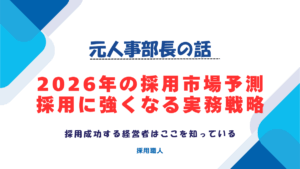面接は“聞く場”ではなく“伝える場”建設業が採用を逃さないための会話術
面接で好印象を与える会社は「話す量」が違う
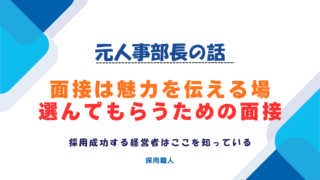
面接=応募者が話す場だと思っていませんか?
「面接では応募者にたくさん話してもらおう」
──これ、ほとんどの面接マニュアルに書いてある“常識”です。
けれど建設業の採用では、この“常識”が逆効果になることが多い。
実際、「面接で良い印象を持った会社ほど話してくれた」という応募者の声が圧倒的に多いんです。
なぜか?
それは、“面接=選考”ではなく、“面接=信頼形成”だから。
面接は「話す」より「伝える」。
聞くよりも、「開く」時間に変える。
この記事では、建設業の面接現場で何百人と会ってきた経験から、
“話す量の違い”が採用成功を左右する理由を解き明かします。
「よく聞く面接」と「よく伝える面接」の違い
まず、典型的な“聞く面接”を想像してみましょう。
面接官「これまでどんな仕事してきた?」
応募者「配管工事を3年ほど…」
面接官「なるほど。残業は大丈夫?」
応募者「はい、問題ないです」
──たったこれだけで終わってしまう。
質問はしているけれど、会話が浅い。
応募者は「ただ答えた」だけで、会社の印象はほぼゼロ。
対して“伝える面接”ではこうなります。
面接官「うちは3人1チームで現場回るスタイルなんですよ。リーダーが段取りをして、若手が学びながら動く形です」
応募者「へぇ、チームでやるんですね」
面接官「そうなんです。だから一人で黙々というより、“連携できる人”が合うかもしれませんね」
──この違い。
前者は「質問」、後者は「会話設計」。
応募者の理解と信頼をつくっているのは“情報の共有”なんです。
話さない面接で“採用ゼロ”だった会社が変わった
ある中堅の建設会社(舗装業)は、面接通過率が低く、応募者の辞退率が高いのが課題でした。
原因を探るため、面接を録音して分析すると──驚くことに、
面接官の発言は全体のわずか28%。
つまり、7割以上を応募者が話していた。
応募者にとっては「質問されて答えるだけ」で、会社の雰囲気も仕事のリアルも見えなかった。
そこで行ったのは、「話す量の再設計」。
・応募者:6割
・面接官:4割
にバランスを変更。
面接官が「仕事の流れ」「一日のスケジュール」「職場の雰囲気」などを具体的に伝える時間を増やしました。
結果、面接後の辞退率が52% → 18%へ改善。
たった数分“多く話す”だけで、応募者の信頼が劇的に変わったんです。
人は“理解した会社”を選ぶ
面接で応募者が重視しているのは「条件」ではなく「納得感」です。
人は、分からないものには不安を感じる。
特に建設業のような「現場の見えない職種」では、
“仕事内容がイメージできるか”が大きな決め手になります。
「なんとなく雰囲気が良かった」
「丁寧に話してくれた」
「一緒に働く人の顔が浮かんだ」
これらの理由で入社を決めた人が多いのはそのためです。
面接とは、“不安を言語化して取り除く時間”。
つまり、「会社がどれだけ話すか」で応募者の判断が決まるんです。
「話す量」を最適化するための3ステップ
では、面接官がどれくらい話せばいいのか?
単に“たくさん話す”のではなく、“戦略的に話す”ことが重要です。
① 前半10分は「自己開示トーク」
最初の10分で、面接官が会社のリアルを話す。
- どんな現場が多いか
- チーム体制
- 一日の流れ
- 最近の現場エピソード
これで応募者の緊張がほどけ、「会話モード」に変わります。
② 中盤15分で「掘り下げ質問」
ここで応募者に話してもらう。
ただし、“質問の前提”に会社の情報を織り交ぜる。
「今の話にあったように、チーム制ですが、一人で判断する場面もあります。そういう時どう考えますか?」
“質問に背景をつける”ことで、応募者の回答の質が上がります。
③ 後半5分で「未来の話」
最後は、“一緒に働くイメージ”を言葉にする。
「この現場だと、あなたの前職経験がすごく活かせそうですね」
「最初の3ヶ月はOJTでつきっきりになるので安心してください」
応募者が「ここで働く自分」を思い描ければ、採用は半分成功です。
会話構成で変わる印象の“温度差”
同じ内容でも、「順番」で印象は変わります。
| パターン | 流れ | 印象 |
|---|---|---|
| A社 | 応募者自己紹介→質問→条件説明 | “事務的”“冷たい” |
| B社 | 会社紹介→質問→現場紹介→条件 | “丁寧”“誠実”“話しやすい” |
話す順序を変えるだけで、「温かい会社」に見える。
応募者は、“情報”よりも“伝え方”で会社を判断しているんです。
職長が話すと応募者の信頼が2倍になる
現場リーダーが面接に同席して話す会社ほど、応募者の印象スコア(アンケート調査で測定)が高い傾向にあります。
その理由は単純です。
「実際に働く人の声」は、会社の広告より100倍リアル。
現場の職長が話すことで、
「この会社は人を大切にしている」
「現場の雰囲気が良さそう」
と感じる。
面接官教育をする前に、“話す人”を変えるだけで結果は動きます。
(参考記事 → 現場が採用に関わる会社ほど“人が集まる”)
応募者の信頼を得る“3つのトーク設計”
話す量だけでなく、“話す中身”も重要です。
特に建設業の応募者に響くのは以下の3つ。
① ストーリーで語る
数字や制度より、「人の話」が響きます。
「最初は未経験で入った若手が、今は班長になってる」
② “違い”を語る
他社と比べた「自社の特徴」を短く伝える。
「うちは元請け案件が多いので、残業が少ないんです」
③ “未来”を語る
応募者の成長イメージを見せる。
「1年後には現場リーダーを任せたいと考えてます」
“リアル+希望”を話せる会社ほど、選ばれます。
面接官教育=「話し方の共通言語化」
話し上手な面接官を育てるのではなく、
「話す構成」を共通化することが大事です。
採用職人では、以下の3つを面接教育で導入しています。
- トークスクリプト化(全社共通の面接台本)
- 10分単位の構成設計(話す量の比率を可視化)
- ロールプレイ評価(録音・自己評価で改善)
これにより、
「誰が面接しても印象が良い会社」になります。
詳細はこちらの記事で紹介 →
建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
実践企業の成果:面接トーク改善で応募率2.2倍
ある建築会社では、採用職人が作成した「話す構成シート」を導入。
面接官が先に“会社の想い”と“現場のリアル”を伝えるように変更しただけで、
一次面接通過率が68%→89%、内定承諾率が2.2倍に上がりました。
「話す量」が多い会社は、信頼される会社。
そして信頼される会社には、人が集まる。
(関連: 採用に成功する建設会社の共通点は「求人の出し方」ではない)
採用職人の支援で“話す面接”を仕組みに変える
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
面接官教育を通じて「話す構成」と「応募者心理設計」を仕組み化しています。
求人原稿で興味を持たせ、面接で“信頼”をつくる──
これが応募導線の本質です。
採用は、「話せる会社」が勝つ時代です。
まとめ:面接の勝敗は“話す比率”で決まる
“話し上手な面接官”より、“話す構造を持つ会社”。
応募者が安心する面接とは、質問が多い面接ではなく、会話の設計がある面接です。
面接とは、語りで信頼をつくる営業。
「伝える会社」に、人は集まる。
あなたの会社の面接、“話す量”は足りていますか?