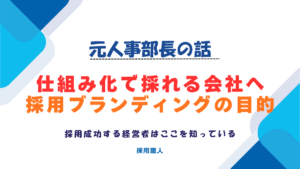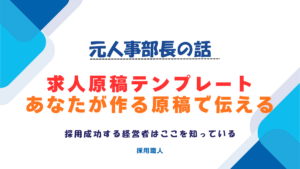採用ブランディングはゴールではなくスタート。現場から始める採用戦略設計
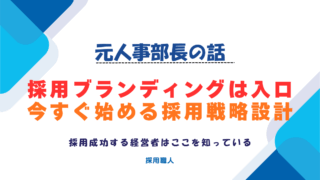
「採用ブランディング=最後に飾るもの」と思っていませんか?
多くの建設会社で、採用ブランディングは“見た目を整える最後の工程”とされています。
「写真を撮って、コピーを作って、サイトをリニューアルする」──
確かにそれもブランディングの一部です。
しかし、本来の採用ブランディングは“採用戦略の入口”にあるもの。
つまり、「誰を採るか」「なぜ採るか」「どんな会社を見せたいか」を決める“設計の起点”です。
この記事では、採用ブランディングを“戦略のスタート地点”に置くことで
採用が継続的に強くなる構造の作り方を、実例とデータを交えて解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
採用ブランディングを“出口”にしている会社は成果が出ない
「整える前に決める」ことが成功の条件
多くの会社が「求人を出して、うまくいかないからブランディングを考える」。
つまり、採用が行き詰まった“あと”でブランディングを導入します。
でも実際はその順序が逆。
採用ブランディングは、求人の“後処理”ではなく、採用戦略の設計段階から始まるものです。
建設業で成功している企業ほど、
求人を出す前に「何を伝えるか」「誰に伝えるか」を明確にしています。
それができている会社は、媒体を変えても応募数が安定します。
データ:ブランディングを“入口”に置いた会社の成果
採用効率が2倍・辞退率は半減
採用職人の支援先30社を分析したところ、
採用ブランディングを初期設計に組み込んだ企業は、以下のような成果が出ています。
| 項目 | 従来型(出口型) | 構造設計型(入口型) |
|---|---|---|
| 平均応募率 | 2.1% | 4.3% |
| 面接率 | 37% | 71% |
| 辞退率 | 29% | 12% |
| 採用単価 | 84万円 | 38万円 |
つまり、「採用ブランディングを最初に考える」だけで成果が倍増する。
なぜか?──それは、「伝える」前に「意味を定義している」からです。
👉関連して詳しく解説 → 「採用成功の8割は“設計”で決まる──現場が動く採用構造とは」
なぜ多くの会社は“出口型ブランディング”に陥るのか
「見た目から入る癖」が構造を歪めている
求人広告会社がよく提案するのは「写真・コピー・デザイン」。
つまり、“見せ方から入る”設計です。
でもその前に問うべきは、
「そもそも、どんな人を惹きつけたいのか?」
「何を伝えたい会社なのか?」
この問いが曖昧なままでは、
どんなに良い写真を撮っても、コピーを磨いても、“刺さらない”求人になります。
採用ブランディングとは、デザインではなく方向性の定義。
方向が決まっていないまま広告を出しても、効果は一瞬で消えます。
改善策①:「採用ブランディング=経営と採用の接点」に置く
経営方針と採用目的を一本化する
採用ブランディングは人事の仕事ではなく、経営戦略の一部です。
たとえば、
- 「10年後に社員数を2倍にしたい」
- 「若手の比率を上げたい」
- 「地域で“誇れる会社”になりたい」
このような経営目標があるなら、
採用ブランディングはその実現手段として“最初に”考えなければなりません。
つまり、ブランディングは“採用戦略の合言葉”。
「うちは何を大事にする会社か」を、求人文・面接・教育にまで一貫して浸透させるのです。
👉理念を言葉に変える方法はこちら → 会社の理念を“求人の言葉”で伝えるブランディング技術
改善策②:「入口設計」の3ステップ
伝える前に“決める構造”を持つ
ステップ1:採用ターゲットの“心理”を定義する
単に「若手が欲しい」ではなく、
「どんな価値観を持った若手か」「何を大事にしている人か」まで具体化する。
→ 採用心理を明確にすることで、伝える言葉が変わる。
ステップ2:現場ヒアリングで“自社の魅力”を再発見
現場の職長や職人から「この会社のいいところ」を聞く。
それがそのまま求人コピーの“素材”になります。
ステップ3:理念と現場をつなぐ“構造マップ”を作る
理念(Why)→文化(How)→求人(What)
この流れで一貫性を作ると、会社の発信に“深み”が出る。
👉関連テーマ → 採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
改善策③:採用ブランディング×DXで構造を可視化する
感覚ではなくデータでブランドを育てる
“入口設計”をさらに強くするのが**採用DX(データ連携)**です。
例えば、
- 求人閲覧率
- 面接通過率
- 職種別応募単価
これらを可視化することで、どのメッセージが刺さっているかを数値で判断できます。
実際、採用職人の支援先でDXを導入した企業では、
「理念を強調した求人」が最も応募効率が高く、
クリック率が平均+52%。
つまり、理念ブランディング=最強の広告資産になるのです。
👉詳しくは → DXで“人が採れる会社”に変わる──建設業採用の新常識
改善策④:「採用ブランディング=文化設計」で定着を生む
“理念で採り、文化で残す”
採用ブランディングの目的は“応募数を増やす”ことではありません。
本質は、「合う人を惹きつけ、辞めない人を育てる」こと。
ブランディングを入口に置くと、
・採用基準が明確になる
・面接で“価値観の一致”を重視できる
・教育方針が一貫する
結果、採用から定着までの流れが一本化される。
実際、ブランディング導入後に定着率が
58%→91%に上がった会社もあります。
👉関連解説 → 「建設業の離職率を下げる会社の共通点とは?定着率を上げる採用と育成の仕組み」
入口設計で「採用が止まらない会社」に変わったC社
“採用広報なし”で応募200人を実現
C社(外構工事・従業員17名)は、ブランディングを“戦略の最初”に導入。
以下の3点を設計しました。
- 「なぜ採用するのか」を経営理念と接続
- 「どんな人を採りたいか」を現場ヒアリングで明確化
- 「どんな言葉で伝えるか」を全社で統一
結果、求人掲載開始から半年で応募200件/採用20名を達成。
広告費は従来の1/3以下。
C社の社長はこう言いました。
「ブランディングを最後にやるものだと思っていた。
でも、最初にやったら“採用が止まらなくなった”」
採用ブランディングが“会社経営のOS”になる時代
採用はもはや広報ではなく、経営そのもの
採用は「人を集める」ではなく「人で会社をつくる」活動。
ブランディングは、その“思想”を社内外に伝えるOS(基盤)です。
これからの建設業では、
・現場の声をデータ化
・理念を見える化
・文化を継続的に更新
──この3つを仕組み化できる会社が“人に選ばれる会社”になります。
採用ブランディングとは、人を惹きつける装飾ではなく、組織を動かす構造設計なのです。
ブランディングは“伝える技術”ではなく“始める思想”
最初に整える会社が、最後に勝つ
採用ブランディングは、戦略の出口ではなく入口。
見せ方ではなく、採用の“出発点”に据えるべき思考法です。
人を惹きつけるのは、
派手な広告でも、きれいな写真でもありません。
“会社が何を信じて動いているか”──それを最初に決めた会社が、採用を制します。
採用職人の採用支援サービス紹介
現場採用のノウハウを体系化した採用職人の採用支援サービスでは、
採用ブランディング設計・導線構築・DXデータ分析までを一気通貫でサポート。
御社の採用を“戦略の入口”から設計し直すことができます。
noteで詳しく読む
「技術者が集まる会社」は求人原稿がうまいのではなく“仕組み”が違う
採用で“写真”が9割を決める──応募率を2.8倍にした「見せ方」の設計
求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由と“自社で採用を強くする方法”