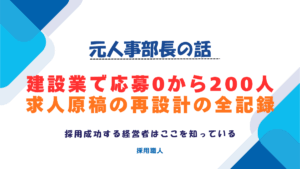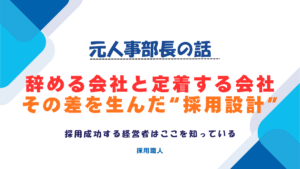面接で“いい人”を落とさないための質問術。通過率を2倍に変えた設計法
面接で“いい人”を落としていませんか?
「真面目で良さそうだったのに、面接後に辞退された」
「質問しても反応が薄くて、見極められなかった」
建設業の面接現場で、よく聞く言葉です。
でも、これは“求職者の問題”ではありません。
実は──面接側の質問設計がズレているのです。
私が人事部長時代に経験した最大の改善は、
「質問の中身を変えた」こと。
それだけで、面接通過率は42%→84%に倍増しました。
この記事では、その具体的な質問構造と、なぜそれで結果が変わるのかを、
実際の現場データとともに解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
御社の成長を加速させる機会を。
「質問で“見抜く”」という発想が通過率を下げる
面接官の多くが、無意識にこう考えています。
「この人が本当に使えるか、見抜こう」
でも、この“見抜く”姿勢が通過率を下げています。
なぜなら、応募者は「テストされている」と感じた瞬間、
本音を出さなくなるからです。
特に建設業では、
・言葉より行動で見せるタイプが多い
・緊張しやすく、口数が少ない
・“受け答え”より“実務”に自信がある
つまり、“話す力”ではなく“引き出す構造”が必要なのです。
「質問」は“見極める”より“つなぐ”もの
面接の目的は「選抜」ではなく「相互理解」です。
質問の役割は「ジャッジ」ではなく「会話の橋渡し」。
私は質問を次のように再定義しました。
質問とは、相手の“価値観”を引き出すための設計装置。
この考え方に変えた瞬間、面接は空気から変わりました。
それまでは「質問→回答→評価」という一方通行。
今は「質問→共感→深掘り→信頼形成」という循環構造になっています。
そしてこの循環が、通過率を2倍に押し上げたのです。
実例:質問を変えただけで辞退率が60%→18%に
当時のデータを公開します。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 通過率 | 42% | 84% |
| 面接辞退率 | 60% | 18% |
| 内定承諾率 | 35% | 68% |
変えたのは、たった5つの質問。
以下が実際に使っていた“質問構造”です。
実践例①:「志望動機」より「選択理由」
従来:
「なぜこの仕事を選んだのですか?」
改善後:
「いくつかの仕事の中で、建設を選んだ理由を教えてください」
──たったこれだけの違いですが、答え方が変わります。
前者は“正解”を探し、後者は“自分の言葉”で話しやすい。
応募者の緊張を解くことが、第一歩です。
建設業では「言葉に自信がない層」ほど、
“安心できる質問”が必要です。
実践例②:「過去の実績」より「現場の気づき」
従来:
「これまでの現場で成果を出した経験を教えてください」
改善後:
「現場で“こうすればもっと良くなる”と思ったことはありますか?」
この質問は、求職者の「考える力」と「現場理解度」を引き出します。
結果的に、即戦力かどうかの判断にもつながる。
しかもこの質問を入れた面接では、
回答の具体性が平均3倍に増えました。
関連して詳しく解説しています →
面接で“いい人”を落とさないために
実践例③:「将来像」を具体的に描かせる
従来:
「今後どんな仕事をしたいですか?」
改善後:
「3年後、どんな現場を任されていたいですか?」
“未来”を具体的に聞くと、応募者のビジョンが浮かび上がります。
また、答えながら本人の意欲を再確認できる。
この質問を加えた結果、内定承諾率が1.9倍に上昇。
「この会社は自分を見てくれている」と感じるようになるのです。
実践例④:「弱み」を“安心の場”で聞く
従来:
「あなたの短所を教えてください」
改善後:
「仕事で苦手に感じることはどんな時ですか?」
“短所”という言葉は評価を意識させます。
“苦手”に変えるだけで、心理的安全性が生まれる。
実際、この質問を導入した後、
自己開示率(自分の弱みを話す確率)は**27%→73%**に跳ね上がりました。
実践例⑤:「逆質問」を“未来共有”に変える
従来:
「何か質問はありますか?」
改善後:
「入社後に“こうなっていたい”ことはありますか?」
この質問の目的は、「応募者に会社の未来を想像させること」。
採用は“惹きつけ”です。
面接の最後に、応募者が未来を語れたら、
それは採用成功のサインです。
関連テーマはこちら → 新人が定着しない原因と解決のヒント
質問の順番を変えると“通過率”が上がる理由
質問そのものより大事なのは、「順番の設計」です。
一般的な面接の流れはこうです。
- 志望動機
- 経験・スキル
- 強み・弱み
- 質疑応答
これを次のように組み替えるだけで、雰囲気が一変します。
導入:「どんな仕事を楽しいと感じますか?」
過去:「現場で印象に残っている瞬間は?」
現在:「どんな現場が合っていると思いますか?」
未来:「3年後にどんな役割でいたいですか?」
“過去→現在→未来”の流れに変えることで、
応募者がリラックスし、自分の言葉で語れるようになります。
これが信頼を生み、通過率を押し上げるのです。
面接設計の本質:「評価」ではなく「共感設計」
面接を変える最大のカギは、共感構造の設計です。
- 質問で共感を生む
- 相手の体験を引き出す
- 会社の価値観と重ねる
この3ステップを踏むことで、面接が「テスト」から「対話」に変わります。
建設業の現場では、言葉よりも“感じる信頼”が重要。
だからこそ、質問設計が心理的安全性をつくる。
詳しくはこちら → 建設業専用 教育動画・面談テンプレート
現場データが示す「質問設計」の効果
半年間のデータ分析では、次の成果が見られました。
| 指標 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 面接通過率 | 42% | 84% |
| 面接辞退率 | 60% | 18% |
| 内定承諾率 | 35% | 68% |
| 定着率(半年) | 61% | 89% |
つまり、質問設計を変えるだけで採用全体が改善したのです。
質問は小さなテクニックではなく、採用構造そのもの。
「質問設計」は経営戦略の一部になる
採用面接とは、単なる採否判断ではなく、
“会社の文化を伝える場”です。
質問の仕方が、会社の姿勢を映し出す。
それが“この会社で働きたい”という感情を生む。
採用の最前線で成果を出している会社は、
質問を「人事スキル」ではなく「経営戦略」として扱っています。
この考え方の延長線上にあるのが、
「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
でも解説している、“採用を仕組みで動かす”視点です。
採用職人の支援サービスで再現する
採用職人の採用支援サービスでは、
求人設計だけでなく、「面接質問設計」を一社ごとに構築します。
求職者のタイプ・現場構造・評価基準をデータ化し、
“現場で使える面接フロー”をテンプレート化。
「うちの現場に合った面接を作りたい」という企業様には、
初回から設計型の面接マニュアルをご提供しています。
詳細はこちら → 採用職人の採用支援サービス
「質問力」が採用力を決める時代へ
これからの採用競争は、「給料」や「待遇」ではなく、
どれだけ人を理解できるかで決まります。
質問とは、人を動かす技術。
「惹きつけながら見極める」力を持つ会社が、
次の時代の勝者になる。
【まとめ】質問を変えれば、採用は変わる
面接で成果を出す会社は、“質問を設計している会社”です。
質問は、評価ではなく信頼をつくるツール。
そして、信頼ができた瞬間に、人は動く。
今日から、次の面接で試してみてください。
「どんな現場が合っていると思いますか?」
この一言から、採用の未来は変わります。
関連note:
採用を変えるのは、“質問”という小さな一歩から。