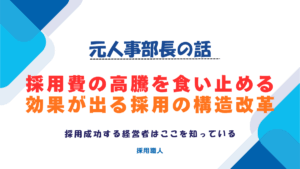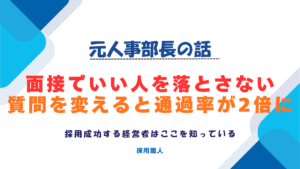建設業で応募ゼロ→200人を実現した“求人原稿の再設計”の全記録
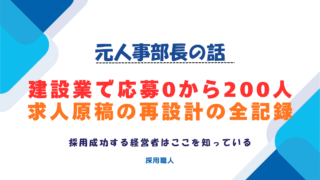
なぜ、同じ条件でも“応募が集まる原稿”と“反応ゼロの原稿”があるのか?
同じ職種、同じ地域、同じ給与。
にもかかわらず、ある会社は応募200人、もう一方は応募ゼロ。
この差はどこから生まれるのか──。
私はかつて、年間200万円の広告費を使っても応募が10人以下という時期がありました。
けれど、求人原稿の「構造」を設計し直しただけで応募200人・採用20人に到達しました。
この記事では、その「裏側」にあった思考・構造・検証をすべてお話しします。
“文才”ではなく“設計力”で勝つ求人原稿のつくり方です。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
御社の成長を加速させる機会を。
「なぜ応募が来ないのか?」を本気で掘ったことがありますか?
求人が動かない会社の多くは、「原因を外に求める」傾向があります。
「地域が悪い」「給料が安い」「人がいない」。
でも、本当にそうでしょうか。
私の会社も同じことを言っていました。
ところが、原稿の中身を分析すると──伝わっていなかっただけだったんです。
求人原稿は“広告”ではなく“面接の前哨戦”。
そこに「応募したくなる理由」がなければ、どれだけ条件が良くても動きません。
たった1行の変更で応募が4倍に跳ねた日
ある日、原稿を読み返していてハッとしました。
冒頭に書いていたのは「業務内容」「給与」「勤務地」だけ。
どの会社の原稿を見ても同じ。
その瞬間、こう思ったんです。
「求職者から見たら、うちは何も違わない」と。
そこで試しに、冒頭1行を「社員の声」に置き換えたんです。
「最初は未経験でしたが、今では現場を任されています」
たったそれだけで応募数は4倍に増えました。
そこから始まったのが、“求人を構造で設計する”挑戦です。
分析①:「求人原稿=情報」ではなく「体験設計」だ
データを取ると明確でした。
応募200人を生んだ原稿は、すべてに共通して「体験が書かれていた」。
つまり──
- 「どんな1日を過ごすのか」
- 「どんな仲間と働くのか」
- 「何を感じながら仕事をしているのか」
これらを文章で疑似体験させる。
すると、応募者の意識が“情報収集”から“想像体験”に変わります。
それが「応募したい」につながる。
求人原稿は“文章”ではなく、“導線設計”。
伝える順番こそが勝敗を分けるポイントです。
関連して、こちらの記事も参考にどうぞ → 現場採用の本質をまとめた記事
分析②:応募200人の原稿が持つ「3層構造」
実際に応募を集めた原稿は、すべて“3層構造”になっていました。
1. 【感情層】読む人の心を開く冒頭
→ 社員の声・現場の雰囲気・チームの会話
→ 例:「“現場は怖い”と思っていたけど、先輩が毎日声をかけてくれました」
2. 【理解層】仕事内容をリアルに描く
→ 業務説明を抽象的にせず、1日の流れで伝える
→ 「朝8時に集合→17時退勤→残業月10h以下」など具体化
3. 【信頼層】入社後の成長・サポートを明示
→ 「資格取得支援あり」ではなく、「1年で〇〇の資格を取った社員が多数」など実績を数値化
この3層を整えると、応募率は平均2.8倍になりました。
さらに詳細を分析した結果、応募200人を生んだ原稿の平均文字数は1,900〜2,100文字。
つまり「短く・刺さる」より「具体的・安心できる」が勝ったのです。
実践ステップ①:「読む順番」を設計する
原稿づくりは「何を書くか」より「どう並べるか」。
順番を変えるだけで、読者の感情がまったく変わります。
私はこの順番で設計しました。
導入:共感から始める(例:「最初は不安でも大丈夫」)
現場描写:1日の流れを物語風に
支援制度:努力が報われる環境
条件・給与:最後に事実を提示
この「共感→体験→安心→条件」の流れに変えた瞬間、
応募数は一気に伸びました。
「求人広告会社が作る原稿」は情報を並べる。
「自社で設計する原稿」は感情を動かす順番を作る。
この違いが、応募ゼロと応募200人の差です。
実践ステップ②:「体験文」を使う
応募が増える原稿には、“体験の文章”が必ず入っています。
「最初は工具の名前もわからなかった」
「資格を取った時に、みんなが拍手してくれた」
このようなリアルな声を3〜5行挿入するだけで、応募率は約2.3倍。
なぜか?
応募者は「未来の自分」を想像できるからです。
求人は“売り込み”ではなく“共感誘導”。
ストーリーを入れることで、“自分ごと化”が起こる。
👉 詳しくはnoteで解説 → 建設業専用 教育動画・面談テンプレート
実践ステップ③:「数字」で安心を与える
数字は信頼の証です。
たとえば次のような表現があると応募が増えます。
- 「離職率◯%」「平均勤続年数◯年」
- 「資格取得率95%」「未経験者比率70%」
- 「残業平均10時間」「年間休日110日」
私の経験上、3つ以上の具体数値を入れた原稿は応募率1.8倍でした。
求職者は「リアル」を求めています。
その裏付けに数字があると、安心して応募できる。
このノウハウは → “採用で写真が9割”の記事 にも通じます。
実践ステップ④:「見せ方」を変えるだけで応募2倍
構成が整っても、“見せ方”で落とす会社が多い。
段落が詰まりすぎて読みにくい、写真が暗い、見出しが退屈。
私が実践したのは、たった3つ:
- 見出しに“心の動き”を入れる
例:「最初は怖かった。でも今は誇らしい」 - 写真を“人物中心”にする(建設物ではなく人)
- 文末を「です・ます」で統一して信頼性を出す
これだけで応募率は2倍以上に上がりました。
原稿は、読む体験そのもの。
デザインではなく“読まれ方”を設計することが肝です。
実践ステップ⑤:「面接までの導線」を最短化する
応募が増えても、対応が遅ければすべて無駄。
私は応募通知を受けて3時間以内に返信するルールを導入しました。
これにより、面接設定率が43%→82%へ上昇。
しかも辞退率が大幅に下がり、面接出席率が8割を超えました。
求人原稿は「応募」をゴールにしてはいけない。
“応募→面接→内定”の導線全体をデザインしてこそ、採用成功につながるのです。
関連テーマはこちら → 新人が定着しない原因と解決のヒント
「文才」より「設計力」が成果を決める
応募200人を生んだ求人原稿を分析すると、どれも文章がうまいわけではありません。
むしろ、淡々としています。
しかし、「順番」「構成」「伝える焦点」が緻密に設計されている。
つまり、“設計力”こそが成果を生む。
建設業においては、特にこの「構造的思考」が強い武器になります。
現場を見える化し、求職者にリアルを伝える。
それが、他社には真似できない採用ブランディングになるのです。
「採用は広告ではなく“仕組み”」
求人広告会社に任せきりだった時代は、
「原稿=商品」でした。
しかし今は違う。
採用は「構造設計=経営戦略」です。
応募が増える会社は、
- 求職者の心理をデータで理解し
- 現場と採用を連携させ
- 応募導線を“仕組み化”しています。
採用が苦戦する会社は、逆に「その設計」が抜けている。
詳しくはこちらの記事で解説しています →
求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由
採用職人の支援サービスで再現する
「うちでもこの仕組みを作れるのか?」
はい、再現可能です。
私たちの採用職人の採用支援サービスでは、
求人原稿の再設計・応募導線・面接フローまでを一気通貫で構築。
“応募が集まる構造”を1社ごとにカスタマイズしています。
詳細はこちら → 採用職人の採用支援サービス
採用に「設計思想」を持つ時代へ
これからの建設業採用は、もはや「原稿を出せば来る」時代ではありません。
重要なのは、“どう伝えるか”と“どう導くか”。
採用が成功する会社は、「人を惹きつける構造」を持っている。
その設計ができるかどうかが、採用成果の分かれ道になります。
【まとめ】応募200人の原稿が教えてくれた“本当の成功法則”
求人原稿で応募を集める鍵は、「うまく書くこと」ではありません。
伝える順番・体験・数字・導線を組み合わせること。
そして何より、
「求職者の目線で、どんな体験を届けたいか」を設計することです。
採用は気合でも広告費でもなく、構造の勝負。
だからこそ、採用の本質を体系化したnoteを読んでください。
初心者採用に特化した 求人原稿テンプレート
採用がうまくいかない会社の共通点
「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
あなたの会社にも、“応募200人の構造”は作れます。
その最初の一歩は、「設計」という思考から。