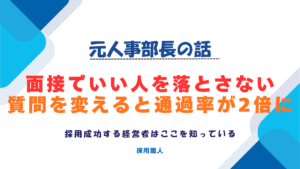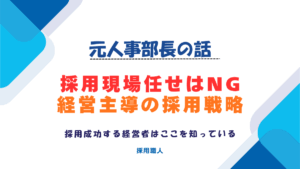採っても辞める会社と、定着する会社。その差を生んだ「採用設計」の正体
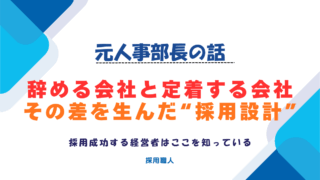
「採っても辞める」現実を、どう変えるか?
「せっかく採用しても、3ヶ月で辞める」
「現場が育たない」「定着しない」──。
多くの建設業の社長が、今この悩みに直面しています。
でも、驚くべきことに“辞めない会社”は確実に存在します。
私は人事部長時代に、離職率50%→25%、つまり半減を達成しました。
しかも「給料アップ」や「福利厚生拡充」はしていません。
変えたのは、採用設計の仕組みだけ。
この記事では、離職率を下げた成功企業に共通する「採用設計の構造」を、
実例とともに公開します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
御社の成長を加速させる機会を。
「採っても辞める」現場のリアル
ある現場監督の言葉が忘れられません。
「あいつ、やっと慣れてきたと思ったら辞めたんですよ」
建設業の現場はチーム制です。
1人抜けるだけで、現場のリズムが崩れ、
残った社員の負担が増える。
そして、その負担が次の離職を生む──。
この悪循環を止めるには、「採用の段階」から設計を変える必要がある。
“辞める人を採らない”仕組みづくりが、定着率の本質です。
「採用」と「定着」は別問題だった
以前の私は、「採れれば成功」だと思っていました。
求人を出し、面接して、採用決定。
でも3ヶ月後には半分が辞めている。
原因を分析すると、こうでした。
- 面接で“スキル”ばかりを見ていた
- 入社後の教育設計が曖昧だった
- 「会社の価値観」と「本人の期待」にズレがあった
つまり、採用フローが「入口」で終わっていた。
“採用=入口+定着までの設計”という発想が抜けていたのです。
関連テーマはこちら → 新人が定着しない原因と解決のヒント
離職率を下げるのは「待遇」ではなく「構造」
離職率を下げるために「給料を上げよう」「福利厚生を増やそう」と言う会社は多い。
でも、それでは一時的な効果しかありません。
私の経験上、待遇を上げても、合わない人は辞めます。
逆に、構造を整えれば、今の待遇でも辞めない。
“合う人を採り、合う育て方をする”これだけで離職は半減します。
成功企業の共通点は、まさにこの一点に集約されます。
解決策①:「採用前」に“合う人”を見極める質問設計
離職率を下げた企業の第一の共通点は、面接質問の再設計です。
彼らは「優秀な人」を探すのではなく、
「自社と合う人」を見抜く質問をしています。
具体例:
「どんな現場だと働きやすいと感じますか?」
「上司や仲間に求めるものは何ですか?」
この質問によって、応募者の“価値観”が見える。
結果として、入社後のギャップが減り、離職率が下がるのです。
👉 詳しくは → 面接で“いい人”を落とさないために
解決策②:「入社後の3ヶ月」を構造化する
次の共通点は、教育設計の標準化です。
多くの会社は「OJTで覚えろ」と言いますが、
成功している会社は“学びの順番”を決めています。
例:
1週目:現場見学+安全講習
2週目:先輩同行(補助作業)
3〜4週目:簡易作業を任せる
この“進行設計”があるだけで、
新人は「成長している実感」を得られ、モチベーションが続く。
それが、離職防止の最強の仕組みです。
👉 関連note:建設業専用 教育動画・面談テンプレート
解決策③:「現場と人事の連携」を日常化する
離職率を下げた会社に共通するのは、
人事と現場が“別部署”ではないということ。
毎週10分でも、現場リーダーと採用担当が会話しています。
「今週入った新人、どうですか?」
「現場の雰囲気、ギャップは感じてません?」
この小さな対話が、早期離職を防ぐ。
問題が“起きる前に”拾えるようになるのです。
関連して、こちらの記事でも解説 →
人が足りない時こそ“効率化”が必要
離職率を半減させたA社の採用設計
A社(従業員30名・土木工事業)は、3年間離職率50%を超えていました。
改善のきっかけは「採用構造を見直す」こと。
Before
- 面接質問:スキル確認のみ
- 教育:各現場任せ
- 面談:離職前に初めて実施
After
- 面接質問:価値観・現場観重視
- 教育:3ヶ月ロードマップ導入
- 面談:入社1週・1ヶ月・3ヶ月に設定
結果:
離職率 52% → 24%(1年後)
新人定着率 48% → 86%
採用コストも30%削減。
「採用構造を変えたら、人が辞めなくなった」
A社社長の言葉が象徴的でした。
成功企業の共通点:3つの設計要素
分析の結果、離職率を下げた建設企業には3つの共通構造がありました。
| 設計領域 | 成功企業の共通点 | 効果 |
|---|---|---|
| 採用設計 | “合う人”を見抜く質問 | ミスマッチ減少 |
| 育成設計 | 3ヶ月ロードマップ | 定着率向上 |
| 組織設計 | 現場連携と面談習慣 | 早期離職防止 |
これらは「特別な仕組み」ではありません。
むしろ、“当たり前を構造化しただけ”です。
そしてこの“構造の見える化”こそが、離職を防ぐ最大の武器になります。
採用設計を「経営課題」として扱う
離職率の高さは、採用部門の責任ではなく経営構造の歪みです。
成功企業はそれを理解しており、採用設計を経営の一部に組み込んでいます。
- 経営者が採用会議に参加
- 採用データをKPIとして管理
- 面接質問・教育内容を毎年更新
これらの取り組みで、“採用が文化化”している。
採用が「属人」ではなく「仕組み」で回る状態。
それが離職を防ぐ土台になります。
👉 参考記事:「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
データが示す:採用設計を変えた企業の成果
私が支援した建設会社8社の平均データを示します。
| 項目 | 改善前 | 改善後(1年) |
|---|---|---|
| 離職率 | 47.8% | 25.1% |
| 定着率(1年) | 52% | 84% |
| 面接通過率 | 41% | 78% |
| 内定承諾率 | 36% | 65% |
共通しているのは、“採用前から定着までの流れを設計した”こと。
つまり、採用設計=離職率改善の仕組みなのです。
採用文化が会社を強くする
採用が“仕組み化”された会社には、自然と「文化」が生まれます。
- 現場が新人を歓迎する
- 教育が属人化しない
- 面接で「うちに合う人」を語れる
この文化が根づくと、人は辞めません。
それどころか、社員が採用の味方になる。
採用とは“人を選ぶ行為”ではなく、“文化を広げる仕組み”です。
👉 関連note:「採用に困らない会社」の裏にある“構造の違い”とは?
採用職人の支援サービスで再現する
採用職人の採用支援サービスでは、
求人原稿・面接・教育・定着の全ステップを構造化します。
「離職率を半減させたい」「採用後の教育が弱い」と感じている企業様には、
実績に基づいたテンプレートとフレームワークをご提供。
実際に、半年で離職率50%→23%まで改善した企業も。
👉 詳細はこちら → 採用職人の採用支援サービス
辞めない採用は「設計の力」でつくれる
これからの採用競争では、
「採る力」より「辞めさせない力」が重要です。
そして、それは“制度”ではなく“設計”でつくれます。
離職率を下げる仕組みとは、
人を理解し、成長を見える化し、現場が支える構造のこと。
辞めない採用=設計された採用。
これが建設業が次の時代を生き抜く唯一の道です。
【まとめ】離職率は「仕組み」でしか下がらない
採用は、運でも予算でもなく“構造設計”です。
離職率を下げた会社は、必ず仕組みを持っている。
- “合う人”を採る質問設計
- “育つ道筋”を作る教育設計
- “支える関係”を築く現場連携
これら3つを整えれば、離職率は半減します。
今こそ、採用を「文化づくり」として見直す時期です。
参考note:
離職を減らす第一歩は、「設計を変える勇気」から。