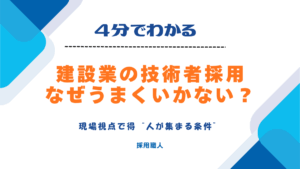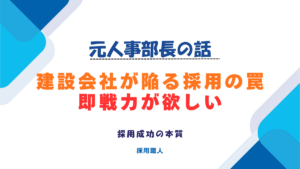「資格保有者を採れば安心」は間違い。建設業がやりがちな採用の勘違い
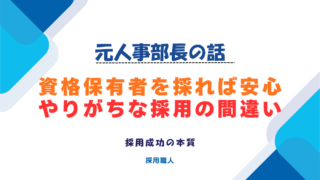
「資格者がいれば現場は回る」と思っていた頃の話
「うちは資格者がいないから現場が回らないんだ」
多くの建設会社の社長が、そう嘆きます。
たしかに資格は現場を動かすための“通行手形”です。
でも実は、資格保有者を採っただけでは現場は安定しない。
私は人事部長時代、この「資格神話」にどっぷり浸かっていました。
結果、採用コストは跳ね上がり、半年で辞める技術者が続出…。
この記事では、そんな失敗から得た教訓――
**“資格よりも現場適性を見抜く採用”**の考え方をお伝えします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
👉 動画を見る
① 🟧 「資格保有者=即戦力」
実は“採用後のミスマッチ”を生むリスクが高い
「一級施工管理技士を採れば安心」――。
一見、正しいように聞こえます。
でも、実際の現場ではこういう問題が起きます。
- 現場スピードについていけない
- 若手とのコミュニケーションが取れない
- 書類管理ばかりで現場を見ない
つまり、資格=スキルではなく、
“資格=条件”に過ぎないということ。
「資格者さえいれば」という採用方針は、
逆に離職リスクを高める落とし穴になります。
② 🟧 「資格よりも“働く姿勢”が現場を支える」
建設業の現場は“協働力”で動いている
現場では、資格があっても“人を動かせない”と成果は出ません。
施工管理者に必要なのは「段取り力」「伝達力」「信頼」。
あるベテラン職長が言っていました。
「資格より“声かけのタイミング”が上手いやつの方が現場は回る」
まさにその通りです。
現場は“人間力”の集合体。
資格より“人柄と姿勢”を採用で見抜くことが、結果的に現場力の底上げにつながります。
③ 🟧 「資格者採用で失敗した会社が変わった瞬間」
“資格偏重”から“現場適性採用”へ
私が人事部長時代に担当した建設会社A社。
最初の方針は「一級施工管理技士だけ採る」。
求人広告もそう書いていました。
結果――応募3名、採用ゼロ。
次に「資格は不問。ただし“チームで現場を支える意欲”重視」に切り替えたところ、
応募28名、採用4名。しかも全員1年以上継続勤務中。
キーワードを変えただけで、応募者層がガラッと変わったのです。
そのときに使用した求人原稿の改善法は、こちらで詳しく解説しています →
現場採用を劇的に変えた求人原稿の作り方
④ 🟧 「資格者を活かす採用設計の3ステップ」
“資格ありき”ではなく“役割設計ありき”に変える
STEP1:資格者の役割を明確にする
「現場管理なのか」「後輩育成なのか」「品質担当なのか」。
役割が曖昧なまま採ると、資格者が迷走します。
STEP2:資格要件を“条件”ではなく“目安”にする
「資格必須」ではなく「資格保有者歓迎(未取得者も育成)」に変える。
応募数は平均1.8倍に増えます。
STEP3:採用後のキャリア導線を示す
「2年後に主任」「資格手当アップ」など、未来を提示する。
これだけで離職率が大幅に下がります。
関連して、採用の導線設計はこちらの記事でも解説しています →
採用成功の現場フローを可視化した記事はこちら
⑤ 🟧 「“資格者を採る”より、“資格者が育つ仕組み”を作る」
採用の目的を“資格”から“戦力化”へ
資格者を採ること自体は悪くありません。
問題は、“どう活かすか”が設計されていないこと。
採用はゴールではなくスタート。
入社後に活かされない資格者は、いずれ離れていきます。
“資格者を採る”より、“資格者が育つ現場をつくる”。
それが、建設業の採用を安定させる本当の道です。
採用は“気合”ではなく“仕組み”。
御社の採用にも、その仕組みを取り入れてください。
🟧 「“資格者が集まる採用設計マニュアル”を公開」
有資格者採用のテンプレート付きで再現可能
この記事で紹介した“資格を活かす採用設計”を、
noteでテンプレート付きで公開しています。
・有資格者向け求人原稿テンプレート
・キャリア導線設計表
・資格別採用訴求リスト
・面接質問テンプレート
知らないまま求人広告を出すと、年間100万円以上の無駄なコストが発生します。
¥20,000のnoteで、1回の採用単価が1/3になる再現性があります。
🟧 「採用は“気合”ではなく“仕組み”」
“資格神話”から抜け出した会社だけが伸びている
資格は武器だが、万能ではありません。
真に強い会社は、“資格者が定着する仕組み”を持っています。
採用は“気合”ではなく“仕組み”。
御社の採用も、次の一手を“構造”から考える時期です。