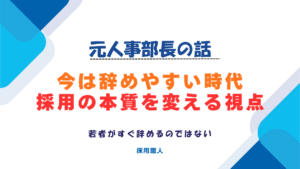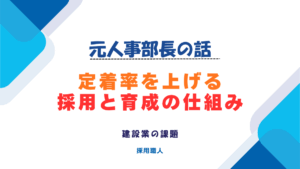「若者がすぐ辞める」のではなく「辞めやすくしている」のは会社側だ
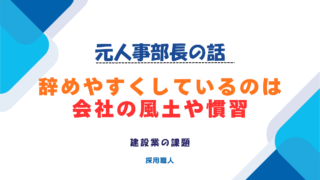
「すぐ辞める若者が悪い」のか?
「今の若者は根性がない」
「3日で辞める」
「すぐ他社に行く」
――建設業ではよく聞く声です。
けれど、冷静に考えればおかしいですよね。
“同じ若者”でも、他業界では続いているんです。
つまり、“辞めやすい構造”を作っているのは業界側。
若手が逃げるのは、「悪い社員」ではなく「逃げたくなる環境」なんです。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
建設業の若手離職率、実はかなり深刻
厚生労働省の最新データによると、
建設業の新卒3年以内離職率は約40%。
全産業平均(約32%)より高く、特に20代前半では顕著です。
さらに中小・零細規模の企業に絞ると、実質的には半数近くが辞めているという実感値もあります。
一方、ITや製造などの業界では、
オンボーディング・教育・キャリア設計が進んでおり、離職率は低下傾向。
つまり、**辞めやすい環境を作っているのは制度・文化の“遅れ”**なんです。
なぜ“辞めやすい環境”ができるのか(構造分析)
現場経験と人事の分析から言えば、理由は次の5つに集約されます。
① 入社後ギャップが大きい
求人広告では「アットホーム」「安定企業」など良い面ばかり。
いざ現場に入ると、
・体力仕事中心
・指示命令が強い
・休日が少ない
このギャップに、若手は最初の3ヶ月で心が折れます。
② 教える時間がない
現場は常に人手不足。
教育担当が施工管理と兼任しており、「教える余裕がない」。
放置=不安増=離職の黄金パターンです。
③ 感謝より叱責の文化
「まだ覚えてないのか」「前にも言っただろ」
昔は当たり前だったこの指導法、今は通用しません。
Z世代は“叱られる仕事”を我慢するより、“感謝される仕事”を探します。
④ 成長の“見える化”がされていない
建設業のキャリアは不透明。
「資格を取れば昇給」などの道筋を提示できないと、
若手は“将来が見えない”と感じ、離職します。
⑤ デジタル化の遅れ
タブレット・クラウド・チャット導入が進まない現場は、
「非効率」「古臭い」「上司がアナログ」と若者に映ります。
デジタル慣れした世代にとっては、それだけでストレス要因。
人事部長時代の実感:「放置は最大の離職リスク」
私が人事部長時代、最も離職率が高かったのは“現場研修期”でした。
入社1ヶ月以内に辞める若手のほとんどが、こう言っていました。
「教えてくれる人がいない」
「質問したら怒られる」
「自分が必要とされてない気がした」
つまり、**辞める理由は“人”ではなく“空気”**です。
現場の「忙しいから放置」が、最も高い離職コストを生んでいる。
関連して、こちらの記事でも詳しく解説しています → 採用成功の具体ステップはこちら
“辞めにくい”環境を作るための3つの改善策
ステップ①:入社前のリアル開示
「楽しい」「稼げる」ではなく、“大変だけど成長できる”を伝える。
リアルを語る会社ほど、入社後の定着率が高い。
ステップ②:新人サポートの仕組み化
教育担当を兼任ではなく、明確に役割化。
初期3ヶ月は“1on1形式”で週1フォローを設けるだけで、離職率が下がります。
ステップ③:現場文化の再教育
上司研修=「叱る技術」ではなく、「承認する技術」。
心理的安全性を高めることで、Z世代のモチベーションは上がります。
このテーマをもう少し掘り下げたい方は → 現場採用の本質をまとめた記事
辞めない建設業へ
今の建設業界は、「辞めやすい」環境から「続けたくなる」環境へ移行できるかの岐路にあります。
若手を“育てる余裕”を仕組み化できた企業だけが、5年後に人材を確保しています。
私が関わった企業では、導線設計と教育制度の見直しだけで
応募200人・採用20人・離職率10%以下を実現しました。
「若手が辞めない職場づくりマニュアル」
この記事で触れた内容をさらに体系化した
「若手定着・採用設計マニュアル」を**note(¥4,980〜20,000)**で公開しています。
・若手離職の5大要因とデータ分析
・入社3ヶ月の“定着設計テンプレート”
・教育担当・上司のコミュニケーション設計法
¥20,000は、“1人辞めるコスト”の1/20。
今、最も投資効果の高い“人材資産”対策です。
「辞めやすい」は時代のせいではない
建設業の若手が辞めやすいのは、社会のせいでも、若者のせいでもない。
会社が“辞めたくなる構造”を放置しているだけです。
だからこそ今、変えれば結果は出る。
採用職人の採用支援サービスでは、
求人設計から教育・定着までを一気通貫で支援しています。
御社の現場に“辞めにくい文化”を根づかせませんか?
採用は“気合”でも“広告費”でもなく、“仕組み”。
“辞めやすい”を“続けたくなる”に変えるのが、次の時代の採用です。