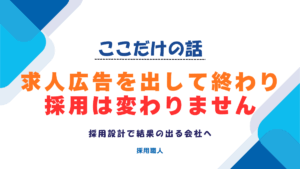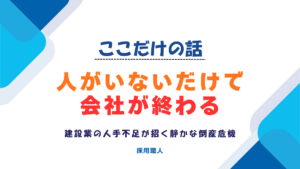採用のカギは“設計”と“連携”にあり。人事×現場で成果を出す採用構造の作り方
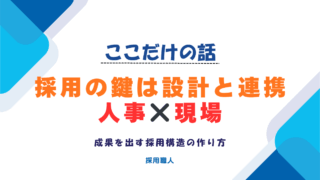
「現場の声」が採用のボトルネックを解く鍵になる
「人事が勝手に決めた条件じゃ、うちの現場には合わない」
「現場が忙しすぎて、面接なんて協力できない」
──こうした声、建設業ではどの会社でも耳にします。
しかし、採用を“現場と人事の対立構造”として見ている限り、永遠に人は集まりません。
本当に採用を強くしたいなら、“現場の声を仕組みに変える”設計が必要です。
私は元人事部長として、現場と人事が完全に噛み合わず、年間200万円の広告費が無駄になった経験があります。
そこから仕組みを再設計し、「現場主導の採用設計」を導入して応募200名・採用20名を達成しました。
この記事では、現場の声を採用設計に組み込む方法を、実例とともに解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
誤解:「採用は人事の仕事」だと思っていませんか?
「採用は人事がやるもんだろ」
これは、私が現場監督をしていた頃に、何度も口にした言葉です。
でも今、こう断言できます。──採用は現場の仕事でもある。
なぜなら、入社する人が一緒に働くのは人事ではなく、現場の職長・監督だからです。
現場のリアルを知らない採用は、“的外れな求人広告”を生み出します。
にもかかわらず、人事は「現場に協力してもらえない」と嘆き、現場は「どうせまた合わない人が来る」と冷めている。
この分断こそ、建設業の採用が進まない最大の理由です。
真実:採用の“設計”は現場の声が主軸になる
採用は、制度やフォーマットでは動きません。
現場の体験・温度・言葉──これが「共感を生む原稿」や「離職しないマッチング」をつくる源泉です。
たとえば、ある鉄筋工事会社の求人では、現場リーダーの一言を原稿に入れただけで応募率が2.3倍に跳ね上がりました。
「朝早いけど、帰りは早い。それを“きつい”と感じるか“自由”と感じるかで、向き不向きが分かる」
──この言葉が、求職者に刺さったのです。
つまり、「現場の声」を設計段階でどう活かすかが、採用成功を決めます。
実例:人事×現場の分断を“設計”で解消したケース
私が支援したA社(配管工事業)では、
人事は「若手が来ない」と嘆き、現場は「すぐ辞める」と怒っていました。
採用の流れを分析すると、求人原稿・面接・入社後教育がバラバラ。
現場ヒアリングを通じて「新人が不安に感じるポイント」をリスト化し、
求人段階から“現場視点の導線”に作り直したんです。
結果──
- 応募:月5件 → 月40件
- 面接率:25% → 68%
- 定着率:半年で43%→84%
現場の声を「設計」に落とし込んだだけで、ここまで数字は変わります。
関連テーマはこちら → 新人が定着しない原因と解決のヒント
実行法①:現場の“採用会議”をつくる
最初にやるべきは、「現場の意見を吸い上げる場」をつくることです。
形式はシンプルで構いません。
- 月1回30分、職長と人事で“採用ミーティング”
- 「どんな人が向いてる?」「辞めた人の共通点は?」を話すだけ
これを継続するだけで、採用方針の精度が上がり、現場の当事者意識が生まれます。
そしてここで出た意見を「原稿」「面接質問」「教育内容」に反映する。
つまり、“現場の声をデータ化して設計に落とす”のがポイントです。
実行法②:現場の言葉を求人原稿に使う
求人原稿は「会社の声」ではなく、「現場の声」で書くべきです。
たとえば:
- ✕「アットホームな職場」
- ○「昼休みは弁当持って全員で日陰に集まる」
現場の空気感をそのまま伝えると、応募者は“自分が働く姿”を想像できます。
この技法は、下記のnoteで具体的に紹介しています。
👉 初心者採用に特化した 求人原稿テンプレート〜経験ゼロから応募が集まる“建設業向け原稿の型”〜
実行法③:職長教育で“採用文化”を育てる
採用設計を支えるのは、仕組みだけではありません。
「人を迎える文化」を現場に根付かせる必要があります。
私は職長教育の中に「採用の視点」を組み込みました。
- 面接に同席する
- 新人受け入れ時に“初日チェックリスト”を活用
- 定着フォローを1on1形式で行う
こうした小さな積み重ねが、現場に「採用は自分たちの責任」という意識を芽生えさせます。
この考え方は、下記の教材で体系的にまとめています。
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
実行法④:人事が“通訳者”になる
人事の役割は「採用の管理者」ではなく、「現場と経営の通訳者」です。
職長が話す“現場の感覚”を経営に翻訳し、経営が語る“戦略の意図”を現場に戻す。
この双方向の翻訳ができると、採用方針のズレが消え、全員が同じゴールを見られます。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
この「人事と現場の連携構築」を、設計図として落とし込むサポートを行っています。
まとめ:現場の声を“偶然”ではなく“設計”に変える
現場の声は、放っておけば“愚痴”になります。
でも、それを仕組みに変えれば、“採用の武器”になります。
人事と現場が連携して動ける採用設計は、
採用効率を上げるだけでなく、職場文化そのものを変えます。
採用とは、人を集める活動ではなく、
現場と人事が同じ方向を向く仕組みを設計すること。
採用を変えたいなら、まず「現場の声」を仕組みに変える設計から始めましょう。
🔗 関連note・内部リンク
📘 採用職人 note 一覧はこちら → https://note.com/recruit_worker