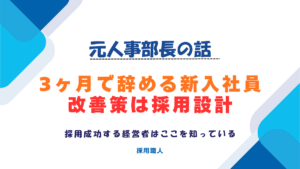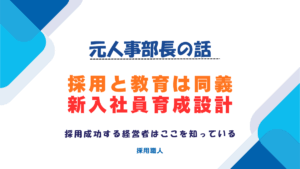「新人がすぐ辞める」は偶然じゃない。建設業の教育ミス構造
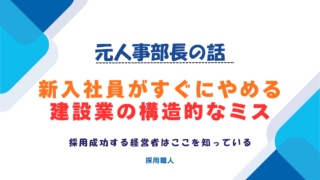
「教えているのに育たない」その原因は“人”ではなく“構造”にある
多くの建設会社が直面している悩み、それが「新人が続かない・育たない」。
「最近の若手は根性がない」「やる気が足りない」と言われがちですが、
実際にデータを見てみると、問題はもっとシンプルです。
教える仕組みが存在しない。
つまり、育てるための“設計図”がないのです。
この記事では、私が人事部長として200人以上の新人育成を見てきた経験から、
「現場で新人が育たない会社がやっていない3つのこと」を具体的に解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
7割の現場が「教育担当不在」という現実
ある業界調査によると、中小建設業の68%が正式な教育担当者を置いていないという結果が出ています。
つまり、入社した新人は「誰に教わるのか」も明確でないまま、現場に放り出されている。
現場監督の多くは「忙しくて面倒を見る余裕がない」と言います。
しかしその結果、新人は「自分の立ち位置が分からない」まま不安を抱え、3ヶ月以内に辞めるケースが後を絶ちません。
新人の離職理由は“人間関係”より“教育の不透明さ”
ある退職アンケートの集計では、離職理由の上位はこうです:
- 1位:何を求められているか分からない(43%)
- 2位:仕事の進め方を教えてもらえない(31%)
- 3位:評価が曖昧(18%)
つまり、辞める原因は「人間関係」ではなく、育成の見える化不足。
教育の流れが整っていない会社ほど、早期離職率が高い傾向にあります。
育たない会社に共通する“3つの欠落”
私が複数の現場を見てきて強く感じるのは、
「人が育たない会社ほど、教育を“人任せ”にしている」ということ。
具体的には、次の3つが欠けています。
- 育成の流れを定義していない
→ 入社から3ヶ月・6ヶ月・1年の“育成ステップ”が存在しない。 - 現場と人事の連携がない
→ 教える側と採用する側の情報共有が途絶えている。 - 職長の教育スキルを磨いていない
→ “教え方”を学んだ経験がなく、指導が属人的になっている。
これら3つが揃わない限り、どれだけ優秀な新人を採っても「育たない」のです。
改善策①:育成を“工程表”で見える化する
建設現場では図面と工程表が命。
教育も同じで、育成の流れを可視化することで初めて進捗が測れます。
新人教育を「見習い→実務補助→担当業務」と段階に分け、
それぞれに到達目標を設定する。
これを育成マップとして共有すると、
新人は「次に何を覚えるか」が分かり、現場は「どこまで任せていいか」を判断できるようになります。
この考え方は「教育テンプレート化」にも通じます。
→ 建設業専用 教育動画・面談テンプレート
改善策②:人事と現場の“採用連携ミーティング”を設ける
採用で伝えた「期待像」と、現場で教えている内容がズレていませんか?
このギャップが新人を混乱させます。
月1回の“教育連携ミーティング”を設け、
「どのレベルまで教えるか」「どの段階で現場デビューさせるか」を擦り合わせるだけで、
教育のブレは大幅に減少します。
関連して、こちらの記事も参考になります → 現場が採用を理解した瞬間、応募が倍増した話
改善策③:職長教育を“仕組み化”する
職長は“現場の先生”です。
ですが多くの会社では、「教え方を教わっていない」まま新人を指導しています。
私が関わったある建設会社では、
職長向けに“教え方講座”を導入したところ、
半年で新人の離職率が38%→12%に低下しました。
これは、職長が「叱る」から「導く」に変わった結果。
“教える技術”を学ぶことで、職長自身も成長するのです。
育つ現場は「個人」ではなく「チーム」で動く
教育の主語を“誰が教えるか”から“チームで育てる”に変えると、
新人の成長スピードは一気に上がります。
たとえば、
- 先輩A:安全ルール
- 先輩B:図面の読み方
- 先輩C:現場マナー
というように分担制を導入すれば、1人の負担も軽くなり、教育の質が安定します。
これが**「チーム育成モデル」**です。
より詳しい導線設計は → 採用しても辞める会社が見落としている人手不足の本当の理由
教育を仕組み化した会社の成果
教育改革を行ったA社(従業員30名)は、
- 新人定着率:6ヶ月で95%
- 職長の育成評価:前年対比+180%
- 応募数:前年比2.2倍
採用職人の支援を導入し、教育と採用の連動を構築したことで、
「新人が3日で辞める」状態から、「半年で戦力化」へ。
詳しい支援内容はこちら → 採用職人の採用支援サービス
「人を責めず、構造を変える」
新人が育たないのは、“個人の問題”ではなく“仕組みの問題”。
人を変えるより、仕組みを変えたほうが早いのが現場教育の鉄則です。
教育は気合ではなく設計。
怒らずに、焦らずに、“仕組みで育てる”環境を整えることが、
これからの建設業の標準です。
✅ 関連note記事
- 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
- 採用で“写真”が9割を決める──建設業で応募率を2.8倍にした「見せ方」の設計
- “採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由