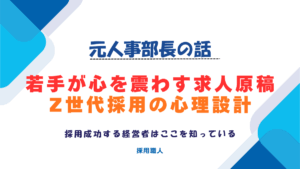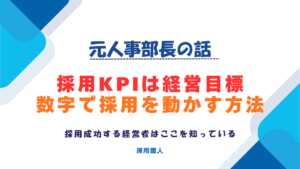採用がうまい会社は発信力より“文化力”がある。建設業の採用ブランディング実践法
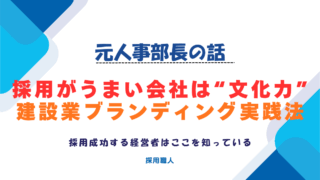
「SNSをやらないと採用できない」──本当にそうでしょうか?
最近よく聞くこの言葉。
でも、私はこう答えます。
「SNSがなくても、採用はできます。
ただし、“文化”がなければ、何を発信しても響きません。」
実際、私はSNSも使わず、広告費も減らしながら、
応募200名・採用20名を達成した会社をいくつも見てきました。
この記事では、SNSに頼らず若手が集まる採用ブランディングの設計法を、
現場目線で解き明かします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
SNSを頑張っても応募が来ない…
「うちもInstagramやってるけど、応募はゼロ。」
「動画を出しても反応が薄い。」
──そんな相談を受けるたびに感じます。
みんな“伝え方”には力を入れてるのに、“伝える中身”がないんです。
どんなに見た目を整えても、
そこに「この会社で働きたい」と思わせる“中身”がなければ、若手は動かない。
SNSは「拡声器」であって「メッセージ」ではない。
ブランディングの本質は、発信ではなく“信頼”の設計です。
見た目だけ整えた採用の末路
私が人事部長をしていた頃、
あるとき「若者ウケを狙おう」と動画を作ったことがありました。
ドローンで撮影した現場、かっこいいBGM、若手の笑顔──完璧な映像。
再生数は1万回を超えた。
でも、応募はゼロ。
理由は明確でした。
「この会社で働くと、どんな日々が待っているのか」が伝わっていなかった。
表面的な発信は「話題」にはなっても、「応募」にはつながらない。
若手は“キラキラ”より“リアル”を求めています。
“見せ方”ではなく“見られ方”を設計する
採用ブランディングで重要なのは、
「どう見せるか」ではなく「どう見られているか」。
たとえば、
- 面接で社長がどんな言葉を使うか
- 職長が新人にどう接しているか
- 先輩社員が会社をどう語るか
この“日常の振る舞い”が、
求人原稿や動画よりも強いブランディングになります。
採用とは、広告制作ではなく文化発信なんです。
関連記事 →
👉 「採用に困らない会社」の裏にある“構造の違い”とは?
解決策①:「会社の言葉」を整える
採用ブランディングの第一歩は、「会社の言葉」を整えること。
求人原稿、ホームページ、面接で言っている内容がバラバラでは、信頼は生まれません。
たとえば:
- ×「頑張りを評価します」
- ○「努力を見逃さない仕組みがあります」
- ×「アットホームな会社です」
- ○「先輩が“昼飯は一緒に食うぞ”と声をかける会社です」
抽象語をやめて、具体的な行動・仕組み・習慣で語る。
これが“伝わる会社”の言葉です。
解決策②:「現場の声」をブランディングの中心にする
Z世代や若手が信頼するのは、“会社の代表”ではなく“現場の声”。
だから、採用ブランディングの中心は社長ではなく職人。
新人が先輩をどう見ているか、職長がどう支えているか──それを発信する。
例:
「うちの現場は朝の声かけがうるさい。でも、それがありがたい。」
「最初に工具を貸してくれた先輩の言葉、今でも覚えてる。」
こうした現場のリアルこそが、**“会社のブランドストーリー”**になる。
関連記事 →
👉 現場が採用を理解した瞬間、応募が倍増した話
解決策③:「ブランディング=採用導線」の設計
ブランディングは“広告”ではなく“導線設計”の一部です。
つまり、採用フローのすべてが「印象づくりの場」。
具体例:
- 応募後のメール返信が「定型文」→印象ゼロ
- 面接前に「現場見学の案内」を送る→信頼が生まれる
ひとつひとつの接点を“ブランド体験”に変える。
それが、SNSを超えるブランディング効果を生みます。
関連記事 →
👉 「求人広告を出す前に考えるべきこと」
解決策④:採用を「教育」と連動させる
ブランディングは“言葉”で作るものではなく、“行動”で伝わるもの。
だから、採用と教育を切り離すと、ブランドは薄まります。
若手が入社後に「聞いてた話と違う」と感じた瞬間、
それまでの発信はすべて嘘になる。
教育体制こそ、最大のブランド資産。
実際、教育を仕組み化した会社では、定着率が90%を超えています。
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
解決策⑤:現場文化を“言語化”する
「うちの職人たちは口下手だから」と言う社長は多い。
でも、その“無口な誠実さ”をどう言葉にするかが、
採用ブランディングの要です。
例:
「派手さはない。でも、仕事終わりに“今日も無事故でありがとう”と言い合う現場です。」
この一文だけで、“どんな会社か”が伝わる。
文化とは、日常の習慣に宿るもの。
それを外の人に届く言葉に翻訳するのがブランディングの仕事です。
関連記事 →
👉 「求人会社に任せても採用できない理由──建設業が自社でやるべきこと」
ブランディングは「戦略」ではなく「姿勢」
SNSがなくても、発信力がなくても、
会社の“姿勢”さえ整えば、人は自然に集まります。
なぜなら、採用ブランディングとは「会社のあり方を伝えること」だから。
発信にお金をかける前に、
- 現場の空気を整える
- 言葉を揃える
- 行動を一貫させる
これを徹底するだけで、
採用は“広告”から“文化”へと進化します。
採用職人の採用支援サービス
採用職人では、建設業向けに「文化から作る採用ブランディング」を支援しています。
求人設計・導線整備・教育仕組み化まで一気通貫で構築。
詳細はこちら → https://recruit-worker.com/
まとめ:「SNSに頼らない会社」が最も信頼される
今の時代、“派手な発信”よりも“誠実な仕組み”が評価されます。
SNSをやめても、広告を止めても、
会社の中に「人を迎え入れる構造」があれば、人は集まる。
それが、本物の採用ブランディング。
そして──
「見せる採用」から「伝わる採用」へ。
これが、次の時代に生き残る建設業の採用戦略です。
関連noteリンク
- 採用に成功する建設会社の共通点は「求人の出し方」ではない
- 求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由と“自社で採用を強くする方法”
- 採用で“写真”が9割を決める──応募率を2.8倍にした「見せ方」の設計"
- “採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
note販売ページはこちら → https://note.com/recruit_worker