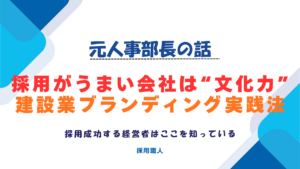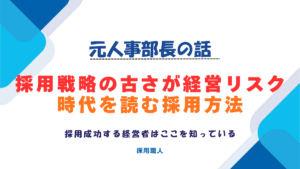採用KPIを経営目標に変える。数字で採用を動かす方法
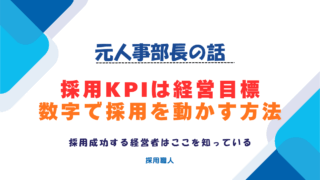
「採用KPIは人事の仕事」──この誤解が会社を止めている
経営会議で「採用の話になると静かになる」──
建設業の現場を支援していて、そんな光景を何度も見てきました。
売上や受注、利益率の議論は活発なのに、
採用だけは「人事に任せている」「現場に聞いてみる」と流されてしまう。
でも、よく考えてみてください。
採用が止まれば、施工量も止まり、売上も止まります。
つまり、採用は“経営の根幹”を動かすレバーなんです。
それにも関わらず、「採用KPI=人事の管理数字」と思い込んでいる会社が多すぎる。
本当は、採用KPIこそ経営の数字なんです。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「採用は感覚」から「採用は数値」へ──真実はいつも数字にある
多くの建設会社では、採用活動が“感覚”で進んでいます。
「応募はそこそこ来てる」
「良い人がいれば採る」
「なんとなくうまくいってる」
──これ、実は非常に危険な状態です。
採用は「感覚」ではなく「構造」で動きます。
その構造を可視化するのが“採用KPI”。
たとえば、下記のような基本指標があります。
| 指標 | 意味 | 理想値 | 経営での活用 |
|---|---|---|---|
| 応募数 | 1ヶ月あたりの応募者数 | 10人以上 | 母集団形成の目安 |
| 面接率 | 応募者のうち面接に進んだ割合 | 50%以上 | 原稿・対応の精度確認 |
| 採用率 | 面接者のうち採用した割合 | 10〜20% | 面接・評価の適性 |
| 定着率 | 採用者のうち半年後に在籍している割合 | 80%以上 | ミスマッチの有無 |
| 採用単価 | 1人採用にかかったコスト | 40万円以下 | 投資効率の判断 |
数字を「採用の健康診断」に使うのです。
採用KPIは、経営会議で扱うべき“経営数値”です。
なぜなら、人材を採る力=事業を伸ばす力だから。
実例:採用KPIを導入して“赤字脱出”した建設会社
私が人事部長を務めていた会社では、かつてこんな状態でした。
- 年間広告費:200万円
- 応募:10人以下
- 採用:1〜2人
- 離職:3ヶ月以内に半数が退職
社長も現場も「人がいない」と嘆き、採用は完全に行き詰まっていました。
そこで、経営会議に採用KPIのレビュー項目を設けたんです。
いわば、“採用の数字を経営会議に上げる”仕組み。
具体的にはこうです。
| 会議項目 | 月次データ | 経営判断 |
|---|---|---|
| 応募数 | 12件 → 26件 | 原稿改善・職種別導線修正 |
| 面接率 | 40% → 68% | 返信速度・対応品質の向上 |
| 採用率 | 8% → 16% | 面接評価基準の統一 |
| 定着率 | 50% → 83% | 教育フロー整備 |
| 採用単価 | 90万円 → 37万円 | 採用効率改善 |
半年後、応募は200人に増え、採用20人を達成。
採用コストは3分の1、施工班は倍、売上は5倍。
経営者が採用KPIを“自分の数字”として扱った瞬間、会社が変わりました。
採用KPIを「経営数字」にする3つの条件
単に数字を追うだけでは意味がありません。
採用KPIを“経営目標”に昇格させるためには、次の3つが必要です。
① 経営計画とリンクさせる
たとえば「来期に施工班を3班から4班に拡大する」なら、
必要な人員(例:職長1名、作業員3名)を逆算して採用KPIに反映させる。
経営計画(やりたいこと)
→ 採用計画(必要な人)
→ 採用KPI(必要な数字)
という“3段ピラミッド構造”を意識すると、採用が経営に直結します。
② KPIを「経営会議で報告する」仕組みをつくる
採用が形骸化する最大の理由は、「誰も数字を見ていない」こと。
経営会議に採用KPIの報告枠を設け、毎月更新するだけで意識が変わります。
- 「応募が減った原因は?」
- 「通過率が上がった要因は?」
- 「広告費の効果測定は?」
こうした議論が経営の場で起き始めると、採用は“経営言語”になります。
③ 定着率までKPIに含める
採用のゴールは「採ること」ではなく「育つこと」。
だからこそ、KPIは採用→定着まで含める。
採用率だけを追うと“ミスマッチ採用”が増える。
定着率まで数字で見れば、“会社の魅力と教育の質”が見える。
詳しくは以下の記事でも解説しています:
新人が定着しない原因は?建設業でよくある「定着の課題」と解決のヒント
採用KPIを導入するための実践ステップ
実際に、建設業の現場で導入できる手順を紹介します。
ステップ1:採用目標を“経営計画”に落とし込む
「売上10%アップ」→「施工班1班増」→「採用4名」
このように、“売上目標”から“採用人数”を逆算する。
ステップ2:現状KPIを洗い出す
まずは現状を見える化。
応募数・面接数・採用数・定着率・単価を整理する。
数字を「見えるようにする」ことが最初の改善です。
ステップ3:KPI目標を設定
理想ではなく、“現実的な改善値”を設定。
例:
- 応募数:10件 → 15件
- 面接率:40% → 60%
- 採用率:10% → 15%
- 定着率:70% → 80%
ステップ4:改善アクションを決める
数字が悪い項目に対して、原因と施策を特定。
- 応募数が少ない → 求人タイトル・原稿改善
- 面接率が低い → 応募返信スピード改善
- 定着率が低い → 教育・フォロー強化
ステップ5:KPIを毎月共有する
月1回の経営会議で更新し、推移を見える化。
数字が動くと、社員の意識も変わります。
実践企業の声:「数字で採用を見たら、経営が楽になった」
支援先のある中堅建設会社(社員30名)は、以前こう話していました。
「採用って感覚でやってたから、改善できなかったんですよね。
KPIを出した瞬間に、“何を変えればいいか”が見えるようになった。」
半年後には、
応募:12→35人
採用率:9%→18%
定着率:60%→85%
広告費は前年より100万円削減。
採用単価は半分になり、利益率も上昇。
社長はこう言いました。
「KPIを経営の言葉に変えた瞬間、採用が数字で語れるようになった。
感覚じゃなく、戦略で動かせるようになった。」
KPIが社内文化を変える
数字の面白いところは、“習慣化”すること。
経営が数字で話すようになると、現場も数字で動き始めます。
- 「応募5件足りないから、来週までに対策しよう」
- 「定着率が下がったから教育を見直そう」
こうして、採用が経営PDCAの一部になっていく。
採用は「特別な活動」ではなく、
売上・利益と同じく“日常管理”する数字になるのです。
採用KPI導入を成功させるコツ
- 完璧を目指さない
最初はざっくりでOK。重要なのは「見えること」。 - 経営者が最初に口を出す
数字に興味を持つのは社長から。
社長が聞けば、現場は必ず動く。 - 定期的にグラフ化する
視覚でわかると、モチベーションが上がる。
採用KPIを“社内スコアボード”にする。
採用KPIは“未来を読む”ための経営ツール
KPIの目的は「管理」ではなく「予測」です。
応募数が減れば、来期の人員不足を早期に察知できる。
定着率が下がれば、教育・給与体系を見直すタイミングが分かる。
採用KPIは、“未来のリスクを可視化する”経営レーダーなのです。
関連して、こちらの記事もおすすめです:
「人が足りない時こそ“効率化”が必要。建設業の現場を救う考え方とは?」
採用KPIを導入した企業の未来像
- 採用が「経営数字」で管理される
- 会議で“人材”が議題の中心になる
- 採用・育成・定着が一本の線でつながる
結果、会社の成長スピードは加速します。
採用KPIは、単なる数字の表ではなく、
「経営と現場をつなぐ共通言語」なのです。
まとめ:採用は数字で動かす時代
- 採用KPIは人事のためではなく経営のためにある
- 経営計画にリンクさせることで“採れる構造”が生まれる
- 数字を追えば、採用は感覚から戦略に変わる
採用は気合でも予算でもなく、構造と数字で決まります。
そしてその仕組みを体系化したのが、
採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から応募導線、採用KPIの運用設計まで、
“経営目線で動かす採用”を現場レベルに落とし込む。
御社の採用を、数字で動く経営資源に変えてみませんか?
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用KPIは、ただの“人事の数字”ではない。
それは、会社の未来を映す“経営のスコアボード”です。
数字で採用を語れる経営者がいる会社は、
人も、利益も、未来も、安定して集まってきます。