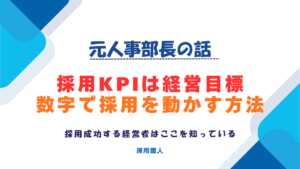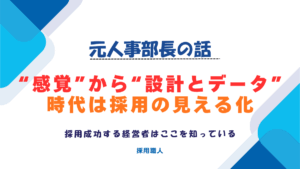採用戦略の古さが経営リスクになる。時代を読む会社だけが人を採れる
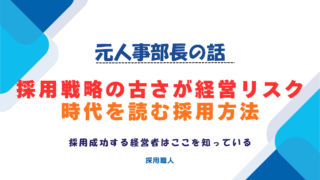
「昔は求人出せばすぐ来たんだけどな」それ、時代が変わっただけです。
建設業の経営者から、いまだによく聞く言葉です。
でも、はっきり言います。
「採用がうまくいかない会社は、人が変わったのではなく“時代を読んでいない”だけです。」
令和の採用は、もはや「求人広告を出す」時代ではありません。
“誰を、どう迎え入れるか”を設計できる会社だけが人を採れる時代です。
この記事では、「採用に失敗する会社」と「採用を仕組みで成功させる会社」の違いを、
現場のデータと経験から明らかにします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「人がいないから採れない」
「うちの地域は人がいない」
「若者が建設業を避ける」
──そう言い続けて、もう10年。
でも実際には、**「人がいない」のではなく「選ばれていない」**んです。
令和の若手は“働く場所を選べる時代”に生きています。
つまり、企業が選ばれる理由をつくれない限り、採用はうまくいかない。
それでも多くの会社は、
「給与上げた」「休み増やした」「広告出した」──これで終わり。
いま失敗しているのは、“対症療法”で時代の変化に遅れている会社です。
採用の主役は「会社」から「求職者」に変わった
昭和・平成は「企業が主導する採用」。
求人を出し、応募を選び、合否を決める構造。
でも今は完全に逆です。
Z世代・ミレニアル世代は「会社を選ぶ側」。
求人は“面接のきっかけ”でしかありません。
彼らが見るのは、
- 現場の雰囲気
- 働く人の価値観
- 会社の誠実さ
“この会社で働く意味”がなければ応募しない。
つまり、採用の本質は「条件の魅力」ではなく「文化の共感」に移ったんです。
関連記事 →
👉 「今の若者はやる気がない」のではなく「選択肢が多い」だけ
求人広告会社任せで失敗したA社の話
A社(従業員30名)は、年間200万円を求人広告に投入。
担当営業にすべて任せていたが、応募はたった5人。
社長は「広告会社が悪い」と怒っていた。
しかし原因は、求人原稿の中身が時代に合っていなかった。
「安定」「成長」「経験者優遇」平成型キーワードばかり。
求職者が求めていたのは、
「未経験でも育ててくれる安心」「自分の意見を聞いてくれる現場」
方向性を切り替え、原稿を現場視点に書き換えたところ、
応募は28件→採用5名。採用単価は1/3に下がった。
「時代を読む」とは、キーワードを変えることではなく、
“価値観の潮流”を読み取ることです。
👉 関連して詳しく解説 → 広告費をかけても応募が来ない理由は“キーワード選定”のズレにある
実例②:「採用文化」を再設計したB社の成果
B社は社長が「採用は現場が関与するもの」と決め、
職長全員が採用面接・教育に関わるようにした。
結果、若手の定着率が70%→92%へ。
これは奇跡ではなく、文化のアップデート。
採用を“人事の仕事”ではなく“現場のプロジェクト”に変えたことで、
社員全員が「次の仲間を迎える姿勢」を持つようになった。
採用がうまくいかない会社ほど、
採用が「誰かの担当」で止まっている。
今は、“全員採用”の時代です。
👉 関連記事 → 現場が採用を理解した瞬間、応募が倍増した話
実行法①:まず「採用の前提」を変える
最初にやるべきは、“採用の定義”を変えることです。
- ×「求人広告で応募を集める」
- ○「会社を信頼してもらう仕組みを作る」
採用はマーケティングではなく信頼づくりの設計。
そのために必要なのは、3つの視点。
1.言葉を整える(求人原稿・HP・面接トーク)
2. 現場を見せる(写真・動画・ストーリー)
3.約束を守る(言ったことを実現する)
これが「時代に合う採用設計の三原則」です。
👉 詳しくはこちら → 採用成功の8割は“設計”で決まる──現場が動く採用構造とは
実行法②:「情報」ではなく「物語」で採る
Z世代・20代が反応するのは“数字”ではなく“ストーリー”。
求人原稿に「誰が、なぜ、その仕事をしているか」を入れる。
例:
「入社3年目。最初は怒られてばかりでしたが、
今は新人に工具の名前を教えられるようになりました。」
この一文があるだけで、応募者は“自分の未来”を想像できる。
つまり、求人原稿は「説明文」ではなく「共感の物語」に変えるべきなんです。
関連記事 →
👉 Z世代が応募したくなる求人原稿の条件
実行法③:「採用データ」を感覚ではなく数値で見る
採用に成功している会社は、“感覚”ではなく“構造”で動かしています。
- どんな原稿で応募が増えたか
- どの経路から面接につながったか
- どの現場長が採用後の定着率が高いか
これらをデータとして蓄積・改善する。
「経験と勘」ではなく「検証と更新」で採用を強くする。
これこそ、“時代に合った採用マネジメント”です。
実行法④:「現場の教育」とセットで考える
今の時代、“採用だけ成功しても意味がない”。
なぜなら、入社後に辞めるスピードが早いから。
だから採用の出口に“教育の仕組み”をつくる必要があります。
面談・動画OJT・育成テンプレート──それらが“辞めない導線”になる。
教育設計を組み合わせることで、
「採用→定着→育成→再採用」のサイクルが完成します。
👉 教育設計はこちら → 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
実行法⑤:「採用文化の刷新」をトップ主導で行う
経営者が“採用に口を出す”ことを避けてはいけません。
いまの時代、採用文化はトップメッセージから始まる。
「うちの会社は、誰を仲間にしたいか」
「どんな人なら長く働けるか」
この言葉を経営者が発信するだけで、
会社全体の採用行動が変わります。
文化は施策ではなく、“思想”から始まる。
採用文化を変えた企業の平均成果
採用文化を再設計した10社の平均データ:
- 応募数:平均2.7倍
- 面接率:+42%
- 定着率:+31%
- 採用単価:平均40万円以下
SNSや広告に頼らず、仕組みと文化で人が集まる構造を実現しました。
関連して、成功事例の詳細はこちら →
👉 “採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
まとめ:「時代に合わせる」ことが、採用の最大の競争力になる
採用がうまくいかない会社は、人が悪いのでも、業界が悪いのでもない。
“時代を読んでいない”だけ。
今の採用は、
「条件で選ばれる時代」から「共感で選ばれる時代」へ。
つまり、採用の本質は「広告」でも「偶然」でもなく、“設計と文化”。
それを整えられる会社だけが、
この「人が辞めやすい・選びやすい時代」に、採用で勝ち残るのです。
採用職人の採用支援サービス
採用職人では、建設業向けに「時代対応型の採用構造設計」を支援しています。
求人設計・導線構築・教育連動までを一貫支援。
詳細はこちら → https://recruit-worker.com/
関連noteリンク
- 「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
- 採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
- 求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由と“自社で採用を強くする方法”
- 「技術者が集まる会社」は求人原稿がうまいのではなく“仕組み”が違う
note販売ページはこちら → https://note.com/recruit_worker