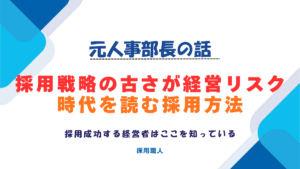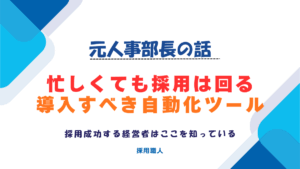採用は“感覚”から“設計とデータ”の時代へ。建設業の採用を変える「見える化」の力
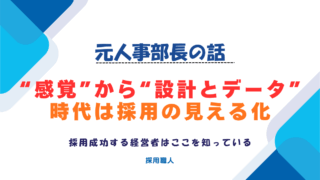
採用を「感覚」でやっていた時代は終わった
かつては「求人を出せば人が来る」時代がありました。しかし今、採用は“感覚”では勝てません。
応募が来ない、面接に来ない、定着しない──これらの課題の根底には、「採用の設計」と「データの見える化」が欠けていることが多いのです。
この記事では
採用を“設計とデータ”で再構築するDXの考え方を、建設業の現場実例を交えて解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
建設業の採用現場に起きている“構造変化”
求人倍率は年々上昇し、2025年の建設業の有効求人倍率は4.2倍(厚労省調べ)。
つまり「1人を取り合う時代」です。
それでもなお、「求人広告に出せば応募が来る」と思っている経営者は少なくありません。
実際には、求人広告会社に頼っても応募が増えない理由は明確です。
それは採用を“広告”として扱っているからです。
採用は「集客」ではなく「設計業務」です。
導線を組み、データを見て、改善を回す。
この考え方がなければ、どれだけ広告費をかけても結果は安定しません。
関連記事 → 「求人会社に任せても採用できない理由──建設業が自社でやるべきこと」
感覚採用から見える“ムダと損失”
私が建設会社の人事部長をしていた頃、
年間200万円以上の求人広告費を使っても応募10人未満・採用0〜3人という時期がありました。
当時の課題は「データがない」ことでした。
・どの媒体から何人応募が来たのか
・どんな原稿がクリックされているのか
・面接率・採用率がどこで落ちているのか
これらが見えないまま感覚で動いていたのです。
しかし、データを整理しただけで驚く変化が起きました。
クリック率の高い原稿を分析し、応募導線を再設計した結果──
応募200人・採用20人、応募単価3万円・採用単価40万円以下を実現。
つまり、“感覚”から“見える化”へ切り替えた瞬間に採用は利益構造に変わったのです。
“採用がうまくいかない”会社の共通点
多くの会社に共通するのは、
採用データを「広告会社が持っている」状態です。
自社ではクリック数も応募経路も分からない。
そのため、改善の打ち手が「広告の変更」か「予算アップ」しかない。
これではいつまで経っても「採用ノウハウ」は会社に蓄積しません。
採用は外注するものではなく、自社の経営データの一部として扱うべきです。
“感覚採用”から抜け出せない企業ほど、広告会社任せの構造になっているのが実情です。
関連して、こちらの記事もおすすめです → 建設業の社長が知らない「求人広告会社の営業マン」が絶対に教えない真実
改善策①:採用を“設計業務”として再構築する
まず必要なのは、「採用担当=広告担当」という誤解を捨てること。
採用は“設計職”です。
採用設計の3ステップ
- データを整える
媒体別応募数、クリック率、面接率、定着率を一覧化。 - 導線を設計する
応募→面接→採用→定着までの各フェーズでボトルネックを特定。 - 改善を回す
KPIを設定し、毎月PDCAを実行する。
この3つを回すだけで、広告費を増やさずとも応募数・採用数は安定します。
特に中小の建設会社では、エクセル1枚のデータ設計でも十分に機能します。
関連記事 → 採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
改善策②:採用DXで“属人化”を脱する
DX(デジタルトランスフォーメーション)というと難しく聞こえますが、
要は「データを集めて仕組みで回す」こと。
建設業の採用DXは、
・スプレッドシートで応募管理を可視化
・応募者データをグラフ化
・改善指標(応募→面接→採用率)を毎月共有
たったこれだけでも“採用の属人化”を防ぎます。
現場と人事が共通のデータを見れば、
「どの求人が効いているか」「どの面接官が結果を出しているか」も分かる。
つまり、採用がチーム業務に変わるのです。
この仕組みづくりの考え方は、こちらの記事でも解説しています → 現場が採用を理解した瞬間、応募が倍増した話
改善策③:データを“経営指標”として扱う
採用データは「人事の数字」ではありません。
それは、会社の未来を示す経営データです。
たとえば、
- 応募単価の上昇 → 市場競争力の低下
- 定着率の低下 → 教育設計の欠陥
- 面接辞退の増加 → 求人の魅力訴求不足
これらはすべて経営判断の材料になります。
「採用に強い会社」は、これらを経営会議で扱います。
数字で語れる採用担当者を育てることが、採用DXの第一歩です。
採用は“経営デザイン”になる
これからの採用は、単なる人集めではありません。
採用=経営をデザインする仕事です。
データを元に採用を設計し、
仕組みで現場を動かす──それが次世代の“採用力”です。
この考え方を体系的にまとめたnoteはこちら:
「採用がうまくいかない会社の共通点」
「求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由と“自社で採用を強くする方法”」
「“採用で苦戦する会社”が必ずやっていない3つのこと」
そして、採用の仕組みを現場レベルで導入したい方は、
こちらの実践noteもおすすめです:
建設業専用 教育動画・面談テンプレート
初心者採用に特化した 求人原稿テンプレート
まとめ:採用は「気合」でも「広告」でもなく、“仕組み”で動かす
「採用が難しい時代」と言われますが、
実際に成果を出している会社は、“データを設計できている”会社です。
採用はもう、感覚では勝てません。
データを集め、設計を組み、改善を回す。
この3つのサイクルが回り出した瞬間、
採用は「コスト」ではなく「利益を生む仕組み」に変わります。
採用職人の採用支援サービスのご案内
現場採用のノウハウを体系化した
『採用職人の採用支援サービス』では、
求人設計から応募導線の最適化までを一気通貫で支援しています。
御社の採用成功を実現する実務設計を、今すぐ体験してみませんか?
関連して読まれている記事:
・「応募が来ない時代に、なぜあの会社だけ採用できるのか?」
・「建設業の離職率を下げる会社の共通点とは?」