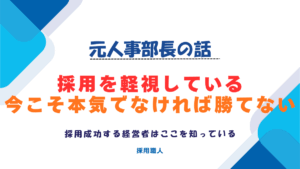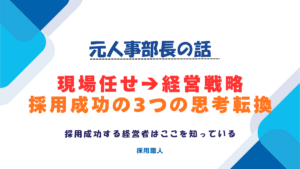採用計画を「経営計画」に組み込むだけで業績が安定する理由
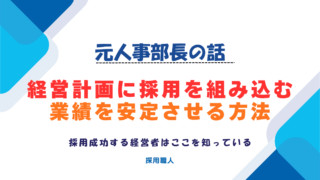
「採用は採用、経営は経営」──その考えが会社を止めている
「採用の話は人事に任せている」
「経営会議では数字(売上・利益)しか扱わない」
──もしそう思っているなら、危険信号です。
なぜなら、採用計画と経営計画がズレる会社ほど、業績が不安定になるからです。
採用は人を集めるための「イベント」ではなく、
事業を継続させるための“経営装置”です。
それを経営計画の外で動かしてしまうと、
いくら求人広告を出しても、いくら現場が頑張っても、結果はついてきません。
データが示す「採用を経営に組み込んでいる会社」の安定性
リクルートワークス研究所の『中小企業採用構造変化レポート2024』によると、
採用計画を経営計画に組み込んでいる企業は、そうでない企業に比べて
- 離職率:−27%
- 業績の年次変動:−38%
- 採用単価:−32%
と、いずれの指標でも安定しています。
つまり、「採用を経営の一部として扱うだけで」、
会社は“波の少ない成長”を実現できるということ。
参考:リクルートワークス研究所「中小企業の採用構造変化レポート2024」
https://www.works-i.com/research/
建設業に多い“採用が浮いている”状態とは
建設業の経営者と話していると、こんなパターンをよく見ます。
経営計画書には「売上目標」「受注目標」「粗利率」などがあるのに、
「採用人数」や「育成計画」が一切書かれていない。
これでは、採用が“経営の外”で動いている状態です。
たとえば、来期の目標に「施工班を2班から3班に増やす」と書いてあるのに、
その裏付けとなる人員採用計画が存在しない。
この矛盾こそが、建設業の成長を止めている「構造的ボトルネック」です。
採用計画を経営計画に組み込むと起きる3つの変化
経営と採用をつなぐだけで、会社は確実に変わります。
① 計画に“人”の視点が加わる
「数字(売上・利益)」だけだった経営計画に、
「人材(採用・育成)」という“現実的なリソース”の視点が加わる。
結果、無理のない経営計画になる。
② 採用活動に“経営判断”が入る
「誰を採るか」「いつ採るか」が経営戦略と直結するため、
採用の優先順位が明確になる。
③ 人件費が“コスト”から“投資”に変わる
採用・教育・評価が事業計画の一部として予算化される。
人に使うお金が“攻めの費用”になる。
この3つが整うと、採用は一気に「仕組み化」されていく。
実例:採用を経営に組み込んだだけで黒字化した会社
私が人事部長をしていた頃、
ある中小建設会社は、年間200万円の求人広告費をかけても応募は10人以下。
採用は毎年ゼロ〜2人。
当然、施工量は伸びず、赤字続き。
そこで、社長と一緒に経営計画の中に採用セクションを新設しました。
内容はシンプルです。
- 3年後に施工チームを4班体制へ
- 必要人員:15人 → 24人
- 年間採用目標:4〜6人
- 採用単価目標:40万円以下
この「採用KPI」を経営会議で毎月レビュー。
広告効果・面接通過率・定着率を数字で追いかけました。
結果、半年で応募200人・採用20人を達成。
翌年、売上は5倍、黒字転換。
経営が採用を「数字で管理」した瞬間、会社が回り出したのです。
採用KPIを経営指標に組み込む方法
「採用KPI」というと難しく感じるかもしれませんが、
本質は“経営の言葉で採用を語る”こと。
たとえば──
| 指標名 | 定義 | 理想値 | 経営への影響 |
|---|---|---|---|
| 応募数 | 求人に対しての応募者数 | 月10名以上 | 母集団形成の基礎データ |
| 面接率 | 応募者のうち面接に進んだ割合 | 50%以上 | 原稿・対応スピードの精度 |
| 採用率 | 面接者のうち採用に至った割合 | 10〜20% | 面接設計と評価基準 |
| 定着率 | 採用から6ヶ月後の在籍率 | 80%以上 | マッチングと育成設計 |
| 採用単価 | 1人当たりの採用コスト | 40万円以下 | 投資効率の把握 |
これらを経営会議の議題に組み込むだけで、
採用は“経営数値”として扱えるようになります。
採用計画を経営にリンクさせる5ステップ
実際に、採用を経営に組み込むための手順を紹介します。
ステップ①:事業目標をもとに必要人員を算出
「施工班を増やす」「売上を20%伸ばす」──
これらの目標を“人”に落とし込む。
(例:1班=3人 × 2班追加=6人採用)
ステップ②:採用計画表を作る
- 年間採用人数
- 採用時期
- 採用コスト
- 担当責任者
を明文化。Excelやスプレッドシートで管理するだけでも効果的。
ステップ③:KPIを設定
応募数・面接率・定着率などを、
「経営会議のKPI」として毎月チェック。
ステップ④:採用活動を“プロジェクト”として運営
採用を単発のイベントにせず、年間プロジェクト化。
進捗報告を「営業・経理」と同じ扱いに。
ステップ⑤:採用後の定着データも分析
採用は“ゴール”ではなく“入口”。
定着率や教育コストも経営数値として追う。
関連して、採用定着についてはこちらの記事も参考に:
新人が定着しない原因は?建設業でよくある「定着の課題」と解決のヒント
「経営×採用」が噛み合うと、社員のモチベーションも変わる
経営計画に採用が入ると、
社員は「自分たちの採用に社長が本気なんだ」と感じる。
面接時にも、社長が語る言葉に重みが出る。
「この採用は、うちの3年後の体制をつくるための投資なんだ」
──この一言が、求職者の心を動かす。
採用が“数字”から“物語”になる瞬間です。
採用計画がない会社に起こる5つの弊害
反対に、採用が経営計画に含まれないと、次のような弊害が生じます。
- 人が足りなくなってから慌てて募集する
→ 毎回、急募でコストが高くなる。 - 採用目標が曖昧
→ 「とりあえず誰か来てくれればいい」採用になる。 - 人件費が読めない
→ 経営計画が“数字の綱渡り”になる。 - 人が定着しない
→ 採用の目的が現場レベルで共有されない。 - 育成計画が後手に回る
→ 教育コストが年々増え、利益を圧迫。
つまり、「採用計画を作らないコスト」は、広告費よりも高いのです。
経営会議で使える「採用計画シート」の考え方
採用計画を経営会議で扱うには、以下の4要素を1枚で見せるのがポイントです。
| セクション | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1. 経営目標 | 売上・受注・班数など | 採用の背景を明確化 |
| 2. 採用目標 | 年間採用人数・職種・時期 | 数値化による行動管理 |
| 3. 採用KPI | 応募・面接・採用・定着 | 成果の見える化 |
| 4. 担当・進捗 | 責任者・次回対応 | 継続的改善 |
これを毎月見直すだけで、採用は“経営会議の議題”に昇格します。
実際のフォーマットは、こちらの記事でテンプレート付きで紹介しています。
建設業の採用はお任せください。母集団の形成に成功応募件数UP!
採用計画を経営に組み込むことの“心理的効果”
面白いことに、採用を経営計画に入れると、
社員の「責任感」と「当事者意識」も変わります。
なぜなら、採用が会社全体の“未来設計”になるから。
現場が「自分たちの仲間をどう増やすか」を考え始め、
人事が「現場をどう支えるか」に変わり、
経営者が「人をどう活かすか」に集中できる。
採用は、組織の方向性を一つに揃える装置なんです。
採用計画が経営を安定させる理由
経営の数字は、最終的に「人の動き」によって決まります。
受注量が増えても、施工班が足りなければ売上は伸びない。
新しい現場が取れても、職長が育たなければ品質が落ちる。
結局のところ、経営計画は人材計画の上に成り立つのです。
採用計画を経営に組み込むことは、
単に「人を採る仕組み」ではなく、
「会社を未来に運ぶ仕組み」をつくる行為です。
まとめ:採用を経営の中に戻そう
- 採用計画を経営計画に組み込むだけで業績は安定する
- 採用KPIを設定すると、採用は「数字で語れる経営テーマ」になる
- 採用は経営の鏡──“採る力”が“伸びる力”をつくる
採用は、気合でも予算でもなく、仕組みで決まります。
その“仕組みづくり”を体系化したのが、
👉 採用職人の採用支援サービス です。
求人設計から応募導線、採用KPIの運用までを一気通貫で支援し、
御社の採用を「経営の一部」に変える仕組みを提供しています。
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
関連リンク
最後に。
採用は「人を集める作業」ではなく、
「未来をつくる経営判断」です。
経営計画書の中に“採用計画”の1ページを増やす。
それだけで、会社は安定し、成長し始めます。