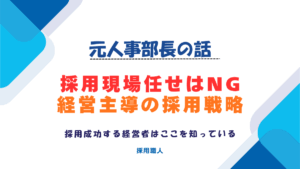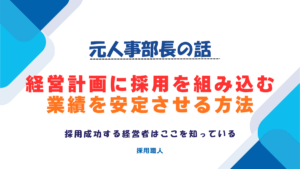採用難は「人がいない」ではなく「経営が採用を軽視している」だけ
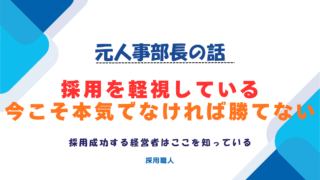
経営が採用を軽視する構造が“人手不足”をつくっている
「今どきは人がいないから、採用なんて無理だよ」
そう言う経営者の多くは、実は採用を“経営課題”として見ていない。
建設業における「人がいない問題」は、
人口減少のせいでも、求人媒体のせいでもなく──
経営の意思決定から採用が外れていることが最大の原因だ。
実際、私は元人事部長として200社以上の建設会社を見てきたが、
「社長が採用方針を語れない会社」に限って、いつまでも人が集まらない。
なぜか?
採用とは、経営の鏡だからだ。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
建設業の採用成功企業に共通する「経営者の関与率」
リクルートワークス研究所の「中小企業採用動向2024」によると、
経営者が採用戦略に関与している企業の割合は全体の34%。
ところが、採用成功企業の経営者関与率は72%に跳ね上がる。
つまり、採用が上手くいっている会社ほど、経営者が深く関わっている。
採用成功とは、単に応募が集まることではない。
「欲しい人材を、欲しいタイミングで採れる仕組み」をつくること。
それを実現するには、経営者自身が「どんな人を採るか」を定義し、
それを経営戦略と一体化させる必要がある。
参考:リクルートワークス研究所『中小企業の採用構造変化レポート2024』
https://www.works-i.com/research/
「現場任せ採用」が抱える4つの構造的リスク
経営者が採用を“現場任せ”にすると、
次のような構造的リスクが静かに積み重なる。
- 人材要件が曖昧になる
現場ごとに“理想像”が違い、求人内容がバラバラになる。 - 採用目的が短期化する
「今足りない」人を埋めることだけに意識が集中する。 - 定着率が下がる
会社としての“方向性”と入社動機が一致しない。 - 採用ノウハウが蓄積しない
担当者が変わるたびにゼロリセットされ、コストが膨らむ。
この結果、採用活動は「毎回一からやり直し」の繰り返しになる。
経営が採用を握らない限り、構造的な改善は起こらない。
現場の声を“経営判断”に変える──採用構造の再設計
採用を経営戦略に組み込むとは、「経営方針 × 人材方針」を接続すること。
私が支援した中で成功している企業は、必ず次の3ステップを踏んでいる。
1. 経営計画と採用要件をリンクさせる
3年後の施工量・受注計画を基に、必要人員・スキル・役割を定義する。
これが採用の“設計図”になる。
2. 採用活動を数字で管理する
応募数・通過率・定着率をすべて可視化。
採用を「感覚」ではなく「経営データ」として扱う。
3. 採用判断を経営者が下す
最終面接だけでなく、「人材像の定義」も経営者が担う。
ここを人事任せにすると、経営理念と採用軸がズレていく。
このプロセスが定着すれば、
“採用は現場の負担”から“経営の武器”へと変わる。
関連して、こちらの記事でも詳しく解説しています →
👉 「求人会社に任せても採用できない理由──建設業が自社でやるべきこと」
実例:経営者が採用を握った瞬間に変わった会社
私が人事部長としていた時、年200万円の広告費で応募は10人以下。
採用はせいぜい2〜3人。
この時、社長の一言が転機となった。
「採用を“経営会議”の議題にしよう」
そこから方針を全面的に見直した。
- 採用ターゲットを「20〜30代・未経験者可」に統一
- 採用目的を「即戦力確保」から「組織の継承・育成」へ転換
- 原稿・面接・評価基準を社長自らレビュー
結果、半年で応募200名、採用20名。
採用単価は約1/3に圧縮。施工量は2倍、売上は5倍に拡大した。
採用構造を「現場判断」から「経営判断」に戻しただけで、
会社全体の生産性が変わったのだ。
経営者が押さえるべき「採用構造の3原則」
採用を経営課題として扱うには、次の3原則を押さえることが重要だ。
- 理念に基づく採用基準を定める
「何をしている会社か」ではなく、「なぜこの会社なのか」を言語化。 - 採用データを経営KPIに組み込む
採用コスト・応募率・定着率を毎月確認し、経営指標として扱う。 - 採用方針を社内に共有する
全社員が「うちの採用方針は○○だ」と言える状態をつくる。
これを実行するだけで、採用活動の質は劇的に変わる。
採用を軽視する経営が招く“損失”の実態
労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、
中小企業が1人採用に失敗した場合の平均損失額は約142万円。
(採用費+教育費+離職による生産性損失を含む)
逆に言えば、採用方針を明確にするだけで、
この“見えない損失”を削減できる。
出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「人材定着・採用コスト調査2024」
https://www.jil.go.jp/
採用は「コスト」ではなく、「投資」である。
経営者がこの視点を持てるかどうかが、
“採れる会社”と“採れない会社”の分かれ目だ。
経営主導採用を実現する実践ステップ
ステップ①:採用方針を経営理念に落とし込む
「どんな人を採りたいか」ではなく、「なぜその人を採るのか」を明文化。
ステップ②:経営会議で採用KPIを共有する
応募数・通過率・定着率を毎月チェック。
採用を“数字で語れる”経営者になる。
ステップ③:現場との連携ルールをつくる
経営が“方向性”を示し、現場が“選定”する役割分担を設定。
ステップ④:採用ノウハウを社内資産化する
面接シート・評価基準・内定フローを標準化し、属人化を防ぐ。
このステップは、採用職人の採用支援サービス でも体系化している。
求人設計から応募導線の最適化までを一気通貫で支援し、
“経営主導の採用”を現実に落とし込む仕組みだ。
関連リソースと参考記事
採用構造の設計や経営視点での再構築に関心がある方は、以下の記事も参考になる。
- 「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
- 求人広告会社に頼ってもうまくいかない理由と“自社で採用を強くする方法”
- 採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
- 「採用に困らない会社」の裏にある“構造の違い”とは?
また、採用設計を深く学びたい方はこちらも →
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート〜“見るだけ・話すだけ”で育つ仕組みをつくる〜
採用を“経営の言葉”で語れる会社が強い
「採用方針を語る経営者」がいる会社には、人が集まる。
なぜなら、求職者は“会社の未来”を見に来ているからだ。
経営者が採用を語れない会社に、
「この会社の将来を一緒に創りたい」と思える人材は来ない。
採用は、経営の延長線上にある。
それを再確認した瞬間から、
“人がいない”ではなく“人が集まる会社”に変わる。
まとめ
- 採用がうまくいかないのは、人手不足ではなく「経営の軽視」
- 経営者が採用に関わると、方針・判断・定着が一気に整う
- 採用は現場の作業ではなく、経営の装置である
note販売ページ
建設業の採用戦略を“経営視点”で再設計する実践ノート(¥4,980〜¥20,000)
採用職人の採用支援サービス
現場採用のノウハウを体系化した『採用職人の採用支援サービス』では、
求人設計から応募導線の最適化までを一気通貫で支援しています。
御社の採用成功を実現する実務設計を、今すぐ体験してみませんか?
https://recruit-worker.com/
関連リンク