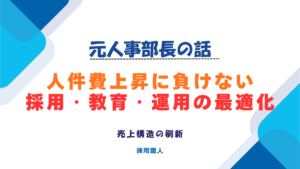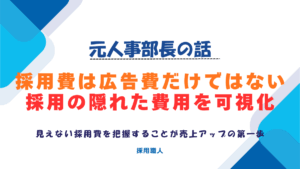【もう人は増やせない】中小建設会社が実践した「作業効率化×採用設計」で現場が変わる
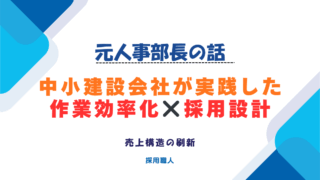
「人が足りないから、もうこれ以上は無理」──そう思った瞬間、成長は止まる
現場では毎日のようにこう聞きます。
「若い人が来ない」
「職人が辞めた」
「残業できないのに仕事は増える」
人手不足は確かに深刻です。
でも、**人を増やす前に“作業を軽くする仕組み”**を作れば、現場は驚くほど変わります。
私が人事部長として関わった会社では、
従業員数を変えずに施工量1.8倍・残業時間40%減を実現しました。
今回はその“現場効率化の仕組み化”を、実例と共に紹介します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
👉 YouTubeで動画を見る
① 🟧「作業効率化=最新技術の導入」
“ICT”や“BIM”だけが答えではない
「効率化」と聞くと、多くの経営者が思い浮かべるのはこうです。
- タブレット導入
- BIM活用
- ドローン撮影
確かに大企業では効果的ですが、
中小建設会社にとっては**“使いこなせる人”がいない**ことの方が問題。
本当の効率化とは、“道具”ではなく“流れ”を変えること。
つまり、「誰が」「いつ」「どの順で」動くかを明確にするだけで、
作業時間は確実に短縮できます。
② 🟧人手不足でも作業量は増やせる
“効率化”は現場の知恵と段取り力で決まる
生産性が高い会社の共通点は、
現場の流れが“見える化”されていること。
たとえば、1日の作業スケジュールが全員で共有されており、
「午前でこれ」「午後はここまで」と“到達点”が明確。
それだけで、
・確認ミスが減る
・待ち時間がなくなる
・連携がスムーズになる
結果、同じ人数でも1.5倍の仕事量をこなせるようになります。
③ 🟧作業効率化で施工量を1.8倍にした中小企業の話
「人を増やさずに現場を回す」仕組みを導入
ある地方の建設会社では、
職人不足で毎年現場が遅延していました。
私が関わったのは、“工程の再設計”と“教育の可視化”。
具体的には、
- 週単位の現場ミーティングで翌週の流れを統一
- 現場チェックリストを導入し、作業抜け漏れをゼロに
- 新人教育マニュアルを動画化し、教える負担を軽減
すると、
- 工期短縮率:平均12%
- 残業時間:月45時間 → 27時間
- 売上高:1.8倍
まさに、“人を増やさずに成果を上げた”成功例でした。
関連して、教育体制を整える実践法はこちら →
👉 入社後フォロー体制の整え方
④ 🟧中小企業でもできる「作業効率化の3ステップ」
“仕組みの見直し”で時間と人を生み出す
ステップ1:作業フローを“紙1枚”で見える化
現場ごとの段取りを、1日単位で整理。
「誰が」「何を」「いつまでに」を書き出すだけで、ムダな待ち時間が減ります。
ステップ2:教育を“属人化”から“共有化”へ
教える人によって教え方が違うと、作業スピードがバラバラ。
動画や写真で“標準作業”を見せると、全員の動きが整います。
ステップ3:報告を“簡略化”するルールを作る
1日3回の報告を1回にまとめる。
チャットや共有アプリで統一すれば、管理の時間も大幅に削減。
この仕組みを採用導線とセットで整える方法は →
👉 採用成功の具体ステップはこちら
⑤ 🟧効率化で“採用コスト”まで下がった理由
働きやすい現場が、人を呼び込む
作業効率化で残業が減り、社員満足度が上がると、
自然と「この会社働きやすい」と口コミが広がります。
結果、
- 応募数:2倍
- 採用単価:150万円 → 40万円
- 離職率:35% → 12%
効率化は“人を減らす手段”ではなく、“人を活かす環境づくり”。
人手不足の時代ほど、“人が辞めない現場”が最強の採用戦略です。
⑥ 🟧「人手不足を効率化で乗り切る」完全マニュアル
“時間を生む仕組み”が会社の未来を変える
この記事で紹介した「作業効率化マニュアル」は、
noteでテンプレート付きで公開しています。
内容:
- 作業フロー見える化シート
- 標準作業マニュアルテンプレ
- 教育・報告ルール設計図
- 成果が出た企業の事例集
価格は**¥20,000**。
1人分の残業20時間削減で、すぐに回収できる内容です。
「人が足りない」と嘆く前に、“仕組みで時間を生む”選択を。
⑦ 🟧「採用は“気合”ではなく“仕組み”」
人手不足の時代、“人を増やす”より“仕組みを整える”
建設業の人手不足は、今後も続きます。
でも、悲観する必要はありません。
“効率化”とは、機械化でもデジタル化でもなく、
「人が動きやすい流れ」を作ること。
採用職人の採用支援サービスでは、
求人設計から現場効率化の導線設計まで支援しています。
御社の「人を活かす仕組み」、一緒に作りませんか?