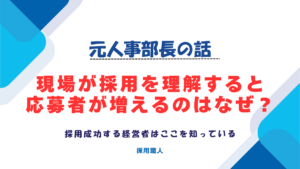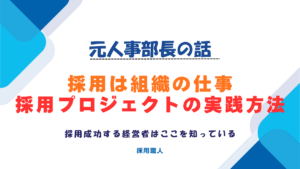採用がうまくいく会社の共通点は“現場が採用を楽しんでいる”ことだった
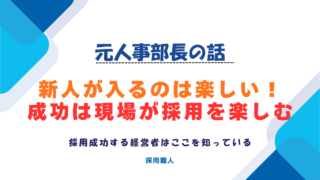
現場が「もう一人ほしい」と言える会社が強い
建設業の採用が難しい理由の一つは、“現場が採用をしたがらない”ことです。
「どうせすぐ辞める」「教育が大変」「仕事を増やすだけ」——そんな声を、私も人事時代に何度も聞きました。
けれど、ある会社では真逆の現象が起きていました。
現場の職長が自ら「うちに新人を入れてくれ」と言う。
結果、応募が増え、定着率も上がった。
なぜこの差が生まれるのか?
この記事では、現場が“人を採りたくなる会社”になるための条件を、人事と現場の両視点から紐解きます。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
現場の本音「人が増えると自分が大変になる」
「人を採る」ことは現場にとって、実は“仕事が増えること”でもあります。
新人が来れば教育が必要。指導すればミスも出る。
だから職長は無意識にこう考えるのです。
「正直、今のメンバーで回ってるし、余計な手間は増やしたくない」
人事が「採用しよう」と声をかけても、現場が乗ってこない。
これではどれだけ求人広告を出しても、定着はしません。
私も当時、この壁に何度もぶつかりました。
現場が“採用拒否”になっていた時期
ある年、私は人事部長として年間200万円の求人広告費を使いました。
応募は10件未満、採用ゼロ。
原因を探るため、現場ヒアリングを行いました。
すると、職長の一人がこう言いました。
「どうせすぐ辞めるんだから、採る意味ないじゃないですか」
その瞬間、気づいたんです。
現場にとって“採用はリスク”だった。
「人を増やす=負担が増える」という構造になっていたんです。
この“心理的コスト”を取り除かない限り、どんな求人改善も意味がない。
現場が「採用したくなる」には“誇り”と“余裕”が必要
現場が採用に前向きになるには、2つの条件があります。
条件①:誇りを感じられる現場であること
人は「自分の現場を見せたい」と思える場所で働きたい。
逆に「見られたくない現場」では誰も採用を支援しようとしません。
つまり、現場環境=採用意欲なのです。
条件②:教育の仕組みが整っていること
「教えるのが面倒」「時間が取れない」と感じる限り、現場は新人を歓迎できません。
教育の型や支援体制を整えることで、**“教える負担”を“育てる楽しさ”**に変えられます。
この2つが揃った瞬間、職長の口から「次はどんな人が入るんですか?」という言葉が出るようになります。
現場が“採用を楽しむ”仕組みを作る3ステップ
採用は、現場が関わった瞬間に強くなります。
ただし、それを仕組みとして定着させることがポイントです。
ステップ①:現場を「採用会議」に招く
月1回で構いません。
現場の声を共有し、採用の成果(応募数・面接数・入社者)を数字で見せる。
これだけで、現場は“自分たちも採用に関わっている”実感を持ちます。
ステップ②:職長に“採用教育”を実施
面接同席や教育テンプレートを共有し、採用を「現場スキル」として学ぶ。
これにより、採用=経営貢献の一部という意識が浸透します。
ステップ③:採用成功を“現場の成果”として評価
採用活動で成果を上げた現場には、報奨や表彰を設ける。
「採用もうまい職長」が社内で評価されると、採用は文化として根づきます。
関連して、現場採用の本質をまとめた記事も参考になります。
現場の空気が変わった瞬間、応募が2倍に
私が支援したB社(舗装業)は、最初は現場が完全に採用拒否。
「新人来ても3日で辞める」「教える時間がない」の一点張り。
そこで始めたのが、“職長が新人教育を設計する”プロジェクト。
指導マニュアルを作り、「これならやりやすい」と現場が納得。
さらに、採用ミーティングで成果を共有するようにしました。
結果、**半年で応募が2倍、1年後には定着率が85%→93%**に。
「採用がうまくいく会社=現場の雰囲気が明るい会社」なのです。
採用職人の支援:現場文化を“採用力”に変える
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
職長教育や現場巻き込み設計、導線構築までを一気通貫で支援しています。
現場を“採用の仲間”に変える仕組みを作ることで、
応募は自然に増え、教育コストも減る。
まさに“採用を楽しむ会社”を再現可能にします。
詳しい実例は以下のnoteで紹介しています。
👉 「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
採用は「現場が誇れる会社」から始まる
採用はテクニックではなく、文化です。
どんなに求人原稿を磨いても、現場が「新人を迎えたくない」と思っていれば、成果は出ません。
逆に、現場が「うちで働くのは悪くない」と思える職場なら、
その雰囲気が応募者に伝わります。
採用は“広告”ではなく、“空気”で決まる。
現場が採用を楽しめる会社——それが、人を採りたくなる会社の条件です。
そして、それはどんな中小企業でも作れる“仕組み”です。
📘 学びを深めたい方へ:noteで体系的に学ぶシリーズ