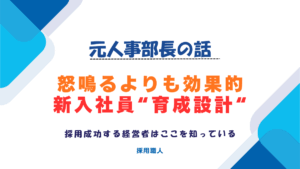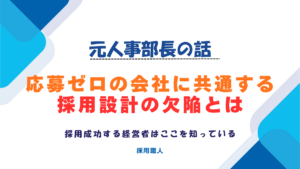「辞めない会社」は面接よりも“採用設計”で決まる。建設業の定着率を変える仕組み
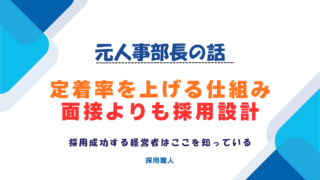
採用段階で“定着率”は決まっている
「せっかく採用しても、3か月で辞めてしまう…」
そんな声を、建設業の経営者からもう何十回聞いたかわかりません。
実は、辞める理由の8割は「採用段階の構造ミス」です。
面接の一言、求人の見せ方、初日の導線、すべてが“離職予備軍”を作ってしまう仕組みになっているのです。
この記事では、
現場人事として年間200万円の広告費を投じながらも採用0人だった私が、
採用設計を見直して「応募200人・採用20人・定着率90%」を実現したプロセスを公開します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
なぜ“辞める人”ばかりが集まるのか
建設業の離職率は全産業平均の約1.5倍。
厚労省のデータでは、**入社3年以内の離職率は約35%**にのぼります。
多くの会社が、「採用したのに続かない」「また1から育て直しだ」と嘆きますが、
それは“面接以降”の話ではありません。
問題はもっと手前──**採用段階の“入口構造”**にあります。
求人票に「アットホーム」「未経験歓迎」と書いても、
実際の現場が厳しく忙しければ、求職者は「話が違う」と感じて離れていく。
このズレこそが“離職の設計ミス”です。
ミスマッチを生む“採用構造の歪み”
建設業の多くは、求人広告会社のフォーマットに頼っています。
結果、求職者が「どんな仕事か」より「条件」だけで判断する原稿になりがちです。
たとえば、
- 「未経験歓迎」と書きながら実際は即戦力が必要
- 「残業少なめ」と言いながら繁忙期は夜10時まで
- 「手に職をつけたい人歓迎」と言いながら育成体制が曖昧
これらは“嘘”ではなくても、現場との温度差を生みます。
求職者は“理想”を、会社は“都合”を基準にしている。
だから、入社して3か月後に「聞いていた話と違う」となるのです。
この構造は「求人広告会社任せ」の弊害でもあります。
広告は“応募を増やす”ことが目的。
しかし、採用の本質は「辞めない人を選び、育てる」ことです。
(関連して、こちらの記事でも詳しく解説しています →
👉 採用成功の具体ステップはこちら)
現場とズレた“採用失敗”の代償
私が人事部長だった頃、年間200万円の求人費を使っても、採用はわずか2名。
しかも1年以内に全員退職。
面接での印象は良かったのに、現場に入ると「合わない」「想像と違った」と辞めていく。
当時、現場からはこう言われました。
「人事は人を選んでるつもりでも、現場を知らないじゃないか。」
その言葉がすべてでした。
そこで私は“採用の主導権”を現場に戻しました。
現場職長にヒアリングを行い、「辞めた人」と「続いている人」の共通点を分析。
すると驚くことに、スキルでも年齢でもなく、
「現場でのコミュニケーションの取り方」「自分の役割を理解しているか」が決定的に違っていた。
つまり、見極めるべきは“性格”よりも“仕事観”だったのです。
改善策①:求人の中に“リアル”を設計する
求人原稿は広告ではなく「フィルター」です。
“来てほしい人”だけでなく、“合わない人”を遠ざける役割を持たせる。
そのために私は、
- 現場の写真を正直に掲載(汚れていてOK)
- 1日の流れを時間で示す
- 「大変なこと」も隠さず書く
これだけで応募数は一時的に減りましたが、
面接後の辞退率が半分以下になり、定着率が90%を超えたのです。
求人の目的は“応募数”ではなく“応募の質”を上げること。
この考え方を変えた瞬間、すべてが変わりました。
👉 関連記事:「応募が来ない時代に、なぜあの会社だけ採用できるのか? 採用競争の勝ち方」
改善策②:面接を「見抜く場」から「見極め合う場」へ
面接では「採用するかどうか」を判断しがちですが、
本当に見るべきは“会社と本人の相性”です。
私は現場リーダーに面接同席を依頼し、
「どんなタイプの人と合うか」をリアルに話してもらいました。
求職者は「現場のリアル」を知り、
会社は「一緒に働けるか」を確認する。
この“相互確認”が、結果的に離職率を激減させました。
面接とは“相性の見極めプロセス”なのです。
(参考記事:面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計)
改善策③:入社後の“最初の3日間”を設計する
辞める人の6割は、入社3日以内に「違和感」を持っていると言われます。
だから、初日からの導線こそ最重要。
私が行ったのは以下の3つです:
- 初日に「一緒に昼飯」を現場全員で食べる
- 現場リーダーが1対1で“仕事の目的”を話す
- 初週は「覚える」より「慣れる」期間に設定
この“心理的安全の設計”だけで、離職率は大幅に下がりました。
採用とは、入社してから始まるのです。
採用設計を変えた結果
- 応募200名/採用20名(1年間)
- 定着率90%
- 採用単価 約40万円(以前の1/3)
採用費は減り、人は育ち、施工量は2倍・売上は5倍。
会社が安定したのは、「辞めない仕組み」を採用段階で作ったからです。
note導線:学びを体系化した実務ノウハウ
この記事で紹介した仕組みは、noteで体系化しています。
📘 「建設業の技術者採用、なぜうまくいかない?現場視点で解く“人が集まる条件”
📘 “採用しても辞める”建設会社が見落としている、人手不足の本当の理由
採用から定着までを「現場ベース」で再設計したい方は、
有料note(¥4,980〜¥20,000)で実践テンプレートをご覧ください。
実際に定着率を2倍にした設計書と面談シナリオを公開しています。
採用職人の採用支援サービス
現場採用のノウハウを体系化した
**採用職人の採用支援サービス**では、
求人設計から導線設計・面接教育までを一気通貫で支援。
御社の採用が「続く人を採る仕組み」に変わる体験を、今すぐ。
まとめ:「辞めない採用」は“設計”で作れる
結論、辞めない会社は「採用段階で仕組みを作っている」。
求人・面接・初期導線──その3つを設計すれば、
離職率は必ず下がります。
採用とは、採ることではなく「続ける人を見抜く」こと。
そしてそれは、気合でも予算でもなく、仕組みで再現できるのです。
✅ 関連note