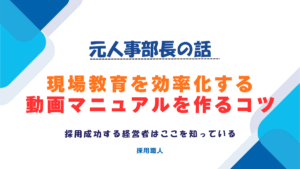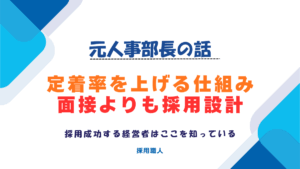現場で怒鳴るより、新人は設計で育てる。建設業が変わる“教育の仕組み”
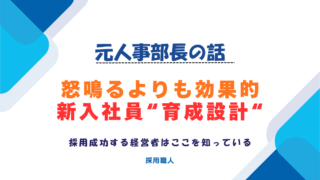
「怒鳴っても辞める、優しくしても育たない」現場が抱える教育のジレンマ
「最近の若い子は叱ると辞める。けど、放っておくと成長しない」
多くの現場監督から聞くこの言葉。実はこれ、“教え方”ではなく“仕組み”の問題です。
私は建設会社の人事部長として、教育現場の改善を10年以上見てきました。結論から言うと、「教育担当者の性格」ではなく「育成の設計」で現場は変わる」のです。
この記事では、怒らない・怒れない時代に合った「仕組みで育てる教育法」を、実際の成功事例を交えて解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
「怒らない教育」では人は定着しない
現場でよくある光景。
新人がミスをするたびに、ベテランが声を荒げる。怒られた新人は黙り込み、次第に距離を置く。
「怒らないようにしよう」と思っても、同じミスが続くとつい感情が出る。
──この繰り返しが、教育の空回りを生みます。
そもそも、「怒らない教育」という考え方は**“対症療法”**にすぎません。
根本の原因は、「何を・いつ・どのレベルまで教えるか」が決まっていないこと。
つまり、教育の設計図がないまま現場任せになっているのです。
教育設計を変えたことで“辞めない現場”に
私が人事部長だった頃、年間10人入社して半年後に半分が辞める状態でした。
面談で辞めた理由を聞くと、「怒られた」「何も教えてもらえなかった」「どうすれば評価されるか分からない」。
そこで始めたのがOJTの仕組み化です。
「先輩の感覚」ではなく、「段階ごとに教える内容を分ける」方式を導入。
たとえば、入社1ヶ月目は安全ルール、3ヶ月目で作業工程、6ヶ月目に図面理解…と、教える項目を一覧化しました。
結果、1年後の定着率は**45%→90%**に。
教育担当者も「何を教えるか迷わなくなった」と言い、教える側のストレスも減りました。
現場教育がうまくいかない3つの構造的ミス
- 教育のゴールが曖昧
→ 「見て覚えろ」「自分で考えろ」は、時代に合わない。 - 評価と連動していない
→ 教えた成果が評価されないから、先輩が育成に本気になれない。 - 教える人がバラバラ
→ 教育内容が属人化し、誰が育てても結果が違う。
これらはすべて、「教育を“感覚”でやっている」ことが原因。
だからこそ、仕組み化が必要なのです。
関連して、こちらの記事でも「採用から教育への流れ」を詳しく解説しています → 新人が定着しない原因と解決のヒントはこちら
仕組みで育てる3ステップ
ステップ①:教育フローを“見える化”する
新人教育を工程表のように分解し、誰が・いつ・何を教えるかを明文化。
「この表を見れば今どこにいるか分かる」状態をつくるだけで、迷いが減ります。
ステップ②:面談テンプレートを導入する
毎月1回のフォロー面談をルール化。
質問内容をテンプレート化すれば、上司が話すのが苦手でも会話が続く。
(→ 詳細テンプレートはこちら)
建設業専用 教育動画・面談テンプレート
ステップ③:育成成果を“評価”に反映する
「教えた人が損をしない仕組み」をつくる。
OJT指導者の評価項目に“育成貢献”を入れると、自然と現場全体の教え合い文化が生まれます。
教育仕組み化で変わった現場の空気
教育設計を取り入れたある中小建設会社では、
- 応募数:前年比2倍
- 定着率:半年で93%
- 教育担当者の満足度:4.6/5.0
「怒らなくても伝わる」「新人が質問してくるようになった」──
現場の空気が“ピリピリ”から“前向き”に変わりました。
さらに詳しい教育設計法は → 建設業の技術者採用、なぜうまくいかない?
「感情」ではなく「構造」で人を育てる
教育は「我慢」ではなく「設計」です。
怒らないよう努力するより、怒らなくても回る仕組みを作る。
そのほうが、現場にも新人にも優しい。
もし今、「若手が続かない」「育たない」と感じているなら、
まず見直すべきは“人”ではなく“仕組み”です。
「仕組みで育てる教育法」を体系化した教材はこちら:
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート
現場採用と教育を一貫して改善したい方はこちらも参考に:
👉 採用職人の採用支援サービス
仕組みが変われば、人は変わる
「教えるのがうまい人」ではなく、「教えやすい環境」をつくる。
それが、“怒らない教育”から“仕組みで育てる教育”への転換点です。
✅ 関連記事: