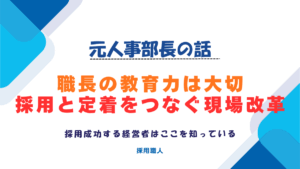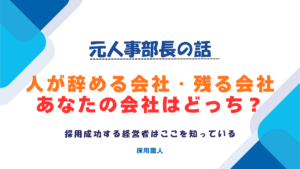職長が“叱らなくてよくなる現場”をつくる。建設業の教育と採用を変える方法
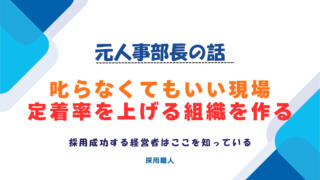
厳しく叱る=現場をまとめる、ではない
「最近の若手は怒られるとすぐ辞める。昔は違ったのになあ」
そう話す経営者に、私はいつもこう返します。
「それ、昔の現場が優しかったわけではなく、“意味のある叱り方”ができていたんですよ」と。
今の現場で問題なのは、叱ることそのものではなく、叱る“設計”がないことです。
叱る基準が人によって違い、職長ごとの温度差が大きい。
結果、「怒られた」「否定された」と受け取る新人が増え、離職率が上がっていく。
私が関わった会社では、職長によって“声のボリューム”が違うだけで、
新人の定着率が30%も差が出ていました。
叱るより“伝える”ことが組織を強くする
叱る=指導ではありません。
指導とは、相手が理解できる形で「伝わる」こと。
言葉を投げるのではなく、“届くように設計する”。
これができていない現場は、どれだけ教育しても育たない。
たとえば、
- 「なんでできないんだ!」 → 相手の思考を止める
- 「どこでつまずいた?」 → 相手の思考を動かす
同じ場面でも、伝え方で結果が変わる。
これを“教育コミュニケーション”と呼び、
多くの建設会社がまだ体系化できていない部分です。
言葉を変えた職長が現場を変えた
私が支援した建築会社では、毎朝のミーティングが“怒声の場”になっていました。
現場の空気は重く、新人は3ヶ月もたずに辞めていく。
そこで、職長向けに「叱らない伝え方ミーティング」を導入。
ルールはたった3つ。
- 指摘ではなく“観察”を口にする
- 感情ではなく“行動”を指摘する
- 1日1回、“できた点”を伝える
最初は戸惑っていた職長も、3週間後には「新人の顔が変わった」と口を揃えました。
半年後、離職率は47%→12%に改善。
さらに「自分も教えるのが楽しくなった」という声が増えたのです。
この内容は、こちらの記事でも詳しく解説しています →
新人が定着しない原因と解決のヒント
現場に“伝える仕組み”を組み込む3ステップ
怒らない文化をつくるには、精神論ではなく仕組みが必要です。
次の3つを意識して設計してください。
ステップ①:職長教育を「コミュニケーション研修」に変える
技能だけでなく、“伝え方”を学ぶ場を職長会議に組み込む。
叱り方の統一こそ、現場の一体感を生みます。
ステップ②:新人の声を「フィードバックシート」で可視化
匿名で「教えられ方の感想」を毎月収集。
数字ではなく“感情の変化”を管理します。
ステップ③:“言葉のマニュアル”を共有する
「注意の言葉」や「励ましのフレーズ」をテンプレ化。
言葉の使い方を属人化させないことが定着率を安定させる鍵です。
関連テーマはこちら →
若手が辞めない現場をつくるための実践ポイント
現場教育と採用をつなげる“文化設計”の重要性
「採用」と「教育」は別物ではありません。
現場での伝え方こそ、会社の“採用文化”を形づくる要素です。
新人が「この職長と働きたい」と思う現場ほど、
採用も安定し、口コミで応募が増えていく。
つまり、教育改革は採用改革でもある。
現場が“伝える仕組み”を持てば、
採用・教育・定着の三位一体構造が完成します。
この考え方は、note記事
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート
でも実践形式で紹介しています。
伝える仕組みを導入した会社の変化
某電気工事会社では、「伝える仕組み」を半年導入した結果──
- 新人の3ヶ月離職:38% → 9%
- 教育にかかる時間:1/2に短縮
- 職長の満足度:自信が“ある”と答えた割合 23% → 81%
と大幅に改善しました。
“叱る文化”から“伝える文化”へ切り替えた瞬間、
現場全体の空気が軽くなり、チームの雰囲気まで変わったのです。
まとめ:言葉を仕組みに変えることが現場改革の第一歩
強い現場とは、“怖い現場”ではなく“伝わる現場”。
職長が怒鳴らなくても育つ環境をつくることが、
次世代の建設業に求められています。
教育は“気合”ではなく“設計”。
そして、叱る力ではなく伝える仕組みが現場を育てます。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
この「伝える仕組み」を現場に落とし込むサポートを実施しています。
求人設計から教育導線の設計まで、御社に合わせた実務支援をご提案しています。
さらに、詳しい実践テンプレートはこちらから:
👉 現場が育つ教育と面談テンプレート