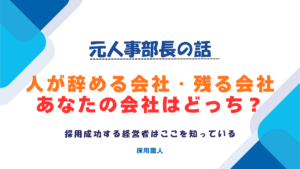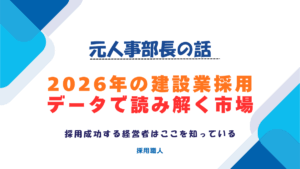定着率が高い会社に共通する“現場の見えない構造”。人が育つ環境のつくり方
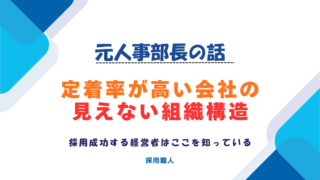
建設業の離職率は、平均で31.7%
国交省のデータによると、建設業の3年以内離職率は約31.7%。
一方で、同じ業種でも「離職率10%未満」の会社も確実に存在します。
この差を生み出すのは、待遇でも制度でもなく、現場の日常の空気。
どれだけ採用に成功しても、
「現場が人を育てる構造」を持たない会社は、
結局“入れては辞める”を繰り返します。
私はこれまで50社以上の採用・定着支援を行ってきましたが、
定着率が高い会社ほど、教育を“仕組み”で設計している。
逆に、離職が止まらない会社は「教える人任せ」「その場対応」になっていました。
離職率を左右するのは“初期3ヶ月”の関係性
ある支援先の建設会社で、職長の育成法を変えた結果、
3ヶ月以内離職率が42%→13%に改善。
変えたのは教育マニュアルでも研修でもなく、「職長の言葉の使い方」です。
新人への最初の3ヶ月で、
- 「質問できる空気」があるか
- 「ミスを笑われない」雰囲気があるか
- 「できた瞬間」を見逃さない職長がいるか
この3つを整えるだけで、数字は劇的に変わる。
つまり、“育つ現場”とは、心理的安全性を仕組みとして持つ現場なのです。
“辞める現場”は、制度よりも文化が壊れている
多くの経営者は「給与を上げよう」「休日を増やそう」と考えます。
もちろんそれも必要。
しかし、現場の離職原因を追うと、約6割が“人間関係”です。
つまり、辞める現場の問題は「人の関係を整える仕組み」がないこと。
職長の口癖が「なんでできねえんだ」になっている現場は、
新人が「助けを求める前に諦める」空気をつくってしまう。
一方、“育つ現場”では、職長が「一緒にやってみようか」と声をかける。
このわずかな言葉の差が、離職率30%の差になるのです。
育つ現場をつくるための“教育設計3ステップ”
現場を変えるには、感情論ではなく設計論が必要です。
以下の3つを整えるだけで、現場の文化が変わり始めます。
ステップ①:職長教育を「管理」ではなく「育成指導」に再設計
職長会議を“工程報告の場”ではなく、“人材育成の共有会”に変える。
「新人がどう変わったか」を話題にする時間を必ず設ける。
ステップ②:教育の“見える化”を進める
新人ごとに「教えた内容」「できたこと」を記録するシートを導入。
誰が教えても同じクオリティで育つ仕組みをつくる。
ステップ③:定期フィードバックの“型”を共有
「観察→共感→提案」の3ステップで話す仕組みを職長間で統一。
伝え方の統一が、定着率向上の最短ルートです。
関連して、こちらの記事もご覧ください →
新人が定着しない原因と解決のヒント
“育つ現場”は採用を強くする
人が辞めない会社は、採用でも有利になります。
なぜなら、“現場の口コミ”が最大の採用媒体になるからです。
「うちの現場はやりやすいですよ」
――この一言が、どんな求人広告よりも信頼される。
現場文化を整えることは、採用を強くする投資でもあるのです。
採用と教育を一体で改善したい方はこちら →
採用と教育を一貫設計する仕組みづくり
定着率が90%を超えた会社
ある設備会社では、職長教育と教育記録シートを導入した結果、
- 3ヶ月離職率:45% → 8%
- 1年定着率:62% → 91%
- 採用単価:140万円 → 38万円
現場リーダーが“育成者”に変わると、
新人の表情が変わり、定着率も利益率も上がる。
これが「人が育つ現場」の本当の姿です。
まとめ:辞める現場を変えるのは、“仕組み”と“関係性”
採用にいくら投資しても、育つ現場がなければ意味がありません。
人が残る会社は、職長が“伝える文化”を持っている。
それは偶然ではなく、設計された結果です。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
採用から教育まで一気通貫で整える“現場定着設計”を支援しています。
御社の現場を「育つ環境」に変える第一歩を、一緒に踏み出しませんか?
さらに詳しい教育設計の仕組みはこちら →
👉 建設業専用 教育動画・面談テンプレート