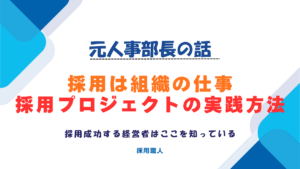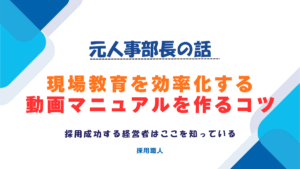「採用は人事の仕事」だと思っている限り、人は来ない。建設業の本質的改革
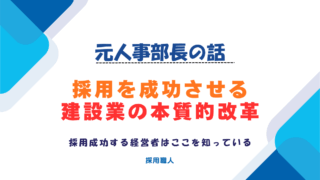
採用が“人事部の仕事”になった瞬間、会社は弱くなる
「採用は人事がやるものだろ」そう言う社長の会社ほど、現場が疲弊しています。
広告は出している。説明会もやっている。けれど人は集まらない。
それもそのはず。
採用とは、“一部署の活動”ではなく、“会社全体のプロジェクト”だからです。
建設業の採用成功企業を見れば一目瞭然。
現場が面接に立ち会い、職長が教育に関わり、経営が採用方針を語る。
採用が会社の文化として根づいているのです。
本記事では、私が元人事部長として体験した「人事任せ採用の限界」と、
“現場と組織をつなぐ採用体制”の作り方をお伝えします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
採用は“人事だけで完結する仕事”
多くの会社では、採用と聞くと「人事部の担当業務」と捉えられています。
しかし、それが採用がうまくいかない根本原因です。
求人を出すのも人事、応募者対応も人事、面接も人事——。
現場は「誰が来るか知らないまま」受け入れる。
結果、「思っていた人と違う」「すぐ辞めた」という不満が残ります。
皮肉なことに、人事が頑張れば頑張るほど、
現場との温度差が広がっていくのです。
採用は“組織全体で動かすプロジェクト”である
採用は、単なる募集活動ではありません。
それは、経営・人事・現場が連携して進める組織改革の一部です。
私が支援した建設会社の中で採用に成功した企業は、例外なく次の特徴を持っています。
- 経営者が採用の旗を振っている
「人を増やすこと=会社を成長させること」と明言している。 - 現場が採用に関わっている
職長が面接に同席し、求人原稿の内容に意見を出す。 - 人事が“調整役”として機能している
現場と経営をつなぎ、採用をプロジェクトとして管理。
つまり、人事は“採用を動かす人”ではなく、“採用をつなぐ人”なのです。
人事任せをやめた瞬間、採用が回り出した会社
私が関わった中堅建設会社(従業員60名)では、
以前まで採用は完全に人事任せでした。
年間200万円の広告費で応募10人、採用1人。
そこで、組織体制を次のように変えました。
- 人事+現場+経営の3者による「採用チーム」を発足
- 職長が求人原稿チェックと面接同席を担当
- 面接後のフィードバックをチームで共有
結果、半年で応募数が3倍、採用数は6人に増加。
さらに、入社1年後の定着率が**62%→88%**へ改善。
「採用って、人事の仕事だと思ってたけど…」
——現場の職長がそう言った時、会社の採用文化は変わり始めたのです。
👉 関連記事:現場採用の本質をまとめた記事はこちら
採用を“チームで動かす”3つのステップ
採用を組織全体で動かすためには、体制そのものを設計し直す必要があります。
ここでは、どの会社でも実践できる3つのステップを紹介します。
ステップ①:採用の「責任範囲」を明確にする
人事は管理、現場は受け入れ、経営は方針。
それぞれの役割を決め、**「採用は全員の仕事」**と明言することから始めます。
ステップ②:採用会議を“定例化”する
月1回で十分です。応募数・面接数・定着率をチームで共有。
“数字で採用を語る”習慣をつけると、全員の意識が変わります。
ステップ③:現場教育を“採用プロセス”に組み込む
新人教育は採用の延長です。
教育担当を決め、採用→育成→定着を一気通貫で管理しましょう。
採用職人の支援:採用を“文化”として根づかせる設計
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
「採用=チーム戦」として動かすための組織設計を支援しています。
- 採用チーム設計マニュアル
- 職長教育・面接スクリプト
- 応募導線の仕組み構築
導入企業では、採用単価40万円以下・応募数2.5倍を達成。
特別な広告やSNS拡散に頼らず、“社内の構造”で人が集まる仕組みを再現しています。
関連note:「求人広告会社任せにしない仕組み構築法」
現場視点で見る:なぜ“人事だけ採用”は続かないのか
現場から見れば、人事がどれだけ頑張っても「知らない人が入ってくる」。
だから、責任を感じにくい。
一方、人事からすれば「せっかく採ったのに、すぐ辞めた」。
この構造を放置していては、採用はいつまで経っても“点”で終わります。
採用を“線”でつなぐには、現場と経営が関与する「流れの設計」が必要なのです。
👉 関連記事:採用成功の構造を変える方法はこちら
まとめ:採用は“部門の仕事”ではなく“文化”である
採用が会社の文化として根づいたとき、
現場が新人を迎え、経営が語り、人事が支える。
採用は「誰がやるか」ではなく、「全員でやるか」。
この構造を作れた会社が、最終的に人材に困らない会社になります。
だからこそ、今こそ考えるべきなのです。
「採用を誰がやるか」ではなく——
**「採用をどうやって全員で動かすか」**を。
採用は気合でも予算でもなく、仕組みと文化で強くなる。
📘 学びを深めたい方へ:noteで体系的に学ぶ採用シリーズ