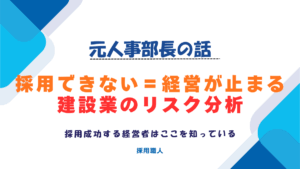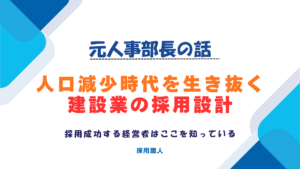数字が語る「採用難の正体」人手不足の裏にある“設計の歪み”を直せ
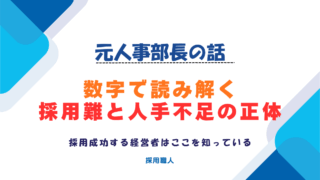
“人がいない”ではなく“仕組みがない”採用難の真実を数字で読む
最近、「もう人がいない」「応募がゼロ」「どの会社も同じ」とため息をつく経営者が増えています。
しかし、私は元・建設会社の人事部長として断言できます。「人手不足」は現象であって、原因ではありません。
求人広告に年間200万円をかけても応募が10人以下だった当時。
データを読み解き、採用の“構造そのもの”を組み替えた結果、応募200人・採用20人を実現しました。
この記事では、「採用難=人手不足」という思い込みを壊し、データで裏づける“構造的な課題”を明らかにします。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
“人手不足倒産”は過去最多、でも全社が苦戦しているわけではない
帝国データバンクの統計によると、2024年の「人手不足倒産」は前年比32%増で過去最多を更新しました。
一見、建設業もその波を受けて「採用が厳しい」と感じがちです。
しかし、同じ地域・同じ職種・同じ給与帯でも、応募が集まる会社と集まらない会社が明確に分かれています。
この差は「運」でも「景気」でもなく、採用の構造の違いです。
求人倍率を見れば、建設業全体では3倍前後。つまり、求職者1人を3社で取り合う構図。
にもかかわらず、一部の企業は応募ゼロ、他社は月に20件以上の応募。
この現象を説明するのは、「人手不足」ではなく「仕組みの偏り」です。
“採用難”の真因はどこにある?3つの統計が示す構造変化
1. 若手層の人口減少よりも「就業構造の変化」
総務省の労働力調査によると、15〜34歳の若年層は過去10年で約15%減少。
ただし注目すべきは、「建設業への流入率」が低下していること。
全体の若者数が減る以上に、“業界の選ばれにくさ”が顕在化しています。
2. “働き方選好”のシフト
内閣府の調査では、20代男性の約65%が「安定・成長よりも自由・環境重視」。
給与よりも「自分の時間」「人間関係」「体の負担」を重視する傾向が顕著。
つまり、求人原稿で「頑張れば稼げる」「やる気次第で昇給」だけを訴えても、届かない時代です。
3. “採用導線”の分断
求人を出す→応募を待つ→面接する、という流れ自体が時代遅れ。
応募者は「企業を調べる→比較→辞退」という“離脱導線”を経ています。
つまり、“応募数”ではなく、“途中で離脱している数”を可視化できていないことが採用難の根本です。
「採用難=広告が効かない」ではなく「設計が噛み合っていない」
多くの会社では、応募数が減ると媒体の切り替えや予算の追加を検討します。
しかし、現実にはそれで成果が出ないケースが大半。
なぜか?——“採用構造”のどこかがズレているからです。
たとえば、
- 求人文が「会社が求める人」にしか向いていない
- 面接までの連絡が遅く、応募者が冷めて離脱
- 現場の雰囲気が伝わらず、「入社後のイメージ」が湧かない
これらは全て、“仕組み”の欠陥です。
「うちは人が来ない」ではなく、「人が来たくなる構造を作っていない」のです。
(採用構造を立て直す方法は → 「求人会社に任せても採用できない理由──自社でやるべきこと」)
求人広告200万円→応募10名→採用ゼロからの再設計
私の前職の建設会社でも、典型的な“人手不足思考”に陥っていました。
「どこも採れないから仕方ない」と言い続け、2年間で採用ゼロ。
そこで私がやったのは、「広告の出し方」ではなく、「採用の設計」をやり直すこと。
- 現場社員3名にヒアリング:「どんな人が入れば助かるか?」
- 原稿の構成を変更:「求める人物像」より「1日の流れ」を前面に
- 応募後24時間以内の連絡ルールを設定
- 面談テンプレートを作成(安全→仕事内容→成長→評価の順)
結果、応募200名・採用20名。応募単価は3万円以下に。
広告会社は驚きましたが、変えたのは「文章」ではなく「構造」でした。
この実例をより詳しく解説した記事:
→ 「応募が来ない会社」がやっている致命的な3つの間違い
(関連記事 → 新人が定着しない原因は?現場でよくある課題と解決のヒント)
【改善策】“構造”を整える3つのステップ
ステップ1:求人設計の「視点」を変える
- 求人は「誰を採るか」ではなく「誰に選ばれるか」で設計する
- 1日の流れ・人間関係・成長ステップをビジュアル化
- 「未経験でも続けられる根拠」を写真と数字で提示
ステップ2:応募導線の“速度”を管理する
- 応募から24時間以内に初回連絡
- 48時間以内に面談確定、72時間以内に現場見学
- “即レス”こそ最大の信頼構築
ステップ3:現場と連携した“教育の仕組み”を整える
- 面談テンプレート+教育動画で統一化
- 職長が「伝える負担」を減らす
- “教育が整っている会社”は、応募率も定着率も上がる
関連note:
(さらに詳しい現場設計はこちら → 建設業の若手採用を底上げする5つの視点)
【信頼と実績】“人が集まる会社”は、設計で勝っている
数字で見れば一目瞭然です。
- 広告費を年間200万円→60万円へ削減
- 応募数10件→200件
- 採用単価150万円→40万円以下
- 定着率半年以内離職率を半減
つまり、「人手不足」を嘆く前に、“採用のPDCA”を回しているか。
仕組みで採用を制した会社は、景気や人口に左右されません。
(参考: 「採用で苦戦する会社」が必ずやっていない3つのこと)
【まとめ】「採用難」とは“構造の警告”である
人手不足は事実。
しかし、それを理由に止まる会社と、構造を変えて動く会社の差は年々拡大しています。
2025年以降、採用の主戦場は「広告」ではなく「設計」と「導線」に移ります。
採用は“気合でも予算でもなく、仕組み”。
もし御社が「人が来ない」と感じているなら、
それは「構造が時代に合っていない」だけかもしれません。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
求人設計・導線改善・面談テンプレ・教育仕組みを現場に合わせて設計します。
“採用が止まらない構造”を、御社にも。
(関連記事: 「求人広告会社任せをやめると採用費は1/3になる」)