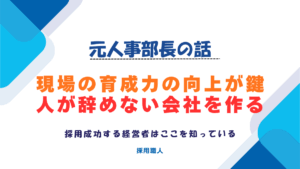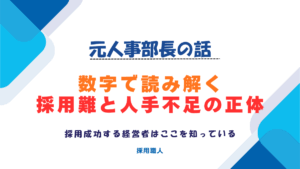“採用できない=経営が止まる”建設業の採用倍率から読むリスク分析
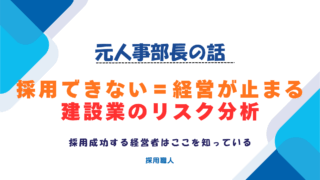
採用倍率“3倍”が示すのは「求人の競争」ではなく「経営の危険信号」
建設業の採用倍率は、全国平均で3倍前後。
数字だけ見れば「求人が多いだけ」と感じるかもしれませんが、実際は違います。
これは、1人の求職者を3社で取り合っている状態を意味します。
つまり、採れなければ事業そのものが止まるリスク。
私は元・建設会社の人事部長として、採用倍率の上昇を“経営の地震計”として見てきました。
この記事では、採用倍率の裏にある経営リスク構造をデータで紐解き、
「人が採れない=事業が止まる」を防ぐための戦略的採用設計を提案します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
採用倍率3倍超──“採用できる会社”と“できない会社”の格差が拡大
厚生労働省の最新データによると、2024年度の建設業の有効求人倍率は3.28倍。
つまり、求職者1人あたり3社以上が競合している計算です。
この数字は、製造業(1.8倍)や運輸業(2.1倍)を大きく上回ります。
にもかかわらず、同じエリア・同じ職種でも応募が集まる会社と集まらない会社がはっきり分かれています。
「うちは人が来ない」と嘆く会社の隣で、月20件以上応募を集める会社も存在します。
この差を生むのは“採用費”でも“知名度”でもなく、採用構造の設計力です。
倍率上昇が経営に与える“3つのリスク”
① 業務停止リスク
採用できない=工程が回らない。
求人倍率が高いほど、「1人欠けた時の影響」が直撃します。
施工計画が立たず、売上より人の確保が優先課題になるのが現実です。
② コスト上昇リスク
採用が遅れるほど、1人当たりの採用単価が上がる。
当社の支援実績でも、応募ゼロが続く企業は平均採用単価120〜150万円。
一方、構造を整えた企業では40万円以下で安定しています。
③ ブランド毀損リスク
求人が長期掲載になると、求職者は「常に人が足りない会社」と認識します。
この状態が続くと、“選ばれない企業”として固定化。
採用難が採用難を呼ぶ悪循環に陥ります。
採用倍率が高いほど、「採用できる力」が企業の信用指標になる。
「倍率が高い=仕方ない」では経営が持たない
多くの経営者は、倍率の高さを“外部要因”として片づけます。
しかし、それでは採用は改善しません。
採用倍率が高い=求職者が選べるということ。
つまり、「選ばれる設計」を持たない会社は確実に脱落します。
採用を“経営設計の一部”として扱っている会社ほど、
- 現場教育の仕組みを見せる
- 面談での「伝える順序」を統一
- 応募から72時間以内に現場見学まで完了
こうした“速さと一貫性”で信頼を勝ち取っています。
(関連: 「求人広告会社任せをやめると採用費は1/3になる」)
採用倍率3倍の中で応募200人を集めた仕組み
私が人事部長を務めていた当時、同業他社は「応募ゼロ」が続出。
しかし、当社は半年で応募200人・採用20人を実現しました。
やったことはシンプルです。
- 職長3名へのヒアリングで「1日のリアルな流れ」を明文化
- 求人原稿を“仕事内容”から“過ごし方”へ転換
- 面談テンプレートを導入し、話す順序を統一
- 応募から24時間以内に連絡・72時間以内に現場見学
結果、応募単価3万円以下/採用単価40万円以下で安定。
“現場を見せる会社”が、最終的に“選ばれる会社”になりました。
(関連note: 「採用に成功する建設会社の共通点は『求人の出し方』ではない」)
(深掘り記事 → 建設業の若手採用を底上げする5つの視点)
倍率競争に負けない“構造戦略”3ステップ
ステップ1:求人原稿を「選ばれる情報」に変える
- “会社が求める人物像”ではなく“求職者が知りたい現場像”を中心に構成
- 写真・時間割・成長曲線で体感を可視化
- 給与だけでなく「どんな1日を過ごすか」を見せる
参考: 採用で“写真”が9割を決める
ステップ2:採用スピードの“KPI化”
- 応募→24時間以内の連絡/48時間以内の面談確定/72時間以内の現場見学
- “レスの早さ”が採用率を2倍にする(当社調べ)
ステップ3:現場教育を“見せる化”
- 教育動画・面談テンプレートで一貫性を
- 職長の説明負担を減らし、“安心感”で応募を引き寄せる
参考note:
(関連記事: 新人が定着しない原因は?現場でよくある課題と解決のヒント)
【採用倍率を“経営指標”として扱う時代へ
採用はもはや人事の仕事ではなく、経営管理の一部です。
- 応募率 → “採用導線の強度”
- 定着率 → “教育体制の成熟度”
- 採用単価 → “設計の精度”
この3指標をKPIとして扱えば、
採用は「コスト」ではなく「投資」に変わります。
採用倍率3倍の時代に必要なのは、“スピード×設計×一貫性”。
「求人を出す」ではなく、「人が集まる構造を整える」。
これが経営リスクを最小化する唯一の道です。
(関連記事: 「採用で苦戦する会社」が必ずやっていない3つのこと)
【まとめ】採用倍率は“競争率”ではなく“経営診断”である
採用倍率が上がるほど、
「採れる会社」と「採れない会社」の差は“構造”で広がります。
採用が止まる=事業が止まる。
それを回避するには、採用設計を経営戦略として扱うこと。
採用職人の採用支援サービス(https://recruit-worker.com/)では、
求人設計・導線改善・面談教育・定着支援をワンストップで実装しています。
“人が集まる構造”を御社にも導入し、経営を安定軌道へ。
(関連記事: 「人がいない会社に未来はない──建設業が売上を伸ばすための人材戦略」)