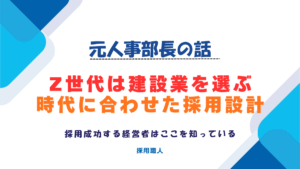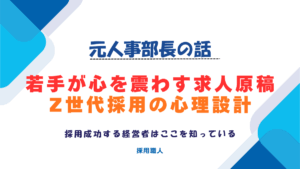離職率が上がる今、採用は「残す設計」より「選ばれる設計」に変える
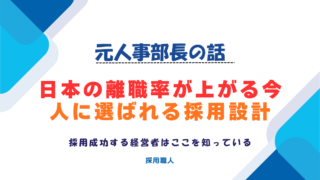
「人が辞める」のは時代のせい──では会社はどう設計すべきか?
“辞めやすい時代”になりました。
悪いことのように聞こえますが、実はそれが「新しい採用の前提条件」です。
若手が辞める、ベテランが抜ける、次が育たない。
そんな中で「どうすれば残ってもらえるか」ばかりを考えると、
採用は守りになり、会社は疲弊します。
いま必要なのは、「辞めても採用が回る構造」を作ること。
それが“辞めやすい時代”の採用設計です。
この記事では、離職率の高い時代における「攻めの採用構造」の作り方を、
データと実例を交えて解説します。
採用職人は建設業に特化した中小企業様向けに採用支援サービスを提供しています。
採用でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。御社の成長を加速させる機会を。
日本の離職率は上がっている
厚労省の最新データによると、
建設業の3年以内離職率は約36%。
10年前に比べて10ポイント以上上昇しています。
つまり、3人採っても1人は確実に辞める時代。
しかも辞めるスピードも早まっています。
以前は「1年は様子を見る」だったのが、
今は「3ヶ月で見切る」が当たり前。
この“流動化の加速”を前提にしない採用は、
いくら採っても穴が空くバケツと同じです。
なぜ「辞めやすい時代」になったのか
Z世代の仕事観を調査したリクルートワークス研究所のデータによると、
20代の約6割が「1社でキャリアを完結させるつもりはない」と回答。
さらに、退職理由の上位は「人間関係」「成長実感の欠如」「環境のミスマッチ」。
つまり“我慢”よりも“選択”が主流になった。
これは彼らが“転職しやすい社会構造”の中で育ったことが大きい。
SNSでは他業界の情報が簡単に手に入り、
副業やオンラインスクールで別の道も見える。
「辞めやすい時代」とは、“他の選択肢が常に見える時代”なのです。
「定着率を上げる」発想の限界
多くの会社が「辞めない人を採ろう」とします。
でもそれは、もう構造的に不可能です。
なぜなら、今の若手は“会社に合うか”を入社後に判断するから。
採用段階では、企業も応募者も“仮交際”のような関係なんです。
「面接で人柄を見抜こう」と頑張るより、
“辞めても困らない設計”を先に作る方が合理的です。
私はこれを「定着前提の採用」から「循環前提の採用」へのシフトと呼んでいます。
改善策①:採用導線を“常時稼働型”にする
昔の採用は「人が辞めたら募集する」でした。
でも今は、「常に採れる仕組み」を持つ会社が強い。
求人広告を出しっぱなしにするのではなく、
採用導線を整備して“いつでもエントリー可能”にしておく。
ポイントは2つ。
1️⃣ 求人ページを「採用サイト化」する
2️⃣ 応募がなくても「認知」を続ける
「求人がない時期」こそ、会社の存在を見せるタイミングです。
これが、辞めても回る採用構造の第一歩です。
(関連記事 → 建設業の社長が知らない「求人広告会社の営業マン」が絶対に教えない真実)
改善策②:面接を“教育の入口”に変える
「採用=合否判定」ではなく、「育成のスタートライン」に。
これが辞めやすい時代の採用設計の核心です。
たとえば私が支援したB社では、
面接の最後に必ず「仕事体験の見学日」を設定。
入社前に“体験”を通して現場のリアルを共有しました。
結果、3ヶ月以内離職が半減。
辞める前に「自分には合わない」と判断できたからです。
つまり“見極め”を早くするほど、会社のダメージも小さくなる。
面接は「絞り込み」ではなく、「相互理解の場」なのです。
関連記事 →
👉 面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計
改善策③:「辞めても戻れる文化」を設計する
辞めやすい時代に必要なのは、“戻りやすい関係”です。
「辞めた社員=裏切り者」という空気をなくす。
「また戻ってこいよ」と言える文化を持つ。
実際、私が支援したC社では“出戻り制度”を導入。
3年で7名が復職し、即戦力として現場復帰。
再雇用率の向上で、結果的に採用コストも20%削減しました。
この柔軟さが、Z世代には何より響きます。
改善策④:“辞めやすさ”を逆手に取る採用戦略
採用面接であえてこう言う会社があります。
「うちは合わないと思ったらすぐ辞めていいよ。でも、やる気があるなら全力で育てる。」
──これが刺さるんです。
なぜなら、Z世代は“選択の自由”を尊重してくれる会社に信頼を感じる。
強制よりも共感を重んじる時代だからこそ、
“辞めてもいい”と認めることで、“辞めたくない”が生まれる。
これは逆説的ですが、現場では実際に効果を出しています。
関連記事 →
👉 「若者がすぐ辞める」のではなく「辞めやすくしている」のは会社側だ
離職率45%→18%に改善した採用構造改革
私が関わったD社では、3年間で離職率を45%→18%に改善。
やったことは3つだけ。
1️⃣ 面接体験制度を導入
2️⃣ 現場教育動画を整備
3️⃣ 採用データを蓄積して改善PDCAを回す
結果、年間採用単価は150万円→42万円まで削減。
応募数は4倍。定着率も安定。
「仕組みで人を残す」ことの効果は、数字が証明しています。
関連して、現場教育設計についてはこちら →
👉 教育の仕組み化で“辞めない現場”を作る方法
“定着を強制しない”採用が主流になる
これからの採用は、「入社」よりも「再会」が価値になる。
つまり、“関係性の継続”が採用力になる時代です。
辞めてもまた戻れる、他社に行っても関係が続く。
そんな柔らかい採用文化を持つ会社ほど、長期的に強くなる。
そしてこの発想の転換こそが、
“辞めやすい時代”を生き抜く経営のアップデートです。
採用職人の採用支援サービス
「辞めやすい時代」に対応する採用設計を、
求人設計・面接導線・教育まで一気通貫で支援します。
詳細はこちら → 採用職人の採用支援サービス
まとめ:人は変わらない、時代が変わっただけ
“辞めやすい”のは悪ではなく、自然な時代の流れ。
企業が変えるべきは、人ではなく「採用の仕組み」。
定着を「願う」のではなく、定着を「設計する」。
それが、これからの建設業が生き残るための採用戦略です。
関連note
- 「今の若者はすぐ辞める」ではなく、「今は辞めやすい時代」──採用の本質を変える視点
- 採用がうまくいかない会社の共通点:「求人広告を出す前に考えるべきこと」
- 面接で“いい人”を落とさないために──建設業が見落とす採用プロセス設計
- 採用に成功する建設会社の共通点は「求人の出し方」ではない
note販売ページはこちら → https://note.com/recruit_worker